Yumeトーク第60回
海洋音響センシング技術の秘められた可能性とは…。
SUMMARY
OKIの海洋音響センシングは、官公需要を中心に大きな実績を築き上げながらも、スポットライトが当たる機会が比較的少ない技術でした。しかし、この技術も、昨今のサステナブル・ブルーエコノミーという新市場の台頭とともに、大きく注目されはじめています。今回は海洋音響センシングに関わる5名のキーパーソンと藤原執行役員CINO兼CTOが、その技術・ビジネス戦略について熱く語ります。
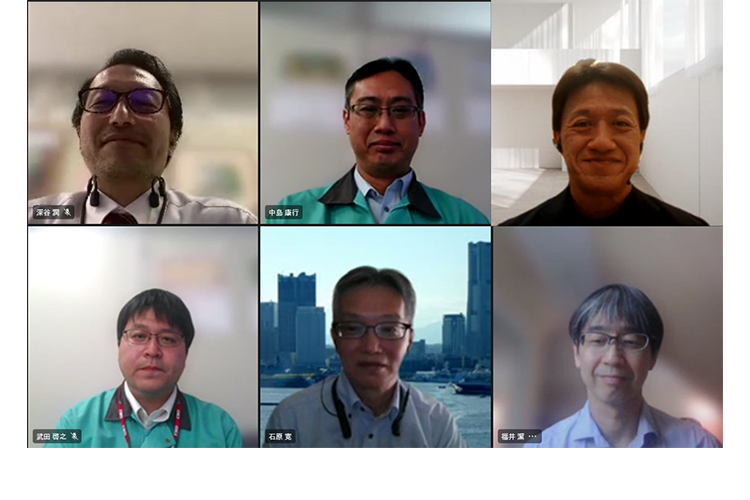
最新記事
民需向け「海洋データインフラ活用サービス」を展開
藤原社史を紐解くと、OKIは戦前から海洋音響センシング技術を手掛け、80年以上の実績があると記されています。これまで用途が限定されていた、このレガシー系の技術が近年、脚光を浴びているようですね。
深谷OKIは海洋音響センシングの分野で豊富な経験と実績を誇っていますが、これまでは、ソーナー、ソノブイなどの防衛向けや海洋資源調査など官需が中心でした。そこで、OKIとしては、4~5年ほど前から海洋IoTとして、この技術の民間転用に向けた技術開発と並行して、新市場開拓のための提案活動、さらにはそれらに対応した社内組織の再編などを進めています。
藤原新たな民間需要が生まれてきた背景には何があるのでしょうか?
石原さまざまな要因が挙げられますが、大きな流れを作ったのは、SDGsの目標のひとつである「海の豊かさを守ろう」を達成するため、海洋の持続可能な経済活動、いわゆるサステナブル・ブルーエコノミーという概念が生まれたことでしょう。そして、これらによる民間市場は、従来の防衛、官公市場の数十倍の規模になると予測されています。
藤原巨大な市場創出が見込まれる中で、OKIとしては、どのような市場開拓を狙っているのですか?
中島近年、水産資源を保護するため、大型船舶の航行や海洋土木工事による海洋生態系への影響を調査する、いわゆる環境アセスメントのニーズが拡大する中で、OKIとしては海洋モニタリング技術の提供を狙っています。将来的には、ソーナー用の光ファイバー水中音響センサーをスピンオフして、大型船舶や海洋生物の音を広範囲にわたって常時モニタリングするシステムを検討しています。
藤原従来、海洋調査と言えば学術調査といった官需が中心でした。近年は水産物の養殖、畜養の生産性向上や漁場監視などを目的としたOKIの「海洋データインフラ活用サービス」の提供を水産業、漁業関係者にアピールしています。
深谷具体的な事例としては、海中に水中音響センサーを設置し、船のエンジン音やスクリュー音、ダイバーの呼吸音などをリアルタイムに検出し、漁場への不審船、不審者の接近を監視する「密漁監視ソリューション」があります。これまでマリコン(マリンコンストラクター)や漁協などとProof of Concept(PoC)を重ね、2020年に商品化しています。
藤原私も客先、外部の会合やセミナーなどに出席して、密漁監視ソリューションの話題を出すと、皆さんから「いいところに目を付けられていますね」と、大いに関心を示していただいています。
洋上風力発電というビジネスチャンス
石原私たちは、さらに大きな市場として洋上風力発電関連事業に期待を寄せています。
藤原洋上風力発電は再生可能エネルギーの主役として、海外、特にヨーロッパを中心に普及が進んでいますが、国内での本格導入は、まだこれからですよね?
石原洋上は陸上のように地形などの影響を受けにくいため風況に恵まれています。また、景観や騒音など周辺環境への影響も少ないことから、この十数年の間に洋上風力発電はヨーロッパを中心に急速な導入が進んでいます。
日本でも、2020年に政府と民間企業で構成する「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」が、2040年までに約4,500基、40GW以上の洋上風力発電の導入目標を発表し、巨大なマーケットが立ち上がろうとしています。OKIとしてもこの好機を見逃すわけにはいきません。
藤原その洋上風力発電と海洋音響センシング技術の関係を説明してください。
石原洋上風力発電を建設する場合、適地を探す調査開発から始まり、海底の基礎工事、電気設備工事、風車タワーの設置などのプロセスがあり、運転開始後は運用・維持管理をしながら、30年後には解体・撤去されます。これら一連のサプライチェーンでコストの35%以上を占める運用・維持管理領域に着目しています。
風車タワー、送電用海底ケーブルなどの水中の構造物や敷設物の健全性・安全性を維持するためには、地上の構造物以上に入念なモニタリングが欠かせません。従来、ヨーロッパなどの風車タワーの点検・監視は、高いスキルを持つダイバーに依存していましたが、タワー設置件数の増加とともに、ダイバーの確保やコストの抑制が課題となっています。現在は水中ドローンと呼ばれるROV(※1)やAUV(※2)などの無人機の導入を進めようとしていますが、無人機と海上・陸上間の通信手段の確保など、いくつか課題も残されています。そこで、OKIとしては無人機によるセンシングや水中音響通信といった独自技術を活用したソリューションを提案しています。
海洋音響センシング技術とAIの融合で、OKI独自の価値を提供
藤原具体的には、どのようなソリューションでしょうか?
武田水中ではごく限られた周波数の電波しか伝わらず、しかも減衰が大きくその伝搬距離も限られているため、情報伝達の媒体として主に音波が使われています。しかし、音波の帯域は電波と比べ狭く、常時動画などの大容量なセンシングデータを伝送することができないため、OKIとしてはAIの活用も合わせて考えています。
深谷具体的には、水中カメラやセンサーとAIエッジコンピューター「AE2100」を搭載したROVが水中構造物の周囲を監視し、AIエッジが何らかの異常を検知した場合、その結果(静止画像)のみを音波で海上の母船へ伝送することで、情報の事前集約による通信負荷の低減を図る仕組みです。
藤原なるほど。OKIのAIエッジ処理と水中音響通信技術と海洋音響センシングを活用したモニタリングの無人化、リモート化によって、大幅な維持管理コストの削減が可能になるわけですね。
そこで、OKIの強み、BMCでいうキーリソースとして何が挙げられますか?
深谷水中マイクなどの各種センサーから、ドライエンドと呼ばれる信号処理・解析技術までワンストップで提供できることでしょう。また、海中の水温や塩分濃度、水圧などの影響で変化する音波伝搬状況を計算するノウハウがあることも大きな強みです。
石原さらに加えると、長年、社内の海上実験・試験などで収集してきた水中音のデータベースや、マルチパスを含めた音波伝搬も模擬できる水中音響シミュレーション技術があります。これを活用してAIに学習させることで、他社ができないようなソリューションが提供できるはずです。
福井私はOKIの920MHz帯マルチホップ無線「SmartHop」を活用したセンサーネットワークによるインフラ構造物のモニタリングシステムの開発に携わってきました。このような陸上の無線技術のノウハウを海洋音響通信に展開するため、このプロジェクトに参加しています。また、イノベーション推進センター(IPC)でPoCに取り組んでいるAIエッジロボットによる高度遠隔運用や橋梁など陸上のインフラ構造物のモニタリングサービス「monifi」を活用し、AUVが海中を自律的に巡回航行しながらモニタリングする「水中移動型センサープラットホーム」を構想しています。
着々と進む、市場開拓に向けた社内体制づくり
藤原目前に巨大市場が立ち上がりつつある。OKIにはキーリソースも揃っている。そこで、一番大事なことは、これをどのようにしてビジネスに結び付けるかです。海洋ビジネスはプレーヤーが多いのですが、OKIとしてはカスタマーセグメントをどこに絞っているのでしょうか?
石原主体となるのは再エネ発電事業者となりますが、環境アセスなどの調査会社、マリコン、風車メーカー、メンテナンス事業者など、プレーヤーは多岐にわたります。OKIとしての直接のお客様はマリコンやメンテナンス事業者となるのでしょうが、最終的には発電事業者がどのサプライヤーを選定するかで左右されるので、アクセス先を見極めるリサーチ力も磨かなければなりません。
藤原確かにアクセス先を見誤ると大変なことになりますからね。
石原海洋ビジネスは事業認可制度が厳しく、機器や装置の規格が地上のものと異なるなど、参入障壁が高い市場です。OKIとしても業界の特殊事情を調査・研究し、慎重かつ迅速に事を進めていくつもりです。
藤原このような民需向け海洋市場を開拓するため、OKIとしての体制づくりは進んでいますか?
石原海洋市場に関しては、これまで統合営業本部や私が所属するDX事業推進センターが主導していました。2020年度には特機システム事業部が新設され、2022年度には静岡OKIとOKIシーテックを統合した新子会社「OKIコムエコーズ」も誕生するなど、海洋ビジネスの事業体制は徐々に整いつつあります。しかし、これらの組織がバラバラに活動しては非効率なので、事業部とSE、研究開発など各部門の意思統一を図り、一体となって活動すると同時に、対外的な窓口の一本化を図るつもりです。
藤原これはCINOとしての私からの要望ですが、洋上風力発電という大きな市場、キーリソース、社内体制と条件が整っているので、是非、Yume Proチャレンジに応募してください。
深谷研究開発を進める中で、応募推進していきます。
石原洋上風力発電は大きなビジネスチャンスなので、使える制度は何でも使うという意気込みでいます。
藤原これからのOKIの目玉になる技術だと思います。何だか最後は、強引にYume Proチャレンジへと誘導してしまったようです(笑)。でも、Yume Proチャレンジはあくまでも手段であり、目的はビジネスとしての成功です。是非、営業、SE、研究開発が連携した全員参加型イノベーションで、大きなビジネスチャンスを掴みましょう。
深谷最後に、この場を借りてお願いがあります。OKIは音響センシング、水中音響通信の技術、ノウハウは持っていますが、ROV、AUVの技術がないので、共創パートナーが必要です。興味を持たれているメーカーの方のご連絡をお待ちしています。
※1 ROV(Remotely Operated Vehicle):遠隔操作型無人潜水機
※2 AUV(Autonomous Underwater Vehicle):自律型無人潜水機
【所属】 ※2022年3月17日取材当時
深谷:特機システム事業部 研究開発部 部長
中島:特機システム事業部 研究開発部 研究開発第二チーム チームマネージャー
武田:特機システム事業部 研究開発部 第一チームTM
石原:DX事業推進センター
福井:イノベーション推進センター ネットワーク技術研究開発部







