社会の大丈夫をつくっていく。――みんなで未来を描く、共創イノベーション「OKI Innovation World 2021」を開催(中編)

2021年10月18日、OKIのイノベーション活動を広く情報発信するイベント「OKI Innovation World 2021」(※1)を開催しました。OKI Innovation World 2021は、以下の3セクションで構成されています。
・Section 1 全員参加型のイノベーション
・Section 2 新たな価値を共創するイノベーション
・Section 3 垣根を越え、挑戦しつづけるイノベーター
中編では、「OKI Innovation World 2021」のSection2についてレポートします。
※1 OKI Innovation World 2021(OKI公式YouTubeにリンクします)
Section2:新たな価値を共創するイノベーション
考えるだけでなくやってみること、一歩を記せば景色は必ず動く
【Special Dialog】 起業のプロからみたOKIのYume Pro
●登壇者
・新規事業家 OKIシニアアドバイザー 守屋 実氏
・OKI 執行役員 イノベーション責任者(CINO)兼 技術責任者(CTO) 藤原 雄彦
パネルディスカッションに参加したCINO兼CTOの藤原が再度登壇。OKIのシニアアドバイザーを務めていただいている新規事業家の守屋実氏をお招きして対談を行いました。
藤原はまず、Yume Proの加速支援をお願いした2019年当時のOKIの印象について質問しました。
守屋氏は、新規事業開発に際してお客様先に行っていない、ヒヤリングしていないことが、当初の違和感だったと語りました。「事業開発に携わる方々からプランを聞いた際、お客様を訪問したかと尋ねると『どのようにして行けばいいのか分からないので行っていない』と答えた方が複数いました。それではモノができてもお客様に売りに行けませんから、まずいなと思いました」。
藤原も、「これまでのOKIは優良なお客様からの受注開発型ビジネスで収益を上げてきたため、当初は新規や別領域のお客様をどう訪問すればよいか分からず、皆が右往左往していました」と振り返ります。
「従来からのお客様とは訪問して話をしているはずです。新しいお客様に行けないのは、できるかできないかの話ではなく、単にやっていなかっただけ、慣れていなかっただけ。ですから、やればいいと促されて素直に行動し始めたら、できるようになりました。この2年で『お客様のところに行けない』と言う人がほとんどいなくなり、むしろ積極的に行くようになっています。この変化の度合は非常にいいなと思っています」と、守屋氏は評価しました。
次に藤原は、守屋氏の近著『起業は意志が10割』で興味を惹かれたフレーズを話題にしました。その1つめが、「マーケットアウト・プロダクトイン」という考え方でした。
守屋氏は次のように解説しました。
戦後のモノ不足の頃は“作り手が大事、作ればいい”のプロダクトアウトでしたが、モノとサービスが充実してくると“消費者に近づこう”というマーケットインの思考が加わりました。「しかし、あらゆるモノ・サービスが溢れている今は、作ったものをどうにかして売り込むというプロダクトアウト・マーケットインの考え方を逆向きにしたほうがよいではないか。作ったものに対する消費者の第一声は『いらない』の可能性もあります。ならば、消費者がほしいと思っているものを調達するくらいの姿勢、消費者から生産者へと矢印の向きを変えることが必要なのではないか。これを表した言葉が『マーケットアウト・プロダクトイン』です」。

この回答に対して藤原は、まだ受注開発型が多数を占める日本の製造業の考え方がどうかを尋ねました。
守屋氏は、「人は考えたようにはならない(おこなったようになる)」という持論を提示し、「たとえばマーケットアウト・プロダクトインという言葉・考え方を教えても、『なるほど』と思うだけでは実行する人にはなれません。本当にやってみることを繰り返して、それが身に付くと、実践する人になれるのです」と語ったうえで、大企業になるほど人が多いため、旧来通りのやり方に慣れた大勢の人の中で新しいことを考えてもやりにくく、結局は昔ながらのまま変わることができないケースが多いこと。一方でスタートアップ企業は、少数ながら全員が変わろう、やろうという意志を持っているためアクションしやすいことを指摘。「アクションを繰り返せば、いずれ身に付きます。つまり全員参加型で取り組むことが非常に大事です」と結論付けました。
2つめのキーフレーズは、大企業の新規事業に求められる要素を示した「3つの切り離し、2つの機能、1人の戦士」でした。守屋氏からは、それぞれに具体例を交えながら明快な解説がなされました。要点は以下のようになります。
・3つの切り離し:大企業は、強い本業を安定して遂行するために最適化されたあらゆる仕組みが身に付いているが、新規事業を立ち上げる際に、その仕組みが阻害要因になることがある。特に「資金」=上場企業ゆえの単年度会計や四半期ごとの業績開示、「意思決定」=何重ものチェックや会議、「評価」=厳格な予実評価(失敗して厳しく批判された経験・記憶)の3つは、新規事業開発の自由な活動やチャレンジを妨げる恐れがあるので切り離した方がよい。
・2つの機能:新規事業を立ち上げるのはお客様がいるからこそ。お客様のために一生懸命頑張る(お客様の課題と戦う)、お客様ニーズを他社と取り合う(競合と戦う)というように、社外で戦わなければならない。ただし一方で、社内での戦い――たとえば稟議を上げる、会議で説得する、根回しをする等々も結構多い。事業責任者が両方を背負うと、社外で戦う前に社内の戦いでエネルギー切れを起こしてしまうので、社外で戦う人たちが思い切り活動できるように、社内の戦いを一手に担う人が必要。新規事業開発には社外向けと社内向けの2つの機能を分けて備えておくべき。
・1人の戦士:新しい事業を作るには、PL(損益計算書)だけでなくBS(貸借対照表)もCF(キャッシュフロー計算書)も、組織のことも見なければいけない。新規事業の責任者には、大企業では財務部や人事部に分担されていることもチェックできるような1人の戦士、意志ある経営者候補が求められる。

藤原はもう1つ、守屋氏が監修した『DXスタートアップ革命』に書かれている「動いた人にだけ道は拓ける(どんなときも前に進め)」を取り上げ、解説を求めました。
守屋氏は、「新しいことというのはそもそも分からないことなので、脳内で妄想しているだけではたぶん何もできません。とにかく一歩を記せば景色が必ず動いていきます。最も早く学習することは最も早く動くことだと思います。そうしたことから、動いた人には必ず道が拓けるので、“まず一歩”の繰り返しをぜひお勧めします」と、アグレッシブなアドバイスを視聴者に送りました。
藤原は、OKI社内で新規事業案を支援する場として「守屋さん相談会」を2週間に一度実施していることを明かし、「その場でも社員に『やってみたらどうですか』とよく話をされていますね。OKI社内にも考えるだけでなかなか動かない体質が少なからずあるので、気をつけなければいけないと思っています」と話しました。
最後の質問は、「OKIの現状と今後やるべきこと」でした。
守屋氏は、「過去と現在の差分変化率をきちんと見ておくこと」を掲げ、「OKIはまだ、目指すところからすると道半ばだと思いますが、過去と現在を比べると着実にレベルアップしています。この変化率が非常に大事で、今後も緩めることなくYume Proの活動を進めれば目指すところに間違いなく近づくことができ、近づいたら目標をもう一段あげればいいのです。登り方を常に意識して行動を起こし、継続することが大事です」と述べました。
さらに、「そのことを積極的にアピールして世の中に知ってもらうことも続けてほしい。OKIを参考にして動き出す人が増え、日本にどんどん広がっていけばいいな、と思っています」と、イノベーションの牽引役としてのOKIへの期待も付け加えました。藤原からは「今後も強い意志を持って、Yume Proを推進し、OKIの全員参加型のイノベーション活動を世に中に広くアピールし続けていきます。」と締めくくりました。
切り口の異なるイノベーションへの取り組み3事例を詳説
【OKI’s Innovation】 OKIと共創パートナーのイノベーション事例
●Yume Proで加速するイノベーション
事例紹介のセッションでは、はじめにイノベーション推進センター長の前野蔵人が登壇。2018年度から本格化させた「Yume Pro」の活動概要――イノベーション・ダイアログに代表される「経営層による文化浸透」、Yume Proチャレンジをはじめとした「社員の実践支援」、2022年度末に6000名の受講修了を目指す「イノベーション研修」の3本柱で活動を推進していること、2020年度からの新規事業開発部隊と研究開発部隊の統合(イノベーション推進センターの設立)と、それに伴うYume Proプロセスの2系統化と連携(新規事業開発向けのビジネスプロセス、研究開発向けのテクノロジープロセスを策定)などを説明しました。

さらに、お客様やパートナーとの社会課題解決を目指す共創によるイノベーション事例として次の8つのケースの概要を紹介しました。
- ① 交通問題:NEXCO中日本様との共創による道路工事規制材の遠隔管理。ロボットの高度遠隔運用により高速道路上の工事現場の安全を確保
- ② 警備力向上:ALSOK様との共創による新たな警備モデルの確立。ローカル5Gを用いて警備ロボットやドローンの遠隔巡回・遠隔監視を実現
- ③ 労働生産性:日本航空様との共創による労働生産性の向上。OKIの映像・音響センサー解析技術を活用し、航空機整備の高度化(安全性・効率性の向上)を実現
- ④ 労働生産性:製造部門を持つお客様との共創による遠隔作業支援システム
- ⑤ 労働生産性:東京・渋谷のサンドイッチ店チェーン様と共創したスマートリコメンド。来店客の視線と表情から好みのメニューを提示することが可能。非接触・非対面環境、現場の効率化などに貢献
- ⑥ 老朽化問題:製造設備を持つお客様と共創を進めている多点型レーザー振動計。レーザーを用いて非接触で物体の振動を計測できる。「Yume Proチャレンジ2019」で大賞を受賞したソリューション
- ⑦ 老朽化問題:日本工営様との共創によるインフラ設備のモニタリングシステム。太陽光発電によるゼロエナジーゲートウェイを用いてデータ伝送することにより、山間部などのインフラでも給配電を気にせず24時間365日のモニタリングが可能
- ⑧ ヘルスケア:島津製作所様と共創した光バイオセンサー。光通信で培ったシリコンフォトニクス技術により特定バイオ分子を高感度に検出、ヘルスケア分野に幅広く活用可能
この他、東京・虎ノ門のOKI本社にあるイノベーションルーム「YumeST TORANOMON」にて、課題の洗い出しからスタートしたPFU様との共創の様子も紹介しました。
続いて、イノベーションの実践によって創出された2つのソリューションについて、それぞれの事業責任者がプレゼンテーションしました。
●IMSのプロセスで生まれた営業発の新商品 フライングビュー®
Yume Proプロセスを活用し、営業主導で創出した新商品「フライングビュー」について、ソリューションシステム事業本部 DX事業推進センター 統括部長の小川哲也が、商品化までの過程を紹介しました。

「フライングビュー」は、4台のカメラ映像から生成された俯瞰合成映像とAIを用いた映像監視により、車両や船舶、ロボットなど移動体の周囲(360度)を遠隔から自由な視点で監視できるリアルタイムリモートモニタリングシステムです。さまざまな共創パートナーと多数のPoCを重ねて商品化に漕ぎつけ、2021年10月14日に販売開始しました。
そのアイデアは2016年、営業部門内に発足した「ビジネス開発室」で生まれました。マーケティングとイノベーションで営業初の新商品を作り出そうと、まずはOKIグループ全体のバリューチェーン上の強みを探索すべく、グループ企業も含めたさまざまな部門へのヒヤリングと分析を徹底的に行いました。その活動の中で見つけた技術が、コンポーネント&プラットフォーム事業本部の関連企業であるOKIアイディエスが保有していた運転支援用(駐車時などに活用されるサラウンドビューモニター機能を提供)のFPGAでした。
「自動運転の期待が高まる市場、運転を支援するFPGA技術、5G時代の到来という3つの要素を掛け合わせると、『スムーズな遠隔サポートを実現するための360度自由視点映像が必要になるはず』。これが、フライングビューの初期の事業仮説になりました」と、小川は振り返りました。
次のステップでは、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)で仮説磨きを進めました。ビジネス開発室で5名のチームを編成し、OKIアイディエスと打ち合わせを重ね、試作・実験を繰り返しました。このとき、皆から“秘密工作員”との愛称で呼ばれていたメンバーが、搭載カメラの位置調整作業を大幅に軽減する画期的な「4カメラボックス」を発案・試作し、それによって仮説検証が一気に高速化しました。
小川は、当時のチームの特徴として、①イノベーションに必要な共通言語を全員が理解していた、②異能の集団だった、③少人数ゆえに素早く動くことができた、の3つをポイントにあげ、「激しく議論を戦わせた中からアイデアが出てくるということが繰り返し起こりました。イノベーションの初期段階においては、この3つが非常に重要ではないかと、体験的に感じています」と付け加えました。
いよいよ事業本部本体と合流し、パートナーとの共創を本格化させていくフェーズに入りました。展示会への出展などを含め積極的なプロモーションで共創パートナーを増やし、現在は計28社にのぼっています。事業部門が作成した試作機で多数のPoCを回し、機能や品質の改善・向上を図りました。ここではPoCの具体例として、①愛知工業大学様との遠隔運転技術に関する共同研究、②会場技術安全研究所様との遠隔操船に関する実証実験、さらに、先に前野も紹介した③ALSOK様とのローカル5Gを使った遠隔警備の高度化に関する実証実験、④NEXCO中日本様とのロボットを使った道路工事規制材の遠隔管理に関する共創について、画像・映像を使って詳説しました。
最後に小川は、フライングビューの商品化までのプロセスが、IMSのプロセスや原則にずばり合致していたことを強調。また、イノベーション活動の全体の見える化と戦略立案の支援に寄与するマネジメントツールやナレッジツールを構築・試行中であることも明らかにしました。そして、「イノベーションとマネジメントは真逆の概念のように見えますが、適切なマネジメントこそがイノベーションを生み出す唯一の方法であると確信しています」と力強く語りました。
●プリンターコア技術から新たな価値へ転換、異種材料融合ソリューション
コンポーネント&プラットフォーム事業本部 開発本部 チームマネージャーの谷川兼一が、プリンターの露光システムに用いてきたコア技術を駆使した新たな市場開拓への取り組みを紹介しました。

谷川ははじめに、あらゆる機器が通信をする超スマート社会(2030年頃)の課題として、データ通信量の増大に伴うIT機器の消費電力増加、技術革新がなければ発電量を超えてしまうという試算もあることを提示し、「高機能化社会の加速と消費電力の抑制を同時に実現することが目指すべき課題です」と話しました。
その解決策とする異種材料融合とは、「LEDとICなど異種材料デバイスを融合する半導体製造技術」を指しています。具体的には、LED表面の極めて薄い機能部分だけを剥ぎ取り、フィルム状にしてICに直接接合します。ここでOKIは、分子間力を適用して直接接合を実現する技術を保有。2006年に世界で初めてLEDとICの融合チップの量産化に成功し、LEDプリンターの露光システムに搭載して、これまでに5億チップの出荷実績をあげています。
このコア技術から新たな価値として導き出したソリューションが、①マイクロLEDディスプレイと②半導体デバイスへの応用です。谷川はそれぞれの内容に話を進めました。
マイクロLEDディスプレイは、有機ELの次の世代のディスプレイとして注目されている高性能・低消費電力の製品です。LEDを剥いで貼る技術を活用することは分かっていましたが、業界や市場の構造を一切知りませんでした。そこで、業界に関連する180社程度をすべて分析し、約40社にインタビューも行って、ビジネス視点と技術視点の両面からOKIが市場参入できるモデルを描いていきました。
マイクロLEDディスプレイの課題は、新技術のために量産実績がないこと。具体的には、接合・転写の速度、接合の精度の2点が高いハードルになっていました。OKIの分子間力を用いた接合は、金属共晶という一般的な方法に比べて接合の速度で520倍、精度も5倍と圧倒的に優位で、プリンターでの量産実績があり、しかも出荷した5億チップで接合が剥れたというクレームがゼロと信頼性も証明されています。
谷川は、ソリューションの提供形式や特徴にも言及しました。「異なる色(RGB)の材料からそれぞれLEDフィルムを作り、それを提供基板上で集積化します。2次元に配列させる方法でもスタックして3Dにする方法でも、また、画素単位でもパネル単位でも提供が可能です。しかも、分子間力で電気接合も一緒に取れるため、手間なく導入でき、テスト後のリペアも可能になっています」。
もう一方の「半導体デバイスへの応用」は、LEDがそもそも半導体であることから、薄い機能層を剥離し分子間力でダイレクトに接合する技術を、他の種類の半導体にも応用展開しようというものです。
谷川は、4つの可能性――①機能の集積(高性能材料を剥離し集積・融合)、②光伝搬(光をダイレクトに伝搬)、③微小電気接合(数㎛で1メガ個の電気接合が可能)、④熱マネジメント(ダイレクトに熱伝導/断熱が可能)について解説したうえで、「ソリューションの提供はLEDとほぼ同じフレームワークで、各種の半導体から剥離したフィルムを提供基板に集積し、必要な加工を行います。お客様側の工程で分子間電気接合ができる異種集積チップ、お客様側でデバイス加工できるような異種材料融合基板など、ご要望にフィットする形式での提供が可能です」と述べました。
そして、「この異種材料融合ソリューションを幅広くご提案することで、お客様のデバイス性能向上を通じて、冒頭に掲げた複数の社会課題を解決し超スマート社会に貢献していきたいと考えています」との言葉で結びました。
●物流DXの推進による課題解決と今後の取組
Section2最後の講演は、OKIとの共創によって物流DXを推進している株式会社ロンコ・ジャパン様にお願いしました。同社 代表取締役社長の福西靖之氏、営業本部DX推進課 課長の安光大二郎氏が、業務現場の課題解決に向けた取り組みの現状と今後の展望を語りました。
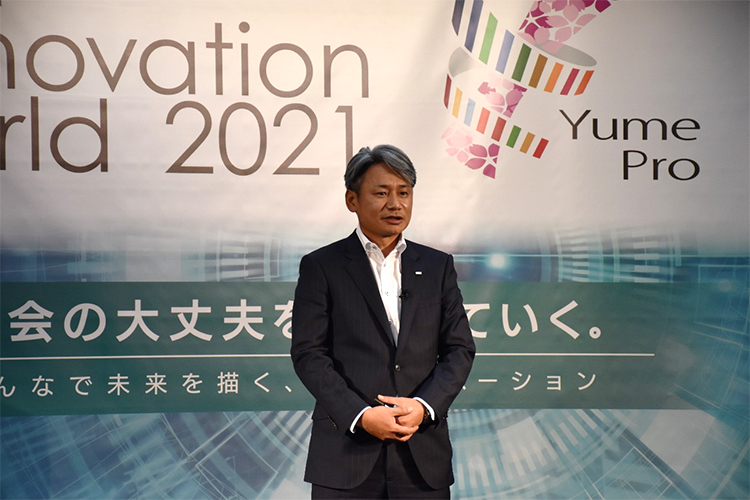
大阪府大阪市に本社を構えるロンコ・ジャパン様は、物流戦略・システム構築から物流施設開発、物流センター運営、人材派遣まで物流機能を幅広く網羅した事業を展開。物流・輸送合わせて全国45拠点、車両446台を有し、大型の幹線輸送を得意としています。2021年9月からは「ロンコ ロジスティクス アカデミー」と銘打ち、物流知識を主としたWebセミナーや企業研修などを提供するアカデミー事業もスタートさせています。
そして1年半ほど前からスタートしたDX事業について、福西氏は「物流DXという言葉が流行り始めた際、我々も何かできないかと考えて取り組んできました。社内業務では、たとえば各事業部からの日次売上・利益報告の自動解析をはじめRPAを積極的に導入しています」と説明しました。
さらに、運輸業界が直面する3つの課題――将来にわたる人手不足、運送業務における“手待ち”と呼ぶ待ち時間の無駄、デジタル化の遅れを、さまざまなデータを紐解きながら提示したうえで、同社がいま「物流業界の社会的ステータス向上とサステナブルな物流の構築」に挑戦していることを明かしました。その中身の1つに「属人化した業務を平準化し効率的な業務へ」という課題があり、「解決策を追求すべくOKIに相談したところ、『できるかもしれません』との返事をもらい、共創へと踏み出しました」。
ここで福西氏から安光氏にバトンタッチし、具体的な取り組み内容が紹介されました。
安光氏は、共創を進めるにあたって重要なポイントが2つあったと振り返りました。「1つは“パートナーをよく知ること”、もう1つは“目的を明確にし、共有すること”でした」。前者について、ロンコ・ジャパン様はOKIにショールームに足を運び、OKIもロンコ・ジャパン様の拠点で終日業務見学を行い、互いの事業・業務を理解し合いました。後者に関しては、もとより「物流業界の課題を解決したい」という想いで一致していました。
両社で議論を交わした際、当初は業界課題解決のための物流プラットフォーム構築という大目的が掲げられましたが、現実的なやり方として「部分最適をつなげていくことによって全体最適を目指す」という結論に至りました。そして、喫緊の業務課題を解決すべく、小売業の顧客から請け負っている店舗配送業務にフォーカスした配車システムの開発から着手することにしました。

ロンコ・ジャパン様では、店舗配送のための配車業務を、1人のベテラン社員が一手に担っていました。1店舗への配送品を2つに分割するルールで指定時間内に最小の車両台数・最小の走行距離で納品完了させる配車作業を、長年の経験に基づいた職人的な感覚でこなしていました。また、配送ルートが毎日変わることから高速道路の利用条件をドライバーにある程度任せていました。こうした属人的な仕組みから脱却するためのシステム開発でしたが、実は顧客側でも以前にシステム開発に取り組んだものの実現できなかったという事実もありました。
安光氏は、「現場で使えないものを作っても意味がないので、2つの要望をOKIに提示しました」と話します。それが①各車両の配送終了時間を均等にすること、②コストよりも安全や安定を重視する場合があること――たとえば降雪が予想される時は最短ルートを回避する設定も可能にすることでした。
完成したシステムは、①②の要件を十分に満たす機能が実現されていました。さらには、大きな導入効果をもたらす2つの付加機能も具備されていました。まず、車両の最大積載量に応じた店舗ごとの配送品の分割数を算出したうえで全車両の合計走行距離が最小となる最適解を導き出す「自動分割機能」。もう1つが、ドライバーに対して日々の配送ルートの中で高速道路を利用する区間を一定ルールに基づいて自動判定し指示を出せる「高速道路利用ルール」設定機能です。
安光氏は、システム活用効果の試算値も提示。1日の走行距離の最小化に関しては、シミュレーションした3日間のうち最も物量が多かった日で12.6%・550kmの削減効果、月次の高速道路利用コストについては、今年8月の実績との対比で11.1%・約36万円の削減効果が得られたことを説明し、「この素晴らしいシステムをいよいよ現場に実装していく段階まで来ました」と現状を語りました。
さらに安光氏は、運輸業界における2024年4月からの新たな規制――働き方改革関連法の適用猶予が終了し、時間外労働の上限規制が課せられること――によって生じる問題、たとえば土曜日稼働の扱い、労働時間抑制のため高速道路を積極利用した場合のコスト負担、待機時間などの無駄やドライバー1人での輸送距離の見直しなどを、具体的な数値で解説。
そのうえで、こうした課題の解決策として、OKIが提供している「LocoMobi2.0®」に対する期待を次のように語りました。「LocoMobi2.0は、モバイル端末向けアプリもしくはETC2.0対応車載器を使って情報を吸い上げるソリューションなので、まずは現状の運行を見える化し、どんな無駄が生じているかを把握できます。さらに、ETCと連動しているので、車両の通過情報を倉庫側と共有すれば手待ちや荷役時間の削減など業務効率化を図ることができます。2024年に向けて、運行データを分析して課題を明確にし、解決策を講じていく作業をOKIと一緒に進めていきたいと考えています」。
講演の終了に合わせてOKIの前野が登壇し、お礼とともに「共創に取り組む前後でOKIの印象はどう変わりましたか」と質問しました。
これに対して福西氏は、「最初に接点ができたときは、『相手にしてくれるのか』と少し疑っていました」と苦笑した後、「しかし、いろいろと進めていくと、レスポンスの速さとクオリティの高さにびっくりし『さすがだな』と思いました。現在も進行中の取り組みの中でも、本当にいいものを作っていただけているので、我々もOKIと一緒に、物流業界の改革に貢献していきたいと考えています」と、今後の意気込みも込めて返答しました。







