社会の大丈夫をつくっていく。――みんなで未来を描く、共創イノベーション「OKI Innovation World 2021」を開催(前編)

2021年10月18日、OKIのイノベーション活動を広く情報発信するイベント「OKI Innovation World 2021」(※1)を開催しました。2回目となる今回も、コロナ禍を踏まえてオンライン形式(OKI公式YouTubeでライブ配信)としました。
昨年12月の第1回では、代表取締役社長の鎌上信也が、①OKIのマネジメントシステムにイノベーション・マネジメントシステム(IMS)を組み込む活動を国内他社に先駆けてスタートすること、②IMSの認証規格ISO 56001標準化に備えてグループ全体でいち早く認証を取得できるようIMS Readyな会社を目指すことを発表、その中で、IMSを共通言語とした「全員参加型イノベーション」を実現していくことも宣言しました。
今回は、この「全員参加型イノベーション」をキーワードに据え、経営陣から各部門のマネージャー・リーダー職、中堅・若手社員まで幅広い層のメンバーが、取り組みの現状や成果、課題、さらに共創によるイノベーション創出の具体例などについて語りました。
OKI Innovation World 2021は、以下の3セクションで構成されています。
・Section 1 全員参加型のイノベーション
・Section 2 新たな価値を共創するイノベーション
・Section 3 垣根を越え、挑戦しつづけるイノベーター
前編では、Section1の模様をレポートします。
※1 OKI Innovation World 2021(OKI公式YouTubeにリンクします)
Section1:全員参加型のイノベーション
「一人ひとりが深く考える」ことを社員全員で実践
【Opening Talk】
まずは開演の挨拶を兼ねて登壇した鎌上社長が、「全員参加型イノベーション」を宣言した意図を明らかにしました。
鎌上社長は、社内改革の1つとして進めている「矢印革命」――お客様の要求を受けて高品質な製品を作る「受注型ビジネス」から、お客様・パートナーとの共創により社会課題を解決する「提案・発信型ビジネス」への転換(「お客様→OKI受注」から「お客様←OKI提案」へ矢印の向きを180度変える)を説明、そのうえで、矢印革命とは「考える文化の醸成」であるとし、さらに全員参加型イノベーションへと結びつくことを次のように説明しました。
「考える文化とは、社会課題の本質は?私たちにできることは?真の顧客価値は?迅速に解決するには?――といったことを、社員一人ひとりが自分事として深く考え、意志を持って取り組むことです。とはいえ、複雑化する社会課題の解を見出すには、一人で考えていては限界があります。部門の垣根を越え、またパートナーやお客様と一緒に、議論を繰り返し行い仮説立案・検証をしていくことによって、独りよがりでない真に求められる解、新しい価値を導き出すことができます。そのために、一人ひとりが自分事として考えることを全員が実践していく。これが、すなわち『全員参加型のイノベーション』です」。

OKIのIMS「Yume Pro」を全社のマネジメントシステムに組み込む、すなわち、イノベーションプロセスを業務プロセスに取り込むことも、「全員が考える」ための具体的な方法・手順を確立し明示することが狙いでした。
その「Yume Pro」の策定を進めた2017年を振り返り、決して平坦ではなかった道のりも詳らかにしました。「当時のOKIには、イノベーションを流行り言葉の1つと他人事のように捉え、現業で食べていけるという甘えが一部にあると感じていた」と指摘、ここからプロジェクトを発足して社内課題の把握から着手しました。マネジメント層のベクトルを合わせるために行った膝詰めの議論では、評論家的発言、知ったかぶり、ビジョンごっこのような意見も多々あったものの、「意志を持って自ら行動し変革するという信念」で、経営層全員の合意を得ることができました。そのコミットメントを社内に浸透させていくことも、「一過性の活動では、社員一人ひとりに正しく伝えることはできない」と考え、社長自らが社員と膝詰めでコミュニケーションする「イノベーション・ダイアログ」をスタートしました。コロナ禍においてもオンラインで開催を継続しています。
さらに、強いリーダーシップのもと全員参加型のイノベーションを推進してきた成果の一例として、2018年から実施しているOKIグループ内のビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」にも触れ、「3年間で応募件数は約4倍に、お客様との仮説検証を利用した応募アイデアも増え、量・質ともに向上しています」と、イノベーション活動が加速、レベルアップしていることを強調、「社員の具体的な活動から生まれた事例も多数ご紹介しますので、楽しみにしてください」と視聴者にアピールし、スピーチを締め括りました。
部門の壁を越えた連携が着実に進展
【Special Session】
●登壇者
・一般社団法人 Japan Innovation Network
・OKI 執行役員 統合営業本部副本部長 圓尾 肇
・OKI 執行役員 ソリューションシステム事業本部副本部長・DX/イノベーション統括 田中 信一
・OKI 執行役員 イノベーション責任者(CINO)兼 技術責任者(CTO) 藤原 雄彦
続いて、日本におけるイノベーション推進の第一人者である一般社団法人 Japan Innovation Network(JIN) にモデレーターをお願いし、OKIの執行役員3名――統合営業本部副本部長の圓尾肇、ソリューションシステム事業本部副本部長・DX/イノベーション統括の田中信一、イノベーション責任者(CINO) 兼 技術責任者(CTO)の藤原雄彦がパネリストとなって「全員参加型イノベーション」の現状や課題について語らいました。
JINは冒頭、自社で実施した『日経ビジネス』読者1000人(平均年齢50歳前後、多くが上場企業・半数以上がメーカーに勤務)へのイノベーション活動に関する調査を紐解き、「一様に、強烈に進んでいる産業構造の変化の中でどうイノベーションを起こすかに苦しんでいる」「自社の活動に手応えを感じられない人が7割」といった調査結果とともに、「OKIが掲げる『全員参加型イノベーション』あるいは『矢印革命』のようなレベルの考え方に基づいて、一定のフレームのIMSを構築しているという回答は皆無と言っていいくらいでした」と述べました。
そして、パネリスト3名に対して「見知った仲であり、今日は忖度、取り繕い、いいかっこしい等はなしに、ぶっちゃけて話をしましょう」と、和んだ雰囲気を作りました。
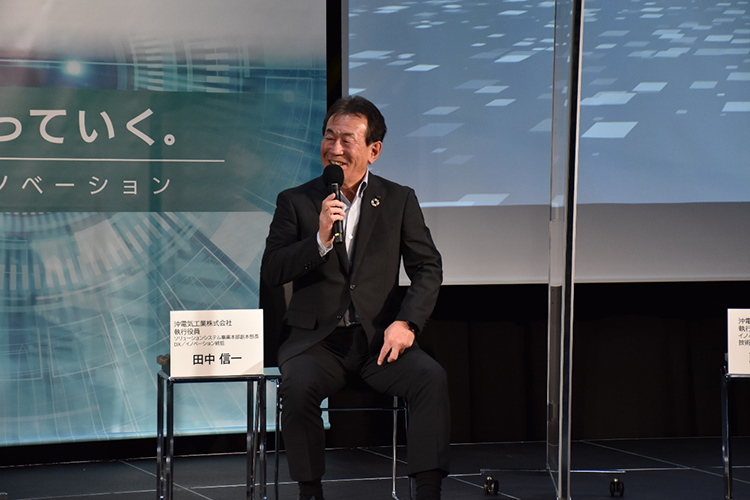
最初のテーマは「イノベーションに取り組む前と後で、現場は何が変わったか」。
田中はまず、3年間で飛躍的に共創パートナーが増えたことをあげ、「SIerやプラットフォーマー、同業他社だけでなく、お客様もOKIとパートナー関係になって新しいことを考えていこうという動きが目立ってきました」と説明。また、お客様課題の解決にあたってさまざまな部門に相談することが増えた=社内の情報共有力が強まったこと、共創パートナーを増やすために社外への情報発信力も強化されたこと、IMSを共通言語として営業部門と事業部門の会話(情報交換)が密になったことを提示し、「イノベーションを興すには、やはり単独では何もできないということを直接的に感じています」と述べました。
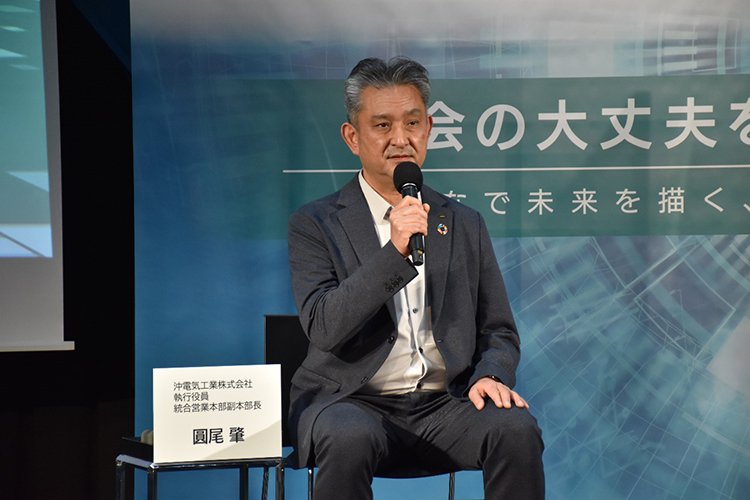
圓尾は、事業部門と営業部門の連携に加えて、研究開発部隊と営業部門も近しくなったと語りました。「以前は、研究開発者に現場の課題など相談してはいけないのではという思い込みがありました。しかし組織が変わり、イノベーションを共に学び、会話をするようになる中で関係性が大きく変わりました。現場の営業マンがお客様課題について研究開発メンバーに直接相談し、一緒にお客様を訪問し、帰ってきて議論を交わすというシーンがかなり見られるようになりました。これは革命的なことだと思います」。
さらに、ビジネスモデルキャンバス(BMC)が共通ツールとなって営業、SE、技術が会話しやすくなったこと、経営陣からの積極的なメッセージが営業の励みになっていること=経営と営業現場の距離短縮も、イノベーションで大きく変化した点に掲げました。
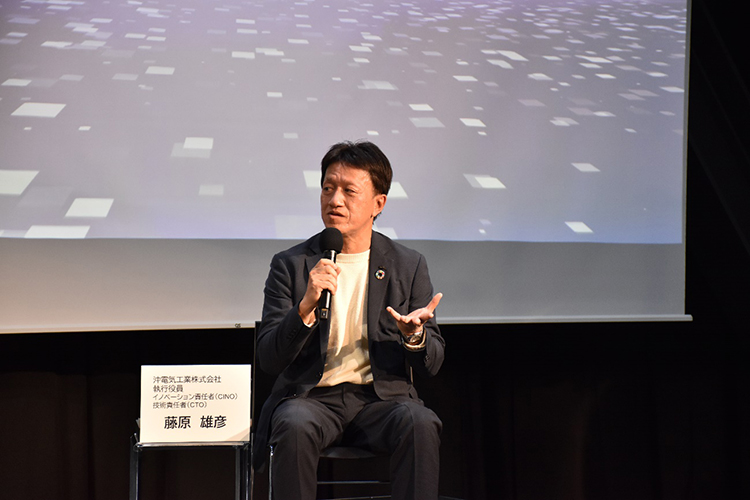
これまでイノベーションを牽引し、イノベーション責任者 兼 技術責任者の任を受けた藤原も、部門の壁を越えてイノベーション活動が広がりを見せている手応えを次のように語りました。「実は、ソリューションシステム事業本部では社内でいち早くイノベーション推進部を本部内に設置した経緯があって、『先に始めたのはこっちだ』と田中によく言われていました(笑)。IMSという共通言語ができたことで、田中とのコミュニケーションはますます多くなり、『イノベーション推進センターと事業部門で一緒に提案していこう』という流れも強まっていきました」。
さらに「営業部門から『お客様側の中長期な取り組みに対応するため、研究開発段階の柔らかいものから提案したい』という声を受けて、研究開発メンバーが一緒に動くようになりました。研究者側も、組織改正によって新規事業創出を意識するようになり、『自分たちもお客様に会って声を聞かなければだめだ』という気持ちが芽生えてきています」と続けました。
2つめのテーマは「現場での全員参加型イノベーションの現状」。JINは、「全員参加型というからには、相当な数の人がイノベーション活動に参加していなければ嘘になります。OKIの現場で、誰がいつ、どうやってイノベーション活動に実際に参加しているのか。実態はどうなのでしょう」と投げかけました。
圓尾は、営業現場の現在の取り組みを示すキーワードをあげ、次のように説明しました。
①失敗を責めない:特に「挑戦した失敗を責めるな」とトップマネジメントから強く注意喚起している。これまで、失注や未達などの結果に対して、鼓舞する狙いも込めて叱咤するケースがあったが、現在は「よく挑戦した」という言葉を積極的にかけている。
②打席に立つ:同じ打率(成功率)なら数多くチャレンジしたほうがいい。「100分の10」「200分の20」といった表現で、「1割でも成功すればOK。ならば10回に1回ではなく、100回に10回、200回に20回の成功にする」ことを推進。打席数を増やすための工夫をした社員を表彰する制度も設け、好事例の横展開も図っている。
そして、「こうした取り組みを通して、③お客様の課題に素直に向き合うということを支援、後押しする動きが営業部門内に広がっています」と付け加えました。
田中も、事業部門でもここ1年、チャレンジに対する評価制度が充実してきたことを明かし、「これまでは成果主義、見方が収益視点でしかなく、ある程度失敗を出さずにプロジェクトをやり遂げて収益をあげた社員を称えるという文化でした。しかし今はチャレンジに視点を向けた評価が非常に高くなっているので、部員側の考え方も変わってきていると感じています」と話しました。
ただ、JINからの「評価制度はもう定着しているのか」との問いに対しては、「そのレベルには達していません。イノベーション推進の諸施策への参加者は増えているものの、『イノベーションに携わる』という自覚を持つ社員がどのくらいいるかと考えると、まだ全員参加型には到達していないと思います」と述べました。
この返答に藤原も頷き、「IMSを全社展開し業務プロセスに活用するという昨年12月のアナウンスは、社内にも大きなインパクトがあり、『新しいビジネスを興そう、現状業務も革新しよう』という気運が高まりました。とはいえ、社員が扱いやすく実践しやすい規格・手順でなければ単なるお飾りになってしまうので、全社プロジェクトで整備をしている最中です。全員参加型の実現目標である2022年度末まであと約1年半ですが、とにかく少しずつでも社内文化が変わるように活動していきたいと考えています」と話しました。
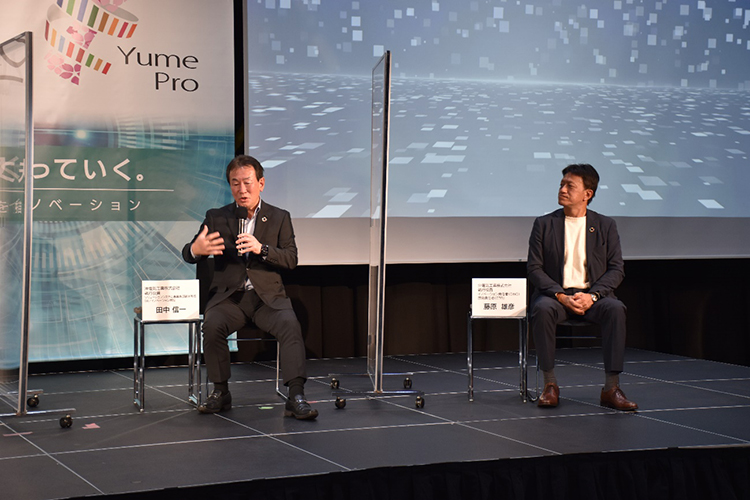
ここで田中が、2021年7月に開催したOKIで初めてのビジネスマッチングコンテストの成果を紹介しました。パートナー企業など約20社と新規ビジネス創出について面談する機会である同イベントに対して、当初は各事業部門とも「あまり関係ない」と消極的でしたが、「全員でやるんだ」と旗を振り、全部門が参加したところ予想よりも盛り上がり、しかも80弱のセッションを行って半数近くが現在も商談、協議を続けています。「少し強制的でも皆を呼び集めて参加させれば、イノベーションに対するマインドはこんなに醸成されるのだと実感しました。今後もぜひ継続的に開催していきたいと思います」と、田中は意気込みを語りました。
JINは、「まさに革命の真っ最中で、手応えも掴んでいるわけですね」との言葉に続けて、「とはいえ、IMSの世界はひたすら成熟度を上げていく、ある種の終わりなき旅といえます。そういう前提で、たとえば来年までにどこまで到達したいか、どんな手を打ちたいか、さらに成熟させるために何が必要と考えているかを、一言ずつお願いします」と、今後の課題を最後のテーマとして掲げました。
圓尾は、まず事業部門と営業部門の会話をもっと増やし、OKIの総合力を見せられるような工夫をさらにしていくこと。もう1つに、営業の現場も含めて外部の人財を少し入れてみることをあげて、「OKIのやり方を経験していない人と一緒にいろいろ取り組むことも大事ではないかと思います」と語りました。
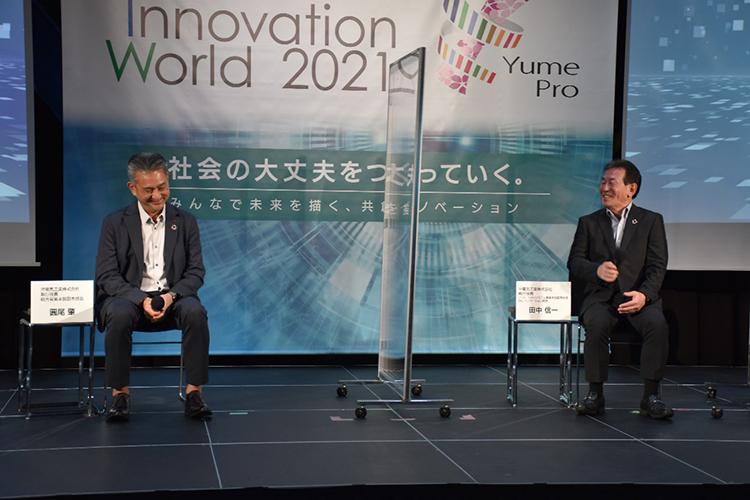
田中は、イノベーション関連の情報共有に関して、組織の縦割りの壁がまだ内在していると指摘、「IMSの定着と併せて、社内の情報と人の流れに関する悪い部分を取り払ってスムーズにしていきたい。これを経営側の視点で皆を支援しながら進めていかなければいけないと感じています」と述べました。
藤原は、先に掲げたIMSを浸透させるための規格・手順の整備に加えて、社内だけでなく社外への情報発信――OKIが何をやっているか、現状はどうかを継続的・積極的に伝えることも重要視し、「それによって、お客様やパートナーと一緒に社会課題を解決していくことをさらに追求していきます」と力を込めました。
ひと通りのディスカッションを終えて、JINはIMSに関する世界の潮流――中国では、ISO 56002が日本のJISに相当する国家規格としてインプリメントされたこと。米国では、QMSからイノベーションは起こらないとの割り切りからQMS+IMSで全体のマネジメントシステムを構築する取り組みが活発になっていること。欧州ではEU規格がISO56002に置き換わり域内全体の共通言語として連携・共創が進んでいること――を解説。これらとOKIの取り組みを比較して、「全員参加型イノベーションは、世界的にも非常に先進的な取り組みだと思います」と話し、「経営トップが『いま社内に革命が起こっている』と、さらっと言えるのはすごいことです。全員でアイデアを発掘して育み、そして社会の大丈夫を作るということが、OKIがやろうとしている全員参加型イノベーションだと理解しました。以前から存じ上げている会社ですが、今日の話でさらに理解が深まりました」とのコメントでセッションをまとめました。
Section 2以降は、後編にてレポートいたします。お楽しみに。







