社会の大丈夫をつくっていく。――みんなで未来を描く、共創イノベーション「OKI Innovation World 2021」を開催(後編)

2021年10月18日、OKIのイノベーション活動を広く情報発信するイベント「OKI Innovation World 2021」(※1)を開催しました。OKI Innovation World 2021は、以下の3セクションで構成されています。
・Section 1 全員参加型のイノベーション
・Section 2 新たな価値を共創するイノベーション
・Section 3 垣根を越え、挑戦しつづけるイノベーター
後編では、「OKI Innovation World 2021」のSection3についてレポートします。
※1 OKI Innovation World 2021(OKI公式YouTubeにリンクします)
Section3:垣根を越え、挑戦しつづけるイノベーター
圧倒的な顧客志向、その先にイノベーションがある
【Innovators’ Talk】
●登壇者
・eiicon company 代表 中村 亜由子 氏
・OKI ソリューションシステム事業本部 金融・法人ソリューション事業部 高橋 秀也
・OKI コンポーネント&プラットフォーム事業本部 開発本部 古川 雄一(リモート参加)
・OKIクロステック 人事総務部 山本 正直(リモート参加)
・OKI 統合営業本部 マーケティング&サポート本部 吉原 和英
・OKI イノベーション推進センター ビジネス推進部 武市 梓佐
最後のセクションでは、OKIグループで積極的にイノベーション活動に挑戦している社員5名が、各々の取り組みとその成果、今後に向けた熱い想いを語りました。
モデレーターには、オープンイノベーションのプロフェッショナル集団であるeiicon company代表の中村氏をお迎えしました。高橋、吉原、武市の3名はイベント会場にて登壇、古川と、山本は、群馬県高崎市の高崎事業所内に新しくオープンしたイノベーションルーム「Yume ST TAKASAKI」からオンラインで参加しました。
まずは各メンバーが、略歴や担当業務など自己紹介を行いました。
高橋は入社して22年目。エンジニア、SEを経て、運輸・流通市場のアカウントSEとしてソリューション提案などの業務に7年ほど携わりました。今年度から幅広いお客様に向けたDXソリューションの企画・提案を担当。現在は主に電力会社や鉄道会社が保有するインフラ設備のスマート保安ソリューション(IoTやAIを活用したリモート設備点検を実現)の推進に携わっています。

吉原は、2000年にOKIグループの保守事業会社に入社。保有する無線資格を活かしたメンテナンス業務に従事しました。その後、ネットワークインテグレーション事業会社に異動し、電気通信事業法改正を捉えたISP事業者向けビジネス、改正省エネ法施行を見据えた環境情報収集サービス「Webセンシング」など、新規事業の開発に注力。2012年にはOKI本体に異動して920MHz帯無線の開発メンバーに加わりました。現在は、改正銀行法に着目し、地域金融機関への非金融ビジネス(地方創生や地域DXに関わる事業)の提案活動を進めています。

武市は、3年前にキャリア採用でOKIに入社し、当時新設されたイノベーション推進部のメンバーとして業務をこなしてきました。所属部門は、Yume Proプロセスに則って新規ビジネスへとつなげるコンセプトの創造、お客様やパートナーとの共創、ソリューション開発などを手がけ、事業部門へと引き継いでいく役目を担っています。武市自身はヘルスケア領域を担当し、人の行動変容や行動の習慣化をサポートするシステム作りに取り組んでいます。

古川は、プリンターのトナー・インクの技術者として開発に12年ほど携わった後、情報機器やプリンター向けのAI開発という異なるジャンルの道へ進みました。そのきっかけが「AI-CoP」(AI-Community of Practice)というエンジニア向けのAI知識・スキル習得を目的としたコミュニティでした。古川は現在、AI開発業務に加えてAI-CoPの運営も手がけています。
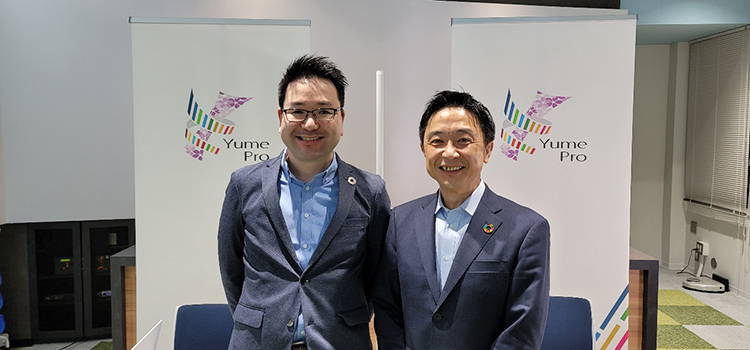
山本は、ICTシステムの構築や電気通信機器の施工・保守などを手がけるOKIクロステックで、教育・訓練計画の立案・実施管理業務を担当しています。その1つに、現場スタッフのスキル向上を目的とした技術訓練があり、年間のべ約5000名に実技の研修を行ってきました。しかしコロナ禍によって、集合形式での研修がままならなくなり、実機を用いた訓練もできない状況になりました。そこで、OKIが開発した遠隔支援システムやスマートグラスを技術訓練に活用することを考案。既存業務の変革という形でイノベーションを実現しています。
本題へと移り、中村氏は1つめのテーマ「顧客への課題解決で見えてきたコト」を、吉原と高橋に投げかけました。
吉原は、920MHz帯無線を使ったセンサーネットワーク構築での経験を語りました。
「お客様からの要件が厳しい内容であることは間々あり、センサーの選択肢がコスト的に制約される場合も少なくありません」。とはいえ、安価なセンサーは機能も限られるため、お客様課題の解決が非常に難しくなり、案件の受注自体も危うくなります。そうして追い込まれていくと、「収集データを本当に必要なものだけに絞ったり、計測タイミングの調整や粒度を落とすなど、さまざまな工夫、あらゆる手を尽くすことで、結果的に高機能なセンサーを代替するような仕組みを実現しています」。吉原は、メンバーとともにこのような実践・体験を何度もしてきたことが、まさにOKIの強みだと強調しました。「OKIは、目の前に与えられた条件で課題解決を可能にする技術力・応用力が非常に高い会社です」。
そして、社会課題の解決をエコシステムで実現する今の取り組みにおいても、「以前のようにOKIだけで端末やシステムを作るのではなく、社会にとってOKIが必要なパーツ、仕組みという位置付けで強みを発揮することができますから、これからも世の中から求められるメーカーとして残っていけると思っています」と述べました。
高橋は、スマート保安ソリューションが生まれた経緯に触れました。
お客様の要望は当初、アナログメーターの数値を見て手書きしている点検業務をデジタル化して効率化したいというものでした。これに対して「メーター確認作業のデジタル化だけで本当に点検業務が効率化するのだろうか」と疑問を持った高橋は、お客様と何度も対話し、業務現場も見学して現状をしっかり把握したことで、「メーターはあらゆる場所にあるので移動が一番非効率なのでは」と考え、リモートで設備点検ができる仕組みを企画・提案しました」。それが現在のソリューションに結びついています。
高橋はまた、「想像×創造、イマジネーションとクリエイションが非常に大事。イノベーションにおいても、お客様の意図を理解して課題解決策を想像し、それを具体的なソリューションとして創造していくというプロセスをいかに早く回して市場投入していくかが肝になると思っています」とも述べました。さらに「OKIは、イマジネーションしたアイデアを、一緒に創造=共創していただける顧客基盤があります。これが大きな強みだと感じています」と続けました。
2つめのテーマには「イノベーションを生み出すために乗り越えた壁」が掲げられました。中村氏の指名を受けて、武市、古川、山本が語りました。
「2、3年前の私は、『イノベーション活動は不確実なものを扱い、その可能性を検討しているのだから、決められたスケジュールの中で決められた成果を出すのは難しいのでは』といった一種の諦めを抱いていました」と武市は話しました。
しかし考え方を転換し、今は「会社や組織から言われた年間目標に対して、チームで成果をあげていくために、選択肢を常に多く持つような取り組みをしています」。本命で進めている方策に8割9割のパワーを使いながら、質のよさそうな別アイデアやメンバーがやりたいと思っている方策も準備し、何らかの事情で本命が思うように行かなくなった際に「こういう選択肢はどうだろう」「こういう進め方はどうだろう」と提案。こうしたやり方によって2020年度以降、「決められた期間内に『これが成果です』と言えるような活動を皆でやることができました」。

古川は、「AI-CoP」の立ち上げ・運営の苦労を取り上げました。独学では難しいAIスキル習得を、講義と実践からなる全6回・6カ月の集合研修型プログラムで進めようというコミュニティは、現在第5期を迎え、さまざまな部門・分野から約80名が参加しています。
最初の苦労は、部門の垣根を越えて参加者を集めることでしたが、「草の根活動ではあるものの上層部の協力、上の人が多く手を挙げてくれたことで一気に解決しました」。
もう1つは、いかに学びやすい環境を作るかでした。「現場に接しているエンジニアほど、身につけている知識とAIが結びつきにくい傾向にあります」。そこで、講師陣にAIの専門家を起用するのではなく、古川自身も含め元エンジニアでAIを学んだ人が講師になることで、参加者が親近感を持ちながらAIを勉強できるようにしました。
直近の課題は、やはりコロナ禍によって完全オンラインを余儀なくされ、以前のようなコミュニケーションがなかなか取れなくなったことです。ただし半面で、「さまざまな拠点の人と同時に活動できるのは大きなメリットだと感じています」と古川は述べました。
山本は、遠隔支援システムとスマートグラスを使った技術訓練の模様を、動画を使って説明しました。Yume ST TAKASAKIに設置されている新型プリンターを前にした受講者がスマートグラスを装着し、研修センターにいる講師からメンテナンス作業の実習を受けるシーンでした。スマートグラスに付属するカメラで受講者の目線で見た映像を研修センターと共有。講師がモニター画面上で製品の操作箇所や具体的な作業方法を指示すると、スマートグラスにAR画像が表示され、受講者に分かりやすくアドバイスができます。
山本は、「Teamsなどを使った訓練では限界があり、どうしようか悩んでいた折にこのシステムを知りました。これなら訓練受講者の移動の手間や時間を解消することもできます。スマートグラスと製品があればどこでも訓練を受けられるような環境を早く構築したいと思っています」と意気込みを語るとともに、長時間使用時の充電電池切れ、通信環境による訓練途中での中断の可能性を課題にあげ、「これらの解決にも取り組んでいきます」と語りました。
中村氏は、「皆さんが本気で、闘志を持ってイノベーションに取り組んでいることが伝わってきました」と述べた後、セッションの最後としてメンバーにもう一言ずつ求めました。
高橋は、スマート保守だけでなく、AIを使って踏切事故の減少に寄与するソリューションも考えていることを明かし、「今後もさまざまな想像×創造を継続して、社会課題を解決するイノベーションを起こしていきたい」と意欲を見せました。
吉原は、今回のイベント全体を通した感想として、他者が発表した技術やソリューションに新たな発見や気づきがあったと述べ、「営業活動への応用や新しいビジネスへのアイデアも浮かんできました」と、話しました。
山本も、グループ企業ながら普段は知ることのできない技術やソリューション、またイノベーション関連の情報を見聞きでき、大きなプラスになったと感想を述べました。さらに、「施工・保守現場の教育活動というのはなかなかスポットが当たらないので、その取り組みを広く発表することができて本当によかった」とも述べました。
武市は、OKIグループ内で年々イノベーション活動がやりやすくなっていることや、社外の方々と一緒に新しい取り組みを進めていこうという意欲や雰囲気の高まりを実感していると話したうえで、「一緒にイノベーションをやりたい方はぜひご連絡をください」と、視聴者に向けてメッセージを送りました。
古川は、「多様化・高速化するお客様の要望や課題にタイムリーに応えるにはAI技術が必須になりました」と強調し、それに対応するエンジニアたちがAI-CoPを通じてレベルアップしていることを改めてアピールしました。さらにOKIには製造現場のデータなどが資産として豊富にあり、その鑑定眼も有しているので、「これからもイノベーションの種が次々と生まれてくると思います」と話しました。
中村氏は、「皆さんの話を聞いて、OKIが圧倒的に顧客志向であることが改めて分かりました。圧倒的な顧客志向の先にイノベーションがある。とても素敵だなと思いました」と感想を述べ、セッションを締め括りました。
全員参加型イノベーションを業界・市場へと広げ、皆で社会課題解決へ
【Closing Talk】
三度目の登壇となった藤原執行役員は、「複雑な環境下で起こる社会課題は1社で解決はできません。OKIの取り組みを早く広く皆さんに伝えて一緒に社会課題解決に向かいたいという想いで、このイベントを催しました」と、改めて開催趣旨を説明。さらに、キーワードである“全員参加型イノベーション”について、「私は、OKIグループ内にとどまらず業界、市場の全体へと広げていきたい。IMSという共通言語を用いて、皆さんでぜひ大きなイノベーションを起こし、社会課題を解決していきたいと考えています」と、大きな夢を語りました。
そして最後に、さらに進展していくOKIのイノベーション活動を紹介する場として来年も「OKI Innovation World」を開催することをアナウンスし、3時間超にわたるイベントを終演しました。








