塾長コラム「Yume塾便り」第76回
パートナーとの関係を強化し、新たな事業を模索する「共創WS」

(左から、伊加田さん、奥谷さん、永見さん、井上さん、青木さん)
最新記事
OKIではイノベーション研修の一環として、お客様やパートナーとのディスカッションやフィールドワークなどを通じて新たな事業アイデアを検討する「共創WS(ワークショップ)」を開催しています。今回は、直近で開催された4件の共創WSの企画・運営に携わったメンバーと行った座談会をレポートします。
※文中の所属は、座談会を実施した2023年3月時点の組織で記載しています。
パートナーに応じて共創WSのスタイルも多種多様
千村お忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。
塾長コラム「Yume塾便り」73・74回でのイノベーション研修の座談会でも共創WSが話題に上りましたが、今回は、その共創WSにフォーカスしたいと思います。
イノベーション研修に携わる者として、共創WSはデザイン思考に基づく発想のトレーニングの場であると同時に、パートナーとのクリエイティブなディスカッションを通して、世の中の社会課題解決するビジネスモデルを構想し、事業化を目指す場として位置づけています。
本日は、その共創WSの企画やディスカッションのファシリテーターを努められている方々にお集まりいただき、それぞれの共創WSの活動状況を共有していただくと同時に、共創WSの現状や今後の展望や課題など、忌憚のないご意見を伺いたいと思っています。
それでは、それぞれの自己紹介を兼ねて、直近で手掛けた共創WSの概要をお聞かせください。
まずは、ビジネスコラボレーション推進本部の井上さんからお願いします。
井上コンポーネント&プラットフォーム事業本部(C&P事本)・ビジネスコラボレーション(BC)推進本部の井上です。よろしくお願いします。BC推進本部は、元々、統営本(統合営業本部)で間接販売を行っていた部署でしたが、事業部で間接販売でのイノベーションを推進するために、事業本部内で営業に従事しております。
私自身は現在、NEC、IBM、NTTデータなどの大手ベンダーやSIerに対して、主に金融流通市場向けの商材を提供する間接販売に携わっていました。そして、今回は間接販売でありますが、ダイレクトアプローチの一環として、お客様であるセブン銀行との共創WSを担当しました。
OKIとセブン銀行との関係は古く、ATMの入出金部分のモジュールを第一世代からパートナーであるメーカー(NEC)に供給し、現在は第4世代機になります。通常の間販であればOKIとメーカーだけの取引で完結するのですが、エンドのお客様であるセブン銀行がATMにどのような価値を求めているのかなどを知るためにも、ダイレクトにアプローチする方法を推進しており、2013年度から定期的に両社の情報交換の機会を設けるようになりました。
この共創WSは、他の方々のWSとはちょっと違い、個別案件での成果を求めるのではなく、セブン銀行との関係強化を目的としています。セブン銀行とは2013年以降、互いの経営層間でのトップリレーションを強化してきました。そして、この数年は、若手中心のWSを開催し、セブン銀行の若手社員の方々にOKIのことを知っていただくとこと同時に、OKIの社員にも自分たちが造り、売った商品が現場でどのように使われているのかなどを理解してもらうことにファーカスしています。直近で開催されたのは、2022年度で、セブン銀行とOKIの新入社員合わせて29名、6グループで実施をさせて頂きました。
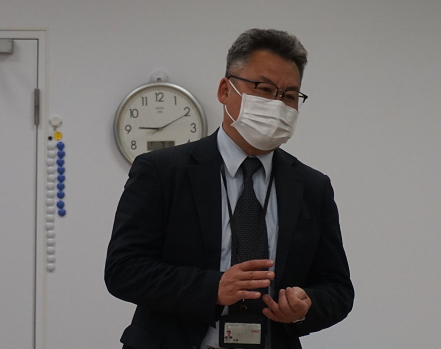
千村ありがとうございます。続いてIPCの青木さん、お願いします。
青木イノベーション推進センター(IPC)ビジネス推進部(BID)の青木です。
BIDは、OKIの中期経営計画2022に明示された物流、ヘルスケア、高度遠隔運用、リモートワーク教育、海洋といった5つのイノベーション領域で、OKIの研究開発メンバーと一緒にお客様と共創し、新規事業を具現化するセクションです。
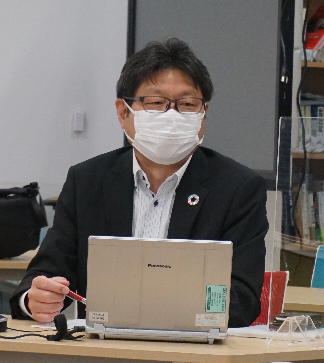
今回、私が携わったのは凸版印刷との共創WSです。凸版印刷5名、OKIから5名の計10名を2グループに分けて行った3日間のコースでした。
凸版印刷は2025年開催の大阪・関西万博協賛企業ですので、今回の共創WSでは万博開催に向けて、カーボンニュートラルの実現に貢献するビジネスをテーマとしました。
凸版印刷とはかなり以前からお付き合いがありました。私自身が凸版印刷とお付き合いを始めたのは2021年です。それ以降、OKIの高度遠隔運用のAIエッジロボットと凸版印刷の多言語ソリューションを組み合わせたサービスの実現に向けて情報交換を重ねています。その中で、もっと両社の交流の幅を広げたいと思い、千村塾長に相談し、今回の開催となりました。
千村補足しますと、10名を2グループに分けて、初日にデザイン思考に基づく課題の設定し、それに基づき2回目までにビジネスモデルを考え、3回目に発表というWSでしたね。後ほど詳しくお聞きしますが、テーマはカーボンニュートラルであったにもかかわらず、2グループとも予想外の発表となったのが面白かったですね。
では、次はIPCの奥谷さん、お願いします。
奥谷IPCのAI技術研究開発部(AID)の奥谷です。
私が共創しているパートナーは、日本データ取引所(Jdex)という、2016年に設立した社員数20名ほどのベンチャー企業です。小さな会社ながら企業のデータ活用に関するコンサルティングや、データ流通プラットフォームの構築・運用などを手掛けるデータ活用のプロフェッショナル集団です。私が研究しているAIはデータがあってこその技術。そこで、Jdexのデータ活用に関する知見やノウハウとOKIのAI技術を融合すればシナジーを生み出し、社会課題を解決する斬新なビジネスの創出が望めると確信し、共創をスタートさせました。具体的には、2021年度から私ともう一人のAIDのメンバーがJdexに出向し、データコンサルティングをサポートしていましたが、今回は、OKIのインフラ監視・防災分野におけるセンシングや通信というデータをJdexのデータ流通プラットフォームを介して、他者と共有することで、新たな価値の創出を目指してWSを開催していただきました。
伊加田AIDでチームマネージャーをやっている伊加田です。奥谷さんの上司になります。奥谷さんの話を補足させていただきます。彼は「データ活用ゴールモデリング」という独自のAI・データ分析手法の発案者ですが、OKI社内ではあまり使うシーンが無かったところ、その技術がJdexの森田社長の目に留まり、50%出向の人材交流という形でスタートした共創です。
千村そうですね。OKIとしては非常に珍しい共創スタイルですね。
Jdexとの共創WSは、初日に解決する社会課題のテーマを設定し、2回目までに現場インタビューの結果に基づくアイデアストリーを作成し、3回目にビジネスモデルを構築、その後プレゼンテーションという、計4日間のかなり具体的で実践的な共創WSでした。詳しくは、また後ほどお聞きします。

では、続いて営業の永見さん、お願いします。
永見統合営業本部 第二営業本部 第三部 第三チームの永見です。私たちのチームはJR東日本をはじめ関東地域の鉄道事業者をお客様としています。今回、共創WSを行ったのはJR東日本の子会社で、駅の券売機や改札機、ホームドアなどの開発・製造・メンテナンスを手掛けるJR東日本メカトロニクス(JREM)です。
OKIは以前からJREMが提供するSuicaのサーバーシステムを手掛け、2021年度の上期には大きな更改が完了しました。通常であれば、これで取引は終わりです。しかし、JREMのご担当者からは、システム更改が終わった後も引き続きJREMとOKIで新しいビジネスを考えていけないかとお声がけいただき、両社の保有技術と知見を持ち寄りながら、現場レベルでの協議は続けていました。そういう中で、OKIにはイノベーション研修の一環としてパートナー企業との共創WSというプログラムがあることを知り、千村さんに相談させていただき、実現しました。
WSのテーマは「新しい駅の価値で社会の大丈夫をつくる」で、駅周辺で起きている「大丈夫でない」問題を抽出し、SDGs的な解決策を探るため、まずはデザイン思考に基づく駅構内、駅周辺の現場観察からスタートしました。JREM3名、OKI3名の参加者を2チームに分け、期間は昨年(2021年)11月~今年1月までの3Daysで、現在は発表された2つのアイデアの事業化の可能性を検討しているところです。
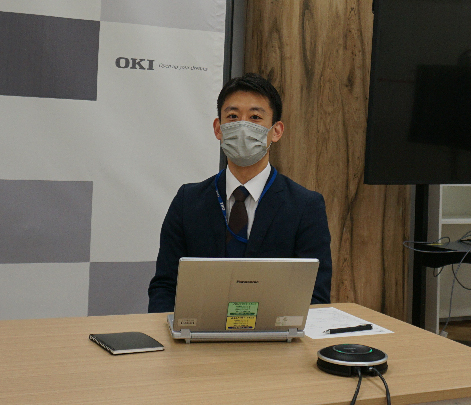
トップ、ミドル、若手の交流で、両社の関係を強化(セブン銀行との共創WS)
千村はい、ありがとうございます。
では、ここからは、それぞれの共創WSのテーマについて深堀りしていきたいと思います。まずは、自己紹介の順番通り、セブン銀行とのWSの井上さんからお願いしますが、それぞれの案件について質問や意見などがありましたら、他の方も適宜ご発言ください。
井上先ほども述べましたが、今回のセブン銀行とのWSは若手を中心した両社の関係強化を図ることが目的でした。直接的な共創成果ではないのですが、昨年(2022年)末に開催された第38回OKIトップセミナーに、セブン銀行の松橋社長にご登壇いただけるなど、一定の成果はあったと評価しています。
WSでディスカッションされたのは「お金の使い方」という漠然としたテーマだったためか、事業化と直結しないようなユニークなアイデアが続出していましたね。興味深かったのは、料理教室に通う20代女子の心理だとか、メタバースの世界でのバーチャル調理、そして意識高い系では、実際に納税している自分の住民税額から最も得するふるさと納税額を算定する仕組みなどがありました。
千村冒頭の井上さんのご発言で、セブン銀行とは2013年からトップリレーションを強化してきたということですが、やはりトップ同士の協議と、今回のような若手中心の協議ではテーマや内容、雰囲気を含め、かなり違いましたか?
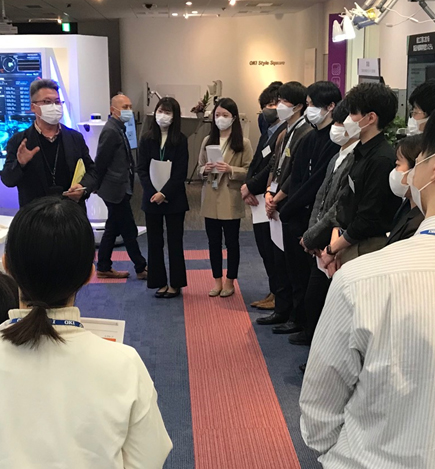
井上やはり、トップ間では、当社提供商材に限定されず、かなりシビアな経営課題が俎上に上がっていますね。一方、ミドル層では、リアルな協議が主になります。また、セブン銀行はオープンイノベーションに積極的な企業で、スタートアップ企業を中心にATMを活用したサービスに関するパートナーを公募した際、OKIはメーカーとして唯一、提案パートナー10社に選ばれました。その場ではATMを使った民泊の予約や電子キーの発行から、多言語対応のセブンATMの海外展開など、さまざまな提案を行いました。そういう実績もあるため、OKIは単なるサプライヤーではなく、多角的な提案をするパートナーであると評価していただいていると思います。
まあ、基本的なことですが、トップ、ミドル、若手のどの階層においても、パートナーと本音でトークできる関係を構築することが共創の第一歩だと思い、セブン銀行との関係を発展させる活動を継続していくつもりです。
千村イノベーション研修に携わる者としても、パートナーと互いに胸襟を開いてトークできるような共創WSのプログラムの改善・向上に努めたいと思います。
予想外のアイデアが生まれた凸版印刷との共創WS
千村では、凸版印刷とのWSの詳細について、青木さんに説明をお願いします。
青木冒頭に説明しました2グループから、全く違うアイデアでの発表がありました。
1つは、凸版印刷のメタバースとOKIの行動変容ソリューションという、現在、両社が注力している技術を融合した「メタバース空間と連動する環境貢献活動促進プラットフォーム」というアイデアです。具体的には、階段利用、資源回収、自家用車以外の利用などユーザーが行った環境貢献ポイントに応じて、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」を成長させて、バーチャル万博会場でゲームやイベントに参加するというプラットフォームの提案です。
2つ目は、かなりユニークなアイデアですが、近年、農村・山村で問題となっている獣害問題の解決と地域振興を推進する「ジビエ肉の流通プラットフォーム」です。これは罠の捕獲状況をリモートで監視する凸版印刷の「リモワーナ®」というソリューションと、OKIが実践している「バーチャル・ワンファクトリー」を応用した「バーチャル・ワン食肉加工所」というコンセプトを組み合わせることで、害獣の捕獲から食肉加工、そしてジビエ肉の需要が高い市場への流通をスムーズにする仕組みです。
前者のメタバースに関しては、OKIとしてあまり携わったことがない領域だったので、当初、OKI社員の中に戸惑いもあったようですが、ディスカッションを進めるうちに次第に理解が深まり、いい経験になったと思います。
一方、後者の関しては、ジビエ肉は低カロリー・高タンパク食であるため流通のターゲットをトレーニングジムでワークアウトしている層に設定したため、当初はジムや筋トレなどの話しで盛り上がり過ぎて(笑)…。一時はどういう方向に進むのか心配していたところもあるのですが、最終的にはうまくまとめ上げることができました。
私が今回のWSを通じて、一番感じたのはアイデアの実現性ということです。いくら優れたビジネスアイデアでも1、2社の共創では実現は難しいのですが、凸版印刷の共創実績のあるゼネコン、食品会社、外食チェーン、マスコミ、エンタメ、住宅メーカーなどといった大手パートナー企業のリストを見た時、多くのパートナーの力を集約できれば、何でもできちゃうような気になり、これこそ共創の醍醐味だろうと思うようになりました。

伊加田井上さん、青木さんの話しを聞いていて、共創WSは、これまでのOKIでは考えられないような突拍子もないアイデアが出てくるところが面白いと思います。でも、ちょっとネガティブなことを言いますが、そのようなアイデアに対して「Why OKI?」つまり、OKIがその事業をする必然性を問われると、気持ちが萎えてしまいますよね。
千村共創WSのプログラムにデザイン思考を採用している理由は、冒頭から「Why OKI?」「Why パートナー?」が議論されることを抑えるためでもあるのです。どちらかと言えば、OKIが「Why OKI?」を意識するのではなく、パートナーからOKIの強みなどを指摘していただけるようにするのがベストだと思います。たとえば、誰かが突拍子もないアイデアを考えても、OKI社内であれば「それは無理だわ」で終わってしまいますが、パートナー側から「OKIだったらやれるでしょう?」と問われれば、話しは終わらず、先に進展しますよね。だから、最終的には「Why OKI?」はとても大事ですが、議論の始めには、あまり意識しないことが大切だと思います。
伊加田そこで、井上さんと青木さんに、2点ほどお伺いします。
私が関わっているJdexとの共創WSでも、突拍子もないアイデアが出てくることもあるのですが、その場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
それと、共創WSの中で、パートナーに「Why OKI?」を言ってもらうためには、どうしたらいいのでしょうか?
井上私たちC&P事本としての現在の課題は、プリンターやATMをベースとした現業の拡大と、海外ビジネスです。セブン銀行との関係においても、コンビニATMの海外展開の必然性について両社とも共通認識を持ち、ミドル層から上の間で今後の現実的な方向性を検討していきたいと考えております。また、ここ数年活発化している若手社員の共創WSについては、両社のトップ間で「どんなアイデアが出てきても否定するのは止めよう」という認識を共有しています。また、今は無理でも、将来的な可能性などを考えて、1度のWSで終了するのではなく、同じメンバーで飲み会でもいいので、定期的なコミュニケーションの場を設けて、関係を継続させたいと思っています。そういう中長期的なスパンでのパートナーとの関係強化を図っていけば、お互いの強みや弱みも理解した上で、新しい価値が創造できるのではないでしょうか。
青木伊加田さんからの質問の明確な回答になっていないかもしれませんが、私は「Why OKI?」から議論をスタートさせた場合、自分たちがやれる範囲でしか考えないので「Why OKI?」は後付けでいいと思っています。実際の社会課題やお客様が直面している困りごとから議論を深めて、そこに使えるOKIの技術を当てはめるのがいいのかなと思います。もし、無ければズルズルやらずに、塩漬け(一時凍結)ですね。
それと、パートナーから「Why OKI?」を言ってもらうためには、長い時間をかけてパートナーとの信頼関係を築き上げていくことですね。そのため、私は凸版印刷に限らず、多くのお客様やパートナーとマメに情報交換するなど、日ごろから関係の強化と維持に努めているつもりです。
千村共創WSの場合、アイデアが出てくる前のモヤモヤした時間も大事かなと思います。最初は余計な口出しをせずに自由にやらせておいて「でも、最終日には発表会があるからね」とさり気なく締める。これがファシリテーターのテクニックの1つだと思います。
罠猟の現場から生まれた獣害対策ビジネス(Jdexとの共創WS)
千村次に、Jdexとの共創WSの詳細について、奥谷さんにお願いします。
奥谷皆さん、アドバイスありがとうございます。参考になりました。
Jdexとの共創WSでは、自然災害による自治体や企業の悩み事を解決する「防災」、原発立地自治体での災害時の被害を軽減する「原発」、獣害被害に悩む自治体の獣害対策を支援する「獣害」の3つのワーキンググループで、それぞれのソリューションを検討しています。
先ほど、青木さんから「共創の醍醐味」という言葉がありましたが、それを最も感じたテーマが3つ目の獣害対策です。このテーマが発想された背景が非常に面白いからです。Jdexは完全リモートワークが可能な会社で、鳥取県在住の社員で副業に罠猟をされている方がいます。近隣の里山などに仕掛けた罠にシカやイノシシなどが掛かったら回収して、役場に預けて対価をいただくという仕事です。この方をOKIのショールームに案内した際、省電力センサーに興味を持たれ、これを活用した獣害対策のビジネス化を構想しました。これはまさに現場の発想で、共創でしか生まれないアイデアだと思います。
それで、現在、考えている仕組みとしては、まず、獣害対策には個体管理が必要なので、監視対象地域の要所要所に省電力センサーを設置し、得られたサンプルデータから統計学的に全域の総数を把握する「獣害対策改善プラットフォーム」の構築を目指します。ここではOKIのセンサー技術やセンサーネットワーク技術と、Jdexのデータ解析・活用技術が活用されています。
また、デザイン思考ということで現場の困りごとを知る必要性を感じ、私自身も鳥取県の現地に赴き、罠の設置場所などを視察すると同時に、実際の獣害被害に悩まれている農家の方々にヒアリングなども行いました。現場で一番感じたのは、一番困っておられる農家や林業の方々は、個人事業のため資金力が無いということ。そこで、私たちとしては、獣害対策のプラットフォームを活用して、地方自治体が確保している獣害対策費の現状の費用対効果の評価し、効率的な対策を提案します。これは、効果の少ない対策費用の一部を個別の農家の獣害対策に充てること。つまり、お金をいただく所と、実際に価値提供する所を分けることで、農家の困りごとを解決するという仕組みです。また、このプラットフォームに、自治体、農家、猟師だけではなく、農水省、環境省などの国の機関、さらには民間の食肉流通業者やジビエ料理店、獣害コンサル、保険会社など、多くのステークホルダーを巻き込むことで、皆に少しずつでも利益や価値を還元できる仕組みづくりを目指しています。
千村このアイデアはまさに、猟師の現場から生まれたデザイン思考であり、私たちのように都会のオフィスの机の上からは絶対に生まれない発想ですよね。
また、シカやイノシシなどをすべて害獣として処分するのではなく、頭数を適正管理し、地域住民との共生を図ることも大切だと思いました。
獣害対策は、青木さんの凸版印刷との共創WSにもありましたが、そことも連携し、さらにはステークホルダーを拡大することによって、たとえばジビエ肉の地産地消のバリューチェーンが構築できれば、ジビエ肉の輸入など必要が無くなるのでカーボンニュートラルにも貢献できますね。
井上現在の日本で、一番問題を抱えているのは第一次産業だと思うのですが、そこをターゲットにした場合は、資金調達の方法もセットで提案しないと難しいですよね。
また、私は自分の興味から猟銃免許を取得したばかりなので、多少、猟の現状は把握しているつもりですが、許認可や既得権、初期投資や経験など難しい問題もあり、それらをひとつずつクリアにすることやどの課題にフォーカスするかも検討することが必要ですね。
千村だからこそ、奥谷さんが言われたようにステークホルダーの輪を広げて、さまざまな技術や知見、ノウハウを共有することで、さまざまな障壁を乗り越えて、うまくビジネスを軌道に乗せていくことができるのかなと思います。これをOKI単独でやろうとすると、とてもモチベーションの継続が難しくなりますよね。
青木最近、私たちが手掛けているヘルスケアや体育ICTなどといった領域では、困っている人、つまり価値を提供する人と、実際にお金を支払う人が異なるケースが増えてきています。この両者をどうやってWin-Winの関係に結びつけようかと常々考えているのですが、伊加田さんの話しを聞いていて、それをつないでくれるのがデータで、そのデータの対価をステークホルダーの間で回す仕組みがあれば、皆がハッピーになれると再認識させていただきました。
千村データはそのままでは価値になりにくいのだけれど、データを持つ人と必要とする人を結び付けてあげると、それが新たな商品やサービスを生み出して、お金が動き出すわけですね。
奥谷私がAIDで研究している「データ活用ゴールモデリング」は、まさしくデータ流通の最適化を目指すものです。
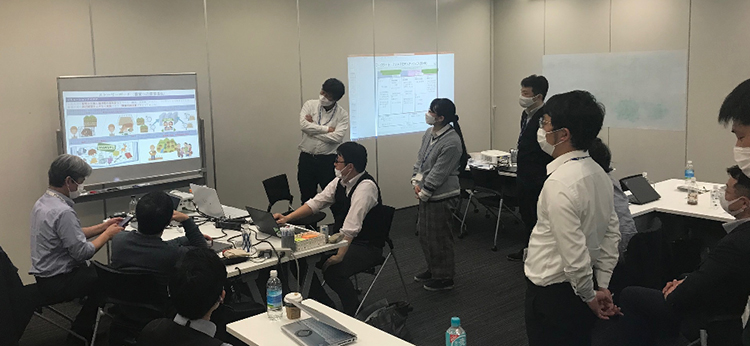
家族の円滑なコミュニケーション環境を提供(JREMとの共創WS)
千村では、JREMとの共創WSの成果について、永見さんにお願いします。
永見JREMとの共創WSでは、2つのグループがそれぞれのアイデアを考え、最終的には、仮想のプレスリリースを発表するスタイルとしました。
まずは、1つ目のテーマ「まもレールお迎えシステム」からご説明します。「まもレール」とは学校や塾帰りのお子さんが改札を通過した際、保護者の方に通知するJREMのサービスです。しかし、これが普及すると、ある特定の時間帯に車などでのお迎えが集中し、駅のロータリーや周辺地区で渋滞や混雑が発生する懸念があります。そこで、WSの初日に実際に駅周辺の視察を実施した結果、駅周辺にサービス利用者専用の駐車スペースや待機スペースを設け、スムーズなお迎えをサポートする仕組みを考えました。ここで、課題となるのが専用スペースの監視であり、そこにOKIのリアルタイムAIエッジ処理による画像認識や車番認識技術などを活用し、不正利用者に注意喚起を促します。そして、これらにより、駅周辺の混雑、渋滞を解消し、地域の暮らしやすい環境を提供します。また、先ほどから話題になっている「どこからお金をもらうか?」ですが、サービス利用者の専用アプリの使用料で賄っていくという仕組みです。
そして、もう1つのテーマですが、奇しくも同じ「まもレール」をベースとした「きょうなんじ?」というサービスです。これは、帰宅時間の連絡など些細なコミュニケーション不足が原因ですれ違う夫婦やカップルに対して、ワンタッチでのコミュニケーションを促すことで、円満な家庭サポートする仕組みです。活用するのはJREMの「まもレール」とOKIが得意とする行動変容技術です。連絡には導入企業の業務用PCを使うというところがミソで、ユーザーはPC画面にポップアップされたメッセージに対して、わざわざ返信メールなどを送ることなく、アイコンなどを使ってワンクリックで帰宅予定時間や残業や飲み会の予定などもメッセージします。そして、本人が最寄り駅の改札を通過したタイミングで、帰宅を待つ家族へ連絡が届くという仕組みです。このサービスは個人ではなく事業者レベルでの契約とし、導入企業にとっては、社員のワークライフバランスの向上とともに残業費の抑制にも貢献します。OKIとしては、ここに行動変容技術を活用することで、ユーザー個人の行動パターンを分析し、どのタイミングで、どのようなメッセージを出してあげると、確実に返信できるのかなどを工夫し、メッセージを進化させることができます。
共創WSを終えた感想としては、まず、現場視察を行いデザイン思考でアイデアを練り上げることができたこと。そして、これまではOKIからアイデアを提案し、JREMに検討してもらうという関係だったのですが、両社で共通の問題意識を持ち、同じ土俵で悩むなど今までと違うコミュニケーションが取れたことは、とても有意義であったと思います。
千村私個人としては、エキナカの商店や駅前のスーパーなどと連携して、帰宅時の買い物を促すなど複雑な仕組みになるかと思ったのですが、発表されたのはJREMとOKIの得意領域を集約したシンプルでわかりやすい仕組みでした。
両案とも「まもレール」を活用したのは、JREMの意向があったのですか?
永見いや。完全にフリーハンドで議論を始め、結果的に、OKIの方から「Why JREM」を投げかけた形です。
井上子供を対象としたお迎えのシステムは面白いと思うのですが、後者の夫婦、パートナーなど家族を対象とした方は、私のように道草が多い者にとっては、ちょっと抵抗があるかな…(笑)。
永見これは、決して飲み会などを抑制するのではなく、井上さんのような連絡無精の人でも簡単に連絡できる仕組みなのです。
井上さんのような指摘も考えて、アンケートを取ってみたのですが、家人が飲みに行くことよりも、何も連絡が無い方が家族にとってストレスになる傾向です。つまり、何も連絡も無く帰宅が遅くなるのと、何らかの連絡がある場合では、待っている家族の心持も違ってくるはずなのです。
井上わかりました。永見さんのご指摘を受けて、日頃の行いを反省しようと思います(笑)。

WSの成果をベースに、事業化へと昇華させたい
千村はい。議論が白熱してきたようですが(笑)…、最後に、今回の共創WSの結果を踏まえて今後、どのように取り組んでいくのか? また、今後、共創を検討している人たちへのアドバイスやメッセージがありましたらお聞かせください。
井上私は、セブン銀行案件以外にも自身が担当している複数のパートナー様との共創推進を担うべく、直近ではIBMと共創検討という形でディスカッションを始めています。今後も共創活動の幅を広げていきたいと思います。また、共創活動を始める人へのアドバイスですが、今日の議論の中で何度も出てきた通り、新たなサービスを構想する際は「Why OKI?」にとらわれずに、現状の社会課題にフォーカスしたアプローチが大切だと思います。もちろん、解決の方法論としてOKIの技術を取り込むのは必要です。
青木凸版印刷との共創WSは発表会を終えたのですが、せっかく両社のメンバー間での信頼関係が醸成でき、具体的なアイデアも生まれたので、活動を継続できるような場を作ってあげたいと思います。また、ジビエ肉の案件は、奥谷さんのJdexとの共創案件と類似しているので、どこかのタイミングでディスカッションに参加させていただき、共創の幅を広げていきたいと思います。
それと、アドバイスですが、やはり、共創で新サービスを検討する際は「こんなサービスあったら便利だよね。世の中の役に立つよね」といったような生活者、ユーザー目線で議論を進めることが大事だと思います。
千村先日、セブン銀行との発表会の場で、先方の上司の方が「それが商品化されたら、自分は率先して買うのか?」「いくらまでだったら買うのか?」など、質問攻めされていましたが、そういう感覚が必要ですね。
奥谷今回の共創WSに関しては、Jdex側が事業化に前向きです。しかし、OKI、Jdexとも狩猟や獣害対策の知見が乏しいので、現在、獣害モニタリングの会社にアポを取って協議を進めるなどして、事業化を目指そうと思います。
また、アドバイスは、共創WSにアサインされると時間も取られて面倒くさいと思われる方もいるとは思うのですが、面倒くさいと思うのではなく、WSを利用してやろうというマインドを持って参加すれば得るものは大きいと思います。実際、Jdexのようなベンチャー企業では研修やWSの機会も少なかったので、今回の経験は非常に貴重だったと、メンバーからも好評を得ています。
永見発表会を終えたJREMとの共創WSですが、近々、またメンバーを集めて、反省会を兼ねて、今後の展望を議論する予定です。
OKIは昔から多くの鉄道事業者をお客様としています。しかし、鉄道業界は長い歴史を持っておりOKIと同様に古い体質を残している部分があるため、共創やイノベーションの取り組み方に悩みを持っていると思います。そういう問題意識を共有しつつ、これまでのOKIと違う側面をアピールし、共創の横展開を図っていきたいと思います。
アドバイスについては、もう出尽くした感があるのですが、共創WSは百発百中で事業化を目指すものではなく、事業化までのプロセスを学ぶ場であり、パートナーとの関係性を構築する場でもあるので、突拍子もないアイデアを出してやろうというくらいの気楽な心構えで参加されるといいと思います。
千村共創WSのプログラムはイノベーションマネジメントシステム(IMS)の規格に準拠してデザインされています。IMSだとかISO規格で「機会の特定」なんてフレーズが出てくると、とても難しく思われがちですが、試行錯誤やコミュニケーションを重ねながら進めていく、当たり前のプロセスです。決して簡単ではないけど、やってみれば意外にできてしまうという経験を得る場でもあるのです。
永見それと、JREMとの共創WSでよかったと思ったのは、JREMの部長が積極的にコミットしてくれたことですね。上司、部下という立場、ジェネレーションの枠を超えて柔軟な立ち位置からアドバイスをしたり、議論をしたりする姿勢に感激しましたね。
千村セブン銀行に限らず、今回の共創WSに関しては、すべて部長クラスの上司の方が積極的にコミットしていただきました。特にJdexに関しては社長の森田さんが企画段階から積極的に参加されていました。これからの共創WSは、若手だけではなく、ミドル層、管理職も交えたメンバー構成があってもいいかなと思っています。OKIの藤原執行役員も、共創WSの発表会を楽しみにしていて、毎回出席して、意見、感想をメッセージしています。
この座談会の冒頭でも述べましたが、共創WSは半分が教育・研修であり、半分が新事業構想という実務的な場でもあります。今後も、その双方の機能を強化・発展させていくつもりなので、皆さんもご協力ください。
今日はどうもありがとうございました。
(2023年4月28日 イノベーション事業開発センター)





