塾長コラム「Yume塾便り」第74回
~実践モードに突入したイノベーション研修の課題と未来~(後編)

(左上から:後藤、尾崎、左下から:岩本、三樹、千村塾長)
最新記事
前回に続き、5年目を迎えたOKIのIMS「Yume Pro」は、社内文化改革から事業化推進に向けて「実践モード」へと移行しつつあり、それを推進する活動の柱となるのがイノベーション研修です。今回は、イノベーション研修の企画・運営・講師などを務める4名のイノベーターに研修の現状や課題から今後の展望までインタビューします。
実践研修の一環として「共創ワークショップ(共創WS)」を積極的に展開
千村さて、今年度(2022年度)からイノベーション研修も実践シフトということで、実践研修の充実化を図っていますが、実践研修を行う際、苦労されていること、工夫されていることをお聞かせください。

三樹実践研修ともなると基礎研修とは異なり、本当のイノベーション、つまり事業化に直結する案件を扱うので、当然のことながら、使う手法も増えるなど一段とレベルが上がります。たとえば、具体的な事例から顧客課題を発見・分析し、その解決策についてプライオリティをつけて導き出すというプロセスを実感できるような研修を心掛けています。
千村実践研修にはⅠとⅡがありますが、その違いはどこにあるのでしょうか?
後藤実践研修ⅠはBMC(ビジネスモデルキャンバス)などのフレームワークの中で、仮設検証を繰り返してアイデアを組み立てていくというレベルです。一方、実践研修Ⅱでは、実際にお客様の現場に足を運びヒヤリングを行い、そこに先ほどの岩本さんの話しにあった起業家の守屋氏のアドバイスのもとで導いた解決策をお客様にフィードバックする、このサイクルを続けることで本格的な事業化にアプローチするプログラムです。
千村共創WSについてお聞きします。現在、OKIのYume Proの活動などの情報発信を通じて、お客様から実際の社会課題の解決のためにOKIと共創したいという要望がいくつも寄せられています。そこで、実際にお客様との共創を経験された感想やご意見をお聞かせください。まずは岩本さんからお願いします。
岩本OKIのイノベーション活動に多くの企業が興味を持っていただいた結果、お客様からOKIの研修プログラムを知りたいという声があり、これまではご要望に応じて共創WSという活動を続けていましたが、今年度からはその活動を能動的・計画的に取り組むようになりました。共創WSの一番のメリットは、お客様や生活者の皆様が持つ切実な課題に向き合い、一緒に解決策や事業化を検討する場のため、とにかく真剣なディスカッションが行われることです。ただ、この議論の場を実のあるものにするためには、お客様と計画段階からしっかり協議し、互いに事務局を立てるなど、全体のプログラムを設計することがポイントです。そして、WS当日はこれまでの研修で培ったノウハウや経験を活かしてファシリテートしていきます。
また、共創WSに参加した社員たちが解決策の導き方や議論の進め方など、気づきを得ることで、お互いの会社の人材育成にも大きく貢献していると思います。お客様からも高い評価を得て、毎年開催しているお客様も増えています。
尾崎共創WSの課題としては、全く異なる業種で、価値観も歴史も文化も違う企業同士が議論すると互いの最大公約数を求め、どうしても議論の幅が狭くなる傾向があることです。そのような時は、一旦、立場をシャッフルするとか、もっと議論の幅を広げていく方向に促すファシリテートを心掛けています。
千村お客様により課題もさまざまだと思いますが、共創WSを進める上でお客様とゴールイメージを共有することは大変な作業なのでしょうか?
尾崎やはり、お客様とベクトルを合わせるところが共創WSの大前提でもあり、難しいことでもあります。
千村これは三樹さんにお聞きしますが、共創WSにおいてお客様やパートナーの最大のメリットは何でしょうか?
三樹お客様にとってOKIは、技術者が多く、技術実績やノウハウも豊富で、特に官公庁関連の納入実績が多いというイメージを持たれ、そこに期待されているケースが多いと思います。一方、お客様はOKIとは全く異なる視点で物事を見ているケースが多く、共創WSを通じて化学反応のようなことが起きて、これまでにないアイデアが生れる可能性が高いということでしょうか。
尾崎それと、OKIは通信からATMやプリンターなどハードウェアにも強く、製造ラインも保有しているなど、カバーしている技術領域が広く、そのリソースの一部を共有できることがお客様にとってもメリットだと思います。
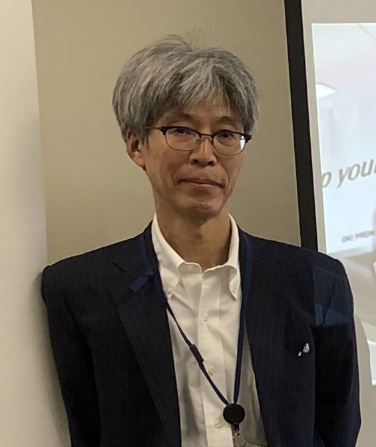
イノベーター育成のため、あえて教え過ぎないことも必要
千村OKIのイノベーション活動において、私がイノベーション塾の塾長として、対外的なプロモーション活動などをさせていただいていますが、実際にイノベーション活動の肝となる社員教育・研修を支えていただいている皆さんであり、常々感謝しています。
では、最後に今後の研修活動について、一言ずつお願いします。
尾崎コロナ禍もあり、この3年近く試行錯誤を重ねてきましたが、そこで得たコミュニケーションの工夫や方法を発展・深化させていきたいですね。それと、リアルとオンラインのハイブリット研修も実現したいと思います。
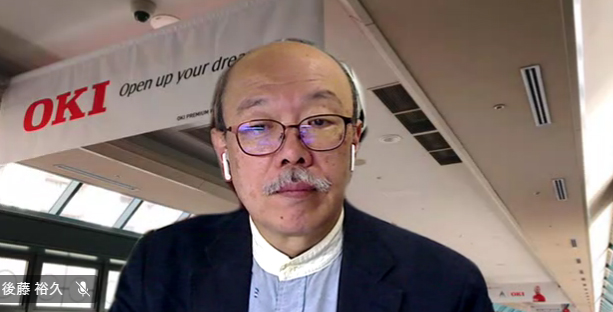
後藤基礎研修の受講者をもっと増やすと同時に、基礎から実践までのステップアップを加速させたいと思います。また、単に各レベルの受講者を増やすだけではなく、一人でも多くのイノベーターを育成していくことが目標です。
三樹これまでいろいろな試行錯誤を重ねてきましたが、研修活動はイノベーション活動と同様に明確な回答はありません。まだまだ工夫の余地があると思うので、これからも改善・改革を進めていきます。
岩本イノベーション研修の企画運営にもデザイン思考を活用しています。お客様である受講者の反応をつぶさに観察しながら理解度などを見て、バージョンアップを繰り返してきましたし、これからも続けたいと思います。また、OKIのイノベーション教育は、研修だけではありません。千村さんが塾長を務める「イノベーション塾」では、多くの実践の場を提供し、イノベーション活動の日常化に向けて社員の主体性や積極性、行動力などに期待し、あえて教え過ぎない教育を目指しています。
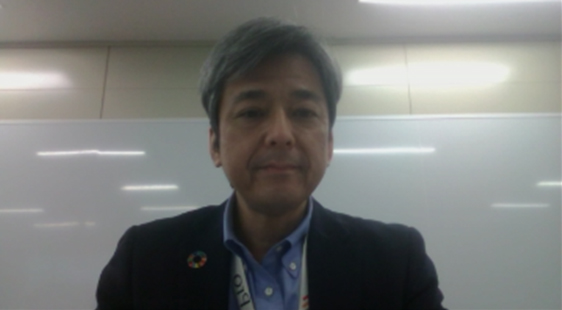
千村はい。このようにOKIの教育スタッフもIMSの手法に沿って、自らの課題を発見し、試行錯誤を重ねていくことがよく理解できました。塾長として、これからもこういうOKIの取り組みをお客様やパートナーに対してアピールしていこうと思います。
今日はどうもありがとうございました。
(2023年1月24日 イノベーション推進センター)







