塾長コラム「Yume塾便り」第73回
~実践モードに突入したイノベーション研修の課題と未来~(前編)

(左上から:尾崎、後藤(オンライン)、三樹(オンライン)、岩本、千村塾長)
最新記事
5年目を迎えたOKIのIMS「Yume Pro」は、社内文化改革から事業化推進に向けて「実践モード」へと移行しつつあり、それを推進する活動の柱となるのがイノベーション研修です。今回は、イノベーション研修の企画・運営・講師などを務める4名のイノベーターに研修の現状や課題から今後の展望までインタビューします。
IMS活動におけるイノベーション研修の位置づけ
千村お忙しいところ貴重な時間を割いていただき、ありがとうございます。
今日はOKIのイノベーション研修の企画運営、講師、ファシリテーターとして活躍されている方々をお迎えして、いろいろお聞きしたいと思います。まずは、それぞれの簡単なプロフィールと研修における役割をお聞かせください。
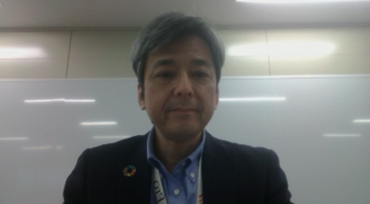
岩本IPC(イノベーション推進センター)企画室教育プロモーションチームの岩本です。私がイノベーション活動に関わるようになったのは、2017年に発足したIPCの前身であるイノベーション推進プロジェクトチームのメンバーとなった頃からですから、かれこれ5年目となります。最初の2年間はヘルスケアやまちづくりなどをテーマに新規事業開発を担当していましたが、2020年以降は社内文化改革の一環としてイノベーション研修に携わるようになりました。具体的には研修プログラムの設計をはじめ企画運営全般です。
尾崎OKIコンサルティングソリューションズ(OCS)の尾崎です。私はSEが長いのですが、お客様に言われたことだけやっていても事業が伸びないと気付き、現在はお客様に対してのDXコンサルティングにも携わっています。OKIのイノベーション研修においては、主にグループワークを行う際のファシリテーションを担当しています。
後藤同じくOCSの後藤です。もともとは研究開発職だったのですが、2003年以降は、それまでとは全く毛色が異なるインキュベーションマネージャーという外部資格を取得し、お客様の新規事業、新サービス、新商品などの開発支援を行っています。OKIのイノベーション研修においてはファシリテーター事務局に携わり、これまでの新規事業創出などの事例を踏まえ、研修に反映させています。
三樹OCSの三樹です。私は長年研究開発部門に在籍し、UI(ユーザーインタフェース)、UD(ユニバーサルデザイン)、UX(ユーザーエクスペリエンス)などユーザー目線での使いやすさを追求する設計法・評価法の研究を行っていました。その後、OCSに移籍し、UI/UD/UXに関連したコンサルティングに携わると同時に、イノベーション研修においてはファシリテーションを行っています。研修においては、ユーザー目線でのイノベーションを心掛けています。
千村皆さん、ありがとうございます。
では、ここから本題です。OKIのイノベーション研修の目的や体系についてお伺いします。これは岩本さんにお願いします。
岩本まずは、OKIのイノベーション活動の経緯について、簡単に触れたいと思います。
2017年にこれまで散発的であった改革の取り組みを日常的、持続的な活動とするため、経営層でイノベーション活動が検討され、2018年4月にOKIのIMS(イノベーション・マネジメントシステム)としてYume Proが発足しました。ここでは、1)経営層による文化浸透、2)社員の実践支援、3)イノベーション研修の3つの施策に、これら全体を支えるIMSを加えた活動が開始されました。その後、2020年4月に新規事業開発部門と研究開発部門を統合した現在のIPCが140名規模の組織として発足し、同年12月からはIMSを間接部門やOKIグループ全体へと展開する「全員参加型イノベーション」が始まりました。そして、2022年度からは、従来の社内文化改革から「実践モード」へとシフトチェンジし、新規事業などイノベーションによる新たな価値の創出を目指しています。
本日のテーマであるイノベーション研修については、大きく基礎研修、SDGs研修、実践研修に分類し、それぞれにプログラムが用意されています。この中で基礎研修に関しては2018年度からスタートし、2021年度からeラーニングを導入したことで、一気に裾野が広がり、2021年度末での修了者数は国内従業員の約70%に達しています。
千村実践モードへシフトしたことで、研修プログラムの変化はありますか?
岩本イノベーター、いわゆる「泳ぎ切れるスイマー」(※1)と伴走人材の育成強化を目指して、新規事業家・守屋実氏から直接指導が受けられる実践研修と他社と一緒に事業アイデアを検討する共創ワークショップを新設しました。ここでは現場潜入・観察・質問を徹底的に反復し、デザイン思考によるビジネス仮説を検証し、商品化・事業化につなげる実践力を磨きます。
※1 「泳ぎ切れるスイマー」とは、IMSを国際標準のプールと喩え、イノベーションの実践者をそのプールで競技を行い、結果を出せるスイマーに喩えています。
4年半の試行錯誤を重ねた結果、内外から高い評価を得る
千村イノベーション研修が始まり5年目を迎えましたが、この間、受講する社員の意識変化などは感じますか?
尾崎スタート当初は、上司に言われて参加したなど受け身の受講者が多かったのですが、この1年半余りで自ら志願して受講する方が増えたというのが実感です。それに伴い、以前は新規事業を担当する社員がメインでしたが、現在は管理部門、生産部門などあらゆる部門からの受講者が急増し、また、年齢層も若手からシニア層まで多様化しています。
千村研修がかなり浸透しているということですが、受講者の評価はどうでしょうか?
後藤基礎研修WSでは、年齢層もキャリアも異なる社員達がグループワークするわけですから、それぞれの立場からの多様な意見が飛び交い、それぞれ刺激になっているようです。先ほど受け身の受講者もいたということですが、そういう方でも最終的には「これまでのOKIにはない新しい取り組みで新鮮で楽しかった」と満足されているようです。
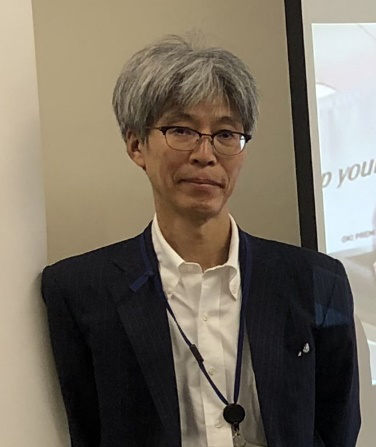
千村年齢や部門を超えたコミュニケーションが活性化したということですね?
後藤はい。あえてそれを意識しているところもあります。
千村では、社外の評価はどうでしょうか?
岩本日経グループの「日経Smart Workプロジェクト」というキャンペーンがあって、毎年、国内企業のイノベーション力を評価しています。昨年まではOKIは”S+”という評価でしたが、最近発表された記事では”S++”という国内30社に入るトップクラスの評価をいただいています。このような高い評価は、私たちのような研修コーディネーターはもちろん、研修受講者の方々のモチベーション向上にもつながっていると思います。
千村社外からも注目されているのは、塾長としても嬉しい限りです。
では、三樹さんに伺いますが、実際に研修を効果的、スムーズに行うために工夫されていることはありますか?

三樹まず、グループワークのキックオフミーティングですね。年齢層もキャリアも異なる初対面の方々に、いきなり「イノベーション」という話題を投じても敷居が高すぎますので、最初は自己紹介と研修における役割分担を相談することで、話し始めの敷居を下げています。その後については、「イノベーション」を議論しやすい、皆が知っている事例を選んで、議論がスムーズにいくようにスライドを工夫しています。その上で、議論が活発になるようなファシリテーションを心掛けています。
千村それでも、議論が停滞したり脱線し過ぎたりすることなどがあると思うのですが…?
三樹そういうケースでは、無理に軌道修正したり、結論に導いたりするのではなく、適宜、皆さんの気づきにつながるヒントやコメントを出すなどしています。イノベーションという答えの無い議論を行っているので、自ら考えてもらうようにしています。
オンライン研修の課題とメリット
千村コロナ禍もあって、2020年からオンライン研修となったわけですが、そのことでご苦労された点を聞かせてください。
岩本オンライン研修の立ち上げ当初は本当に大変でした。現在は皆さんリモートワークに慣れてきましたが、開始当初はスモールスタートで数名のグループワークからはじめ、2か月かけて徐々に拡大していきました。今もそうなのですが、毎回、研修を終えた際に反省点や改善点を洗い出し、プログラムとしてのブラッシュアップを図っています。
また、オンラインで受講者の顔が見えないため、微妙な反応などを把握し難いこともあるので、そのフォローに苦労しています。
後藤オンライン研修開始当初の課題は、受講者のネットワークや端末、マイク、スピーカーなどを含めた周辺デバイスなどからアプリを含めた環境がわからなかったことです。ノートPCではマイク、スピーカーが内蔵されていますが、デスクトップPCは外付けが必要であり、受講者の環境に応じたフォローが必要でした。また、当初は、リモートワークには不慣れな方が多く、当日、トラブルなどが発生した際のバックアップ体制の構築などにも苦心した覚えがあります。

千村逆に、オンラインにしてよかった点はありますか?
岩本研修の全てをデジタルデータで保存できるので、いつでも簡単にレビューができる点やオンラインツール上で共同編集機能を活用することによって資料作成の生産性を高めながら議論を深めることができています。
そして、何といっても、全国どこからでも手軽に受講できるようになったことが良かった点です。地方拠点やグループ会社の社員など、組織横断的なコミュニケーションが活性化することで多様性のあるアイデアが生れ、イノベーション活動が推進され、さらにはOKIグループとしての総合力の強化にも貢献できていると思います。
千村オンラインツール「Microsoft Teams®(※2)」の共同編集機能を全社レベルの研修で活用しているケースは少ないようで、私もマイクロソフトさんのセミナーで事例紹介しました。国内では先進的な事例として評価されています。
※2 Microsoft、Microsoft Teamsは、マイクロソフト社の登録商標です。
(2023年1月20日 イノベーション推進センター)







