Yumeトーク第56回
Yumeハブメンバーが組織を越えた全員参加型イノベーションを牽引する(前編)
SUMMARY
Yumeハブは、イノベーションに対する部門間の温度差をなくし、「全員参加型イノベーション」をOKIグループ全体でより一層加速するための施策です。各部署やグループ会社で選出されたYumeハブメンバーがその活動を牽引しています。
今回は、Yumeハブメンバーの5名と藤原CINO兼CTOが、活動の現状や問題点、今後の展望などについて、前編・後編の2回にわたりご紹介いたします。
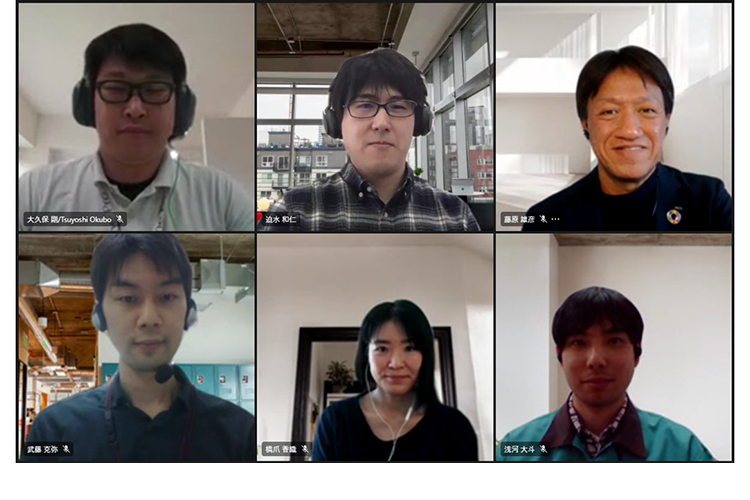
最新記事
Yumeハブ活動と全員参加型イノベーションを牽引する5名の戦士たち
藤原皆さん、こんにちは。私にとってYumeハブメンバーは、仲間、同志と思っています。特に今日は若手ばかりなので、ぶっちゃけトークでいきましょう。まずは、みなさんの自己紹介と、Yumeハブメンバーに選ばれた時の心境、もしくは立候補された方はその時の意気込みを聞かせてください。では、大久保さんからお願いします。
大久保コンポーネント&プラットフォーム事業本部(以下、C&P事本)開発本部の情報機器ファームウェア開発部所属です。旧OKIデータ出身で、入社18年目になります。入社以来一貫してプリンターのファームウェア開発に従事しています。職場のYumeハブ1期生の方に声を掛けていただき参加した活動をきっかけに、Yume Proの活動には興味を持っていましたが、上司からの推薦を受けYumeハブメンバーとなりました。当初は、大役が務まるか不安もありましたが、私にとってイノベーションは明るく楽しいイメージがあったので、ポジティブな気持ちで参加したことを覚えています。
藤原大久保さんはC&P事本内のイノベーション活動を紹介したYume Proフォーラム(2019年度より開始したイノベーションを加速するための社員向けセミナー)を仕切ってくれましたよね。その際、大久保さんは完全なイノベーターだと思いました。
では、イノベーション推進センター(以下、IPC)の迫水さんお願いします。
迫水所属はIPCネットワーク技術研究開発部です。専門は映像圧縮技術ですが、最近はIoTや高度遠隔運用など専門技術以外にも関わっています。Yumeハブメンバーには推薦で選ばれました。それまでYume ハブという活動自体は認識していたのですが、正直に言って、活動内容の詳細やその効果については深く知りませんでした。しかし、営業や生産現場、関連会社など、普段仕事であまり接する機会のない人たちと交流できるいい機会だと思い参加しました。
藤原IPCはまさにYume Proプロセスで業務推進しているので、今日はいろいろ聞きます。
次に統合営業本部(統営本)の武藤さんお願いします。
武藤第一営業部所属です。2014年に中途入社して以来、郵政や流通市場を担当し、最近では迫水さんと組んで郵便ポスト監視の実証実験をはじめ高度遠隔運用の活動に注力しています。Yumeハブには立候補しました。価値観や社会に対する視点などが異なるさまざまな部署の方々と話しをしていると新しい発想が生まれてくると思ったからです。
藤原それって、とても大事なことです。セクショナリズムの打破は、OKIとして大きな経営課題でもあります。でも、最近は若手・中堅社員を中心に他部門との交流を望む声が出てきたことに頼もしさを感じています。
では、OKIソフトウェア(以下、OSK)の橋爪さんお願いします。
橋爪OSK、DXビジネス推進本部所属です。先ほど藤原さんが若手ばかりと言われて、入社年を言うのは少し躊躇うのですが1998年入社です(笑)。当初はハードウェア開発を手掛けて、その後、OSKへ転籍しソフトウェア開発に携わっていたのですが、思うところがあり2012年に退社し、一人法人として起業。独立後は子供向けプログラミング教育や幼児教育向けアプリ開発のコンサルやデジタル人材の育成などの事業を手掛けていました。やがて、古巣のOKIがイノベーションに取り組み、異業種の企業といろいろおもしろいことをやっていると知り、起業経験を糧にOKIのイノベーションに貢献したいと想いが湧きあがり2021年に、OSKに中途入社として出戻ってきました。そういう経緯からYumeハブメンバーも自ら立候補しました。新入社員としてフレッシュな気持ちで参加しています。
藤原Yumeハブメンバーとして橋爪さんのことは知っていましたが、そんなユニークなキャリアを持っていることまで知りませんでした。キャリア豊富な人がフレッシュな気持ちになれるのは素晴らしいことで、私たちとしても心強いです。
では、静岡OKI(以下、SOKI)の浅河さんお願いします。
浅河SOKI技術部でOKIのルーツとも言える電話機などの設計・開発を担当しており、主に船舶電話機や非常用電話機などに携わっています。SOKIでは2年ほど前に社内にイノベーションを推進する組織が立ち上がり、私はその組織の下で部署内の推進員(ハブ)として活動していました。Yumeハブには特に立候補したわけではないのですが、推薦された時は、すんなりと前向きな気持ちで受けたことを覚えています。
藤原私もSOKIからよく相談を受けるのですが、組織改革にも積極的ですよね。今日はその辺も聞いてみたいと思います。
全員参加型イノベーションとは、技術者をお客様の現場に連れ回し共に行動すること
藤原5人の意気込みをお聞きして、ポジティブな方ばかりで安心しました。イノベーションはリアリストよりも、”あきらめきれない人”、の方が向いていると思います。
では、それぞれの職場でのYumeハブとしての活動内容を聞かせてください。先ほどと同じ順番でお願いします。
大久保C&P事本のグループとしても、数年後を目標にイノベーションが常態化した組織を目指しています。そのために克服しなければならない課題としては、イノベーションを新事業の創出だけと誤解するなど、全員参加型のイノベーションの定義が組織で共有されていないことや、イノベーションを興す工数が足りないなどがあります。そこで、現在、Yumeハブ事務局と連携してイノベーションの意識を浸透させるための教育ツールを作成しているところです。
藤原私たちOKIが志向するイノベーションは、新規事業の創出と既存事業の革新を進めること。つまり変革に挑戦した結果、お客様に新しい価値を提供することです。しかし、イノベーションイコール新規事業創出と思っている社員がまだまだ多いのも事実。社員の一人ひとりが「自分は社会の大丈夫をつくっていく仕事をしているのか?」を問い続けることが全員参加型イノベーションであり、そのためにOKIのIMSつまりYume Proを活用してもらいたいと思います。
また、OKIグループ全体で展開しているYume Proチャレンジのような取り組みを部門内でも行うと組織としての横のつながりができるので、工数問題の解決になると思います。
迫水私の所属はイノベーション推進センターなので、メンバーがイノベーションを興すべく取り組んでいるのはある程度当然なのかもしれませんが、イノベーションの質を高めるための課題は何かと言う観点で、組織内でヒヤリングをおこないました。その結果、課題のひとつとして、組織内でのコミュニケーションに問題があり、隣の組織で何をしているのかお互いのことを知らないことがイノベーションの質を低下させる原因になっているのではないかと思い、組織横断的なコミュニケーションを円滑に行える仕組みづくりを検討しているところです。具体的には、個々が日頃漠然と考えていることや、思い浮かんだ発想を自由に書き込みできるような仕組みや、人と人をマッチングするシステムを情構築できないかと考えています。
武藤統営本としてのYumeハブの活動は、情報発信とコミュニケーションの活性化に注力し、私は後者を担当しています。具体的な活動としては二つの試みがあります。そのひとつが、若手会と称して営業第三部の20代の若手を選抜し「10年後の郵便局を考える」というテーマで継続してディスカッションを行い、その結果を四半期ごとに報告してもらう活動。もうひとつは「同行営業」と称して、他チームの営業活動に同行することで新たな気づきを得て、イノベーションにつなげるという試みです。
また、反省点としては、若手会は自発的な活動ではなかったので、その後、会議体の枠を超えた活動に波及しなかったこと。今後の課題と認識しています。
藤原最近、営業本部長などと議論する機会があるのですが、私は常々「Yume Proの主役は営業だ」と主張しています。その理由は、IMSの初期段階、つまり仮説を立てる際にはお客様の現場の課題を発見することが重要で、お客様に一番接している営業がその役割を担っているからです。そのためにも、ビジネスモデルを可視化するツールである「BMC(ビジネスモデルキャンバス)」を活用し、関係者全員で情報共有して欲しいと思います。そして、営業やSEだけではなく、IPCの研究開発メンバーもお客様のもとに連れて行くことこそ全員参加型のイノベーションだと思います。
武藤それは私も感じているところで、私自身、迫水さんをはじめIPCのメンバーを現場に連れ回しているので、そういう姿勢を統営本の組織内にも示したいと思います。
橋爪私たちOSKのYumeハブは、SOKIとともにOKIのソリューションシステム事業本部(以下、SS事本)のグループとして活動しています。SS事本の現在の取り組みとしては、現場の管理職や一般社員が持つイノベーションに対する意識や部門間連携に関する課題についての詳細なアンケートを実施しています。
そして、私個人としては「OSKに新しい風を吹き込む」という意思で活動しています。その中で感じたOSKとして課題は、情報発信力が乏しい、イノベーションの意義が全体に浸透していないことなどがあります。また、OSKは若手からベテランまで、たとえばマイクロサービスアーキテクチャ、クラウドネイティブなどと言った新技術の取得に貪欲であるにも関わらず、それを社外だけではなくOKIグループ内にもアピールできていないことに気づき、Yume Proの発表会の席で、藤原さんをはじめIPCの方々に直談判し、OKIPEDIA(OKIの技術ポータルサイト:イントラ専用)の中にOSKのページを作っていただきました。
それと、以前、OKIのイノベーション・ダイアログに参加した際、OKIの鎌上社長の意図がダイレクトに伝わり、いい経験となったので、早速、OSK社内でも同じような機会が必要と思い、猪﨑社長の承認を得て定例のダイアログを開始しました。ダイアログ内ではファシリテートをし、猪﨑社長と社員の皆さんの対話を通してイノベーションについての想いを伝えようとしています。
藤原いや、かっこいいですね~。一度社外に出たというのは貴重な財産です。是非、経験をOKIグループ内に伝えてください。
では、同じSS事本グループとして活動されているSOKIの浅河さんお願いします。
浅河SS事本の取り組みとしては、橋爪さんが話された通りです。SOKIでは新商品創出と風土改革のための施策として、Yume Proチャレンジを模倣したSOKIチャレンジを開催しているのですが、私は参加者にアイデア出しやビジネスモデルキャンバス(BMC)の書き方などをアドバイスしたり、レクチャーしたりしています。また、昨年末にSOKIのYumeハブ1~3期生で協力して、若手社員を対象としたSOKI社長とのダイアログを開催しました。ちなみに、現在、SOKIチャレンジのアイデア登録数は50件を超え、内4件はYume Proチャレンジにエントリーさせていただきました。
藤原そういう若い人たちを中心とした努力が実を結び、今年度のYume Proチャレンジの登録数は254件を数え、前年度比プラス100件です。とても嬉しいことです。
後編ではYumeハブ活動を通して苦労した点やその課題・困難をどう乗り越えたか、今後の抱負を紹介していますので、ぜひご覧ください。







