Yume対談
「事業構想大学院大学×OKI<前編>
~新規事業創出のプロが見たOKIの全員参加型イノベーション~」
SUMMARY
今回は、新規事業を創出する人材の育成と研究を行う「事業構想大学院大学(東京・南青山)」 を訪れ、同校の田中里沙学長と、OKIの藤原執行役員CINO兼CTOが対談しました。
OKIのYume Proを活用した全員参加型イノベーション、地方創生や新規事業の創出、社会課題の解決にむけた共創の必要性をテーマに意見を交わします。前編となる今回は、OKIの全員参加型イノベーションについて、新規事業創出のプロフェッショナルである田中学長から講評、アドバイスをいただきました。
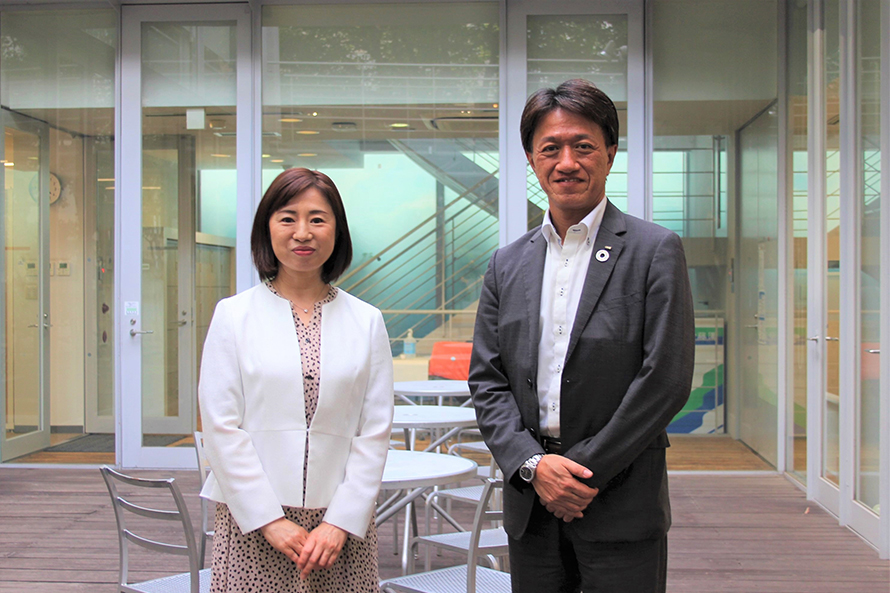
新規事業を構想し、持続可能な事業へ導く人材を育成
藤原本日は、お忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。
私たちOKIは、全社的なイノベーションを推進すると共に、社会課題解決に向けて多くのお客様やパートナーとの共創に取り組んでいます。このような取り組みは、事業構想大学院大学の理念である地域活性や新規事業創出のための人材教育と共通項が多いと思っています。そこで本日は、私たちOKIの取り組みに触れながら、田中学長にアドバイスなどをいただき、OKIだけではなく地域や企業を含めた日本社会全体のイノベーションなどについて、幅広く意見交換させていただきたいと思っております。
まずは、田中学長の簡単な自己紹介をお願いします。
田中私は広告・マーケティングの専門誌「宣伝会議」の編集長を長く務め、マーケティングコミュニケーションの専門家として政府や自治体などの委員会・審議会にも多数参加をしてきました。そして、2012年、事業構想大学院大学の開学と同時に教授に就任し、2016年から宣伝会議の取締役を兼任の上、三代目となる学長を務めています。
藤原さんはOKIでイノベーションに取り組まれていらっしゃいますが、技術畑のご出身ですか?
藤原はい、技術者です。入社直後から当時OKIの主力製品であった大手通信会社向け局用交換機のハードウェア設計を手掛けるなど、長く受注開発型の仕事に携わっていました。その後、30代で海外事業を経験し、2017年IoTアプリケーション推進部門の長を務めた当時から、社長直属のイノベーション推進プロジェクトチームに携わりました。田中学長が学長に就任されたのが2016年とのことですから、私はイノベーションの1年後輩ということになりますね(笑)。
次は、貴校の取り組みについてお聞かせください
田中 事業構想大学院大学は、不確実かつ激動する国際社会の中で、日本の企業、特に中小企業が新規事業を創出することでその閉塞感を破ることができるという意識とビジョンから生まれた社会人向けの専門職大学院です。新規事業を担うリーダーや承継者・起業家等経営者の育成を目指す本学では、文字通り事業構想、つまり新規事業のアイデアを構想し、それをサステナブルな事業へと発展させるプロセスを習得するカリキュラムと研究環境を整えています。具体的には、まず、既存の経営資源をベースに新規事業のアイデアや閃きの「発・着・想」を導き、知恵と情報を集めることで「構想案」を策定します。さらに、現場の声を聞き感触を得る「フィールド・リサーチ」を行い、構想実現のための「構想計画」を練り上げ、プレゼンテーションや提案などステークホルダーの共感を得るための「コミュニケーション」プロセスを実践する事業構想のメソッドを展開します。「教える」ことを超えて「気づきを与える」ことを重視しています。
藤原学生さんは、どういう方が多いのでしょうか?
田中院生の年齢層は幅広く、企業・組織の中で新規事業やイノベーションを担当する藤原さんのような方から、事業継承者、起業を目指す方、地域活性化を担う自治体関係者など、多様な院生が在籍し、それぞれが刺激し合いながら事業構想を研究しています。職業は会社員、公務員、医師、会計士、議員、元プロ選手など実に多彩です。開学から10年で修了生は466名にのぼり、新規事業や地域活性など、多彩なフィールドで活躍しています。

IMSを共通言語に、全員参加型イノベーションを展開
田中OKIさんは、2017年からイノベーションに取り組まれているとのことですが、何かきっかけがあったのですか?
藤原一番のきっかけは、経営陣の危機感ですね。
OKIは長年、通信をはじめ、金融、官公庁、交通、流通など社会インフラを担うシステムや製品を手掛けていました。しかし、21世紀に入り、局用交換機などの受注が激減し、その後の主力製品もペーパーレス化、キャッシュレス化などの影響を受け、需要拡大も見込めなくなりました。2015年頃には、当時の川崎会長や鎌上社長(現会長)らが「新規事業を起こさなければ会社の存続が危ぶまれる」という危機感を共有し、まずは新規事業を創出する仕組みづくりを模索し始めました。その後、2017年にOKIとしてのイノベーション・マネジメントシステム(IMS)、つまりイノベーションを興す仕組みづくりから着手し、翌2018年に「Yume Pro」という名称でOKIのIMSがスタートしました。その目的は、社会課題の解決に貢献する新規事業の創出とそれを実現するための社内文化改革です。
田中なるほど。未来社会への危機感からスタートしたという点は本学と共通ですね。
イノベーションと言うと、一部の精鋭たちがリードしていくイメージを持たれがちです。その中で「全員参加型イノベーション」というのは、とてもユニークです。
藤原私たちは、新規事業の創出だけではなく、既存事業の革新もイノベーションと定義しています。したがって、間接部門も含めた社員全員が取り組むことができるような仕組みを構築・推進しています。
田中IMSを共通言語として、それを拡大していくスタンスは素晴らしいと思います。
最近、IMSを導入する企業が増えている半面、途中で挫折しまうケースもあると聞いています。OKIさんは、ここまで順調にステップアップされているようですが、継続されるために工夫されていること、さらなる課題があれば具体的に教えていただけますか。
藤原当初、イノベーションに取り組む人間は周囲から色々と言われます。私も一部の者から嫌味を言われたり、妬まれたりして、孤独感に苛まれていた時期もありました。すみません、愚痴になってしまいましたね(笑)。
田中イノベーターって、最初は誰しも孤独です。社長から新規事業担当者として任命されても、費用や人材はありません。モチベーションが保てないと孤立していた方が、本学に入学したら同じような境遇の人が多くて勇気づけられたと言う院生も多いんです。
藤原そういった方々の気持ち、痛いほどわかります(笑)。

BMCの活用で活気づいた「Yume Proチャレンジ」
藤原実際にIMSを進めると、大きく3つの課題に集約されました。一つ目が『「新しいことをやれ!」と言われても、どう行動すればよいかわからない』、二つ目は『組織の縦割りが強く、協力してくれる人を集まられない』、そして『現業が忙しく、新しいことに取り組む時間がない』です。
田中どれも、組織として新しいことにチャレンジする際の「あるある」ですね。その課題の一つひとつの解決に取り組まれているわけですね?
藤原まず、行動の方法に関しては、外部の専門家からアドバイスをいただきつつ、全社員がイノベーションの考え方から実践までを学ぶ教育活動や、既存のQMS(ISO 9001)とIMS(ISO 56002)を連結させ、行動を起こす手順を示しました。
二つ目は、組織のタテ割りを解消するために、各部署から選任されたイノベーションの伝道師「Yumeハブ」の設置、ビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」の開催、OKIクループ内の保有技術をDB化した技術情報ポータルサイト「OKIPEDIA」の開設を行いました。
時間の問題に関しては、新しいことにチャレンジする者が周囲から理解・共感を得やすい環境づくりが必要でした。そのため、社内外に積極的に情報発信することでイノベーションの必要性を認知させること、そして、チャレンジに必要な時間確保を上長が容認するルールの徹底、さらには、目指すべき中長期のイノベーション戦略を全員が共有しました。
田中課題解決のため、多角的な活動や取り組みをされていますが、この中で最も成果を上げている活動はどれですか?
藤原やはり、「Yume Proチャレンジ」ですね。新規事業だけではなく既存事業の革新アイデアも対象としたコンテストで、大賞受賞案件には、仮説検証とプロモーション支援として1億円の予算が与えられます。
田中社員を対象にしたアイデアコンテストは、よく行われていますが、実現支援のための金額は1千万~2千万円というのが相場です。1億円という額にOKIさんの経営陣の本気度が伺えます。
藤原第1回の2018年度の応募件数は37件でしたが2021年度は254件と、4年間で約7倍も増えました。
田中そこまで急増した要因をどのように分析されていますか?
藤原まずはIMSの活動がOKI社内・グループ内に浸透し、認知されたことでしょう。
それとビジネスモデルキャンバス(BMC)の活用が進んだことだと思います。
OKIのIMS、特にYume Proチャレンジでは、新規事業のコンセプト構築のフレームワークとしてBMCを活用するため、全社員にBMCの研修を実施しています。つまり、お客様に対して何度もヒアリングを行うことで仮説を磨き、「誰に」「何を」「どうやって」を提供するかを明確にします。OKIの場合、長年の技術の蓄積があるため、保有するリソースを「どうやって」活用するかばかり考えてしまうため、「誰に」つまり、どういう困りごとを持つお客様に、どういった価値を提供するのかという視点を忘れがちです。
田中私たちも「事業構想は、始めに対象者=顧客あり」としています。持続可能なビジネスとは、どんな顧客に支えてもらうか、つまり、お金を出していただけるかで決まるわけですから、当然のことです。
藤原そして、IMSという共通言語を用いて、新たな事業や活動を継続することで、さまざまな社会課題を解決することを目指しています。ちなみに、現在、OKIの中期経営計画で掲げているキーメッセージは「社会の大丈夫をつくっていく。」です。
田中長くマーケティングコミュニケーションに関わってきた経験から言わせていただければ、そのキーメッセージはセンスが良くて素敵だと思います。普通は、社会の安心・安全など無難な表現にしがちですから。
藤原ありがとうございます。私もとても気に入っています。
少し熱が入りすぎて、ここまでは私ばかり喋ってしまいましたね。
後編では、私から田中学長に、実際に新規事業を創出するためのノウハウや、官民一体となったエコシステムの構築について、いろいろと聞いていきたいと思います。
<参加者プロフィール>
・田中 里沙
事業構想大学院大学 学長
マーケティングコミュニケーションを専門とし、雑誌「宣伝会議」編集長、編集室長を経て、宣伝会議取締役メディア・情報統括。内閣府、政府広報、総務省、財務省、国土交通省、農林水産省、環境省等の審議会委員、環境省「クールビズ」ネーミング委員、東京2020エンブレム委員、伊勢志摩サミットロゴマーク、G20ロゴマーク選定委員等を務める。2012年本学教授、2016年4月学長に就任、現在に至る。







