Yume塾便り「Yume塾便り」 第43回
OKIの本当の強みとは(その4)
~標準化戦略とビジネス推進をリードするキーマンの存在~
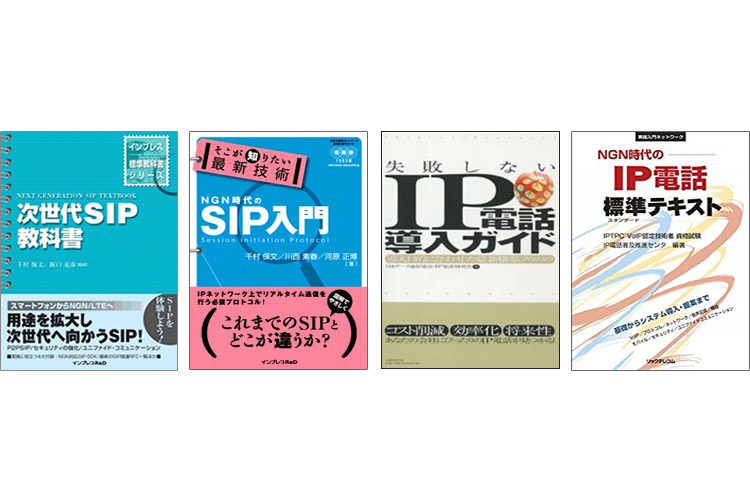
最新記事
前回は、IP電話市場が拡大する以前に事業関係者を支えた熱い思いについて語りました。今回は、自身の経験を踏まえて、ビジネスをリードするための標準化戦略と技術委員会をリードするOKIの専門家の存在についてご説明します。
IP電話の開発は、前回紹介した方々の先見の明が大きな成功要因ですが、加えて国際標準化活動の推進とビジネス推進を同時に行ったことも重要でした。電話サービスの提供価値は「どんな機器でもつながる」ことですので、標準化を進めていくことは価値実現にとって必須の取り組みとなります。そこで、世界中の企業が集まり、国際電気通信連合(ITU)などで共通規格を作成する標準化活動が行われています。OKIは、電話網の開発初期からこの活動に参加しています。VoIPの規格開発時には、まだ参加する日本人が少なかった時代から標準化会議に参加し、技術仕様の提案などにも貢献しました。
たとえば、通信事業者のIP電話サービスに加入すると電話機を接続するための箱が送られてきますが、この箱はゲートウェイと呼ばれています。このゲートウェイは、電話やファクシミリの通信をインターネット上に伝送するための変換装置です。このゲートウェイにファクシミリを伝送するための手順は、 IP-FAX(T.38)と呼ばれる規格です。この規格の策定にOKIは多大な貢献を果たしました。IP電話サービス開始当時はIP網でFAXは通らないと言われていましたが、多くのFAXベンダーと協力し、IP網でFAX通信ができるようになりました。これは今で言う共創活動であると考えます。
このような国際標準を日本で普及、浸透するために冒頭の写真にあるような書籍を執筆しました。この本を執筆した当時は、VoIPのシステムを開発する部門の責任者を行いながら、仕事の合間に執筆活動をしていました。その頃は、まだマイナーなサービスであったIP電話を早く普及させるには、OKI単独ではなく、業界全体で切磋琢磨して良いサービスを作らなければならないという思いが強くありました。
また、OKIには、私以外にも各分野でその業界の技術標準の策定や相互接続性確保のための活動をリードしている専門家がいます。たとえば、ITU-T(電気通信連合 電気通信標準化部門)のSG16(第16研究部会)(※1)で副議長をOKIのネットワークシステム事業部の山本秀樹部長が務めています。SG16は、マルチメディアアプリケーションの標準規格を策定しており、地デジや映像サービスで使用されている映像圧縮技術(MPEG-2、H.264、H.265など)、テレビ会議、映像サービス、およびデジタルサイネージなどの標準化を推進しています。また、通信機器間の相互接続性試験を実施しているHATS推進会議(高度通信システム相互接続推進会議、現在のHATSフォーラム)の高呂賢治(現:OKIコンサルティングソリューションズ)は1988年にこの団体が発足した直後より、長年にわたり活動をリードしています。
技術仕様を標準化してしまうと競争力が無くなると間違った認識をしている方もいますが、標準化は顧客の利便性を高めつつ、その規格策定をリードすることで自社の強みを活かすことも可能です。OKIでは、標準化の推進は事業や研究開発を担当している技術者が自ら行っており、ビジネスを考えながら、その中で標準化活動を行う文化があります。
このようにOKIでは、過去から現在までに綿々と伝わる技術の伝承とその技術を活かすための標準化活動などが強みの源泉になっています。
次回は、IP電話サービスの普及を支えた教育サービスについて紹介します。
-

ITU-T SG16副議長 山本秀樹 -

HATS推進会議で講演する高呂賢治
(2020年2月5日、OKIイノベーション塾 塾長 千村 保文)







