Yumeトーク 特別編
快適なテレワークに。雑踏や雑音環境下でもクリアな音声を収音する。~コンシューマー向け商品開発の課題と展望を探る~
SUMMARY
コロナ禍でWeb会議やテレワーク機会が増える中、周囲の会話、騒音、生活音などを気にせずに快適なコミュニケーションを実現する、エリア収音技術が注目されています。今回は、この技術の商品化を進めるイノベーション推進センターの技術者・藤枝大とソリューションシステム事業本部のSE・石黒高詩に、商品化・事業化の課題や展望についてインタビューします。
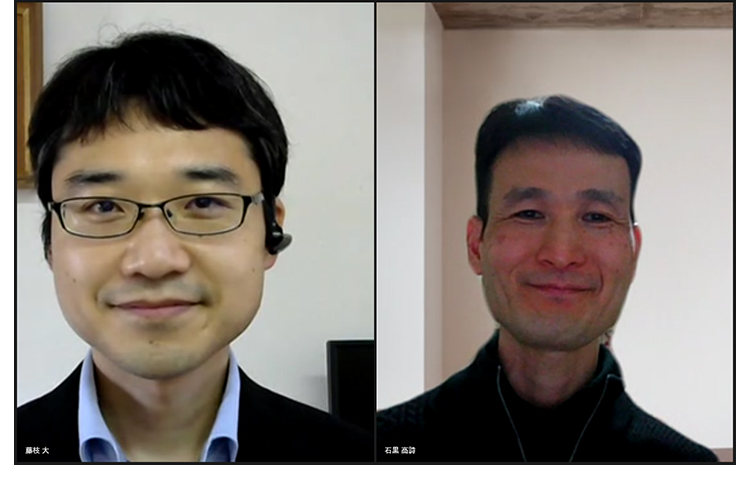
最新記事
テレワークのプライバシーとセキュリティを守る
それぞれのOKI入社の経緯と、入社後のキャリアを聞かせてください。
藤枝子供の頃から音楽、特に和音などの解析に興味を持ち、大学・大学院(博士課程)では電気工学科で自動採譜や多重音高推定などを研究しました。卒業後は、音声処理技術の研究を続けたいという思いから、2011年にOKIへ入社しました。
入社直後から雑音除去技術や音声帯域拡張技術など、学生時代の延長のような感覚でデジタル音声信号処理の研究開発に携わっていました。しかし、そんなお気楽な研究者生活も入社7年目頃から一変。先輩が研究開発を続けてきたエリア収音技術の製品化活動で、初めてプロジェクトマネージャーという大役を務めることになりました。品質保証や進捗管理などといったマネジメント業務を通じて研究開発と製品開発のギャップを実感し、私自身の意識も大きく変わったと思います。そして現在は、研究開発活動と並行し、事業部と連携しながらエリア収音技術の商品化を進めています。
石黒大学では電気工学科を専攻し、卒論のテーマは音声認識でした。とは言っても、一貫して音声処理技術に取り組んできた藤枝さんとは違い、私の場合は、それほど技術にこだわりは無かったと思います。OKIに入社したのは1990年。この頃はバブルの末期で、学生にとって売り手市場でした。入社直後に携わったのが局用交換機の音声処理や加入者制御回路LSIの開発。その後、局用交換機の需要が無くなると、キャリア向けVoIP-GW装置の開発を経て、2007年からはIP電話(ソフトフォン)の音質向上のためのソフトウェア開発から開発マネジメントにも従事。このようにハードウェア/ソフトウェア、アナログ/デジタルを問わず、さまざまな技術に関わってきました。そして、現在は、エリア収音技術の事業化に向けた社内外活動を進めています。
快適なテレワークのためのエリア収音とは、どのような技術でしょうか?
藤枝私たちは、快適な音から不快な音まで、さまざまな音に囲まれて生活しています。しかし、人と人が円滑に会話するためには、相手の声以外の音声は極力少ないことが望まれます。通常、特定話者の音声を拾うためには指向性の高いガンマイクなどが使われていますが、この方法だとマイク操作が必要なばかりか、マイクを向けた方向にある雑音も収音してしまいます。エリア収音は会話を交わすエリアの周囲に複数のマイクを設置し、特定話者の音声のみを収音する技術です。これは、複数のマイクの指向性をそれぞれ別の位置から話者の方向に交差させ、各マイクが拾った音声から共通の成分をピックアップし、それ以外の成分をリアルタイムで除去することで実現します。
用途としては、当初から駅構内などの雑踏に設置される案内端末や、消防・工事現場などの騒音環境での通話、ビデオ会議のハンズフリー通話などを想定し、実証実験を重ねたところで事業部へ移管し、2020年までには開発に区切りをつける予定でした。しかし、思わぬコロナ禍の影響でテレワークが急激に普及した結果、エリア収音は、在宅時における子供や家族の声、防災無線といった周囲の音や工事の騒音などの雑音の除去、また、オフィスでは周囲の会話からの情報漏洩などのリスク回避に有効という判断から、PC向けエリア収音マイクの商品化を急ぐことになりました。
コンシューマー向け商品ならではの難しさがある
商品化に向けた活動内容、課題などを聞かせてください。
石黒商品化は2つの方向性で進めています。1つは公衆の場に設置される案内端末などに組み込まれるシステムとしてのB2B商品、そしてもう一つは、個人が使うマイクロフォンなどのB2Cとなるコンシューマー向け商品です。ここで課題となるのは後者です。OKIはこれまでB2Cの実績がほとんどないため、B2Cに強いパートナーとの共創を選択しています。しかし、プロモーションやマーケティング全般を共創パートナーに依存するわけにもいかない。そこで、まずはB2B向けの技術的なプロモーションを先行させ、現在は、営業、SE、研究開発の各部門のメンバーをあつめたチームOKIで、B2Cに向けたプロモーションにも知恵を絞っています。今後にご期待ください。
藤枝エリア収音はOKIプレミアムフェアやCEATECにも出展しているので、基本的なプレゼン資料や動画コンテンツなどは一通り用意できています。今後は、これらをコンシューマー向けにアレンジし、まずはSNSなどを通じて積極的な情報発信をしていくつもりです。ちなみに、私が出演しているエリア収音マイクのプロモーション動画は、YouTubeのOKI公式チャンネル(※1)で公開されているので、是非ご覧ください(笑)。
※1 リモートワークのプライバシーとセキュリティを守るエリア収音マイク|CEATEC2021【OKI公式】(OKI公式YouTubeにリンクします)
商品化に向けた技術開発で苦労されている点はありますか?
藤枝私にとって音響に関する研究開発はライフワークのようなもので、苦になったことはありません。現在、エリア収音マイクのプロトタイプを作り、実際にテレワークで使いながら評価しつつ機能のブラッシュアップを進めています。ですが、私は研究気質が強い人間なので、どうしても多くの機能を盛り込んでしまう傾向があるようで、事業部からは「コンシューマー向けなのでシンプルに」とブレーキをかけてもらっています。また、技術者としてこだわりたい機能と、コンシューマーを含めたお客様が求める機能は必ずしも一致しないということにジレンマを感じることもあります。
石黒私も技術者なので、実は「機能載せたい派」で、藤枝さんの葛藤は痛いほど理解できます。多機能と言ってもソフトウェアで組んでいるので、高価なマイクや追加のハードウェアが不要であるならば、初心者向けの「フルオート」と、ヘビーユーザー向けの「マニュアル」の2つモードを用意すれば問題ないと、どちらかと言うと藤枝さんの肩を持ちがちです(笑)。
余談はさておき、私が苦労している点は、やはりB2B、B2Cを含めたマーケットに関する情報と知識の取得です。入社直後から開発に携わってきた局用交換機の製造が終わった際、請負型の製品開発の限界を感じたことから、マーケティングに興味を持ち、独学で学び続けたつもりですが、まだ満足はしていません。
藤枝いや、石黒さんは本当にビジネスやマーケットに詳しく、先ほど述べた機能の取捨といったところでも、いつもユーザー視線での的確なアドバイスをいただいて、感謝しています。
エリア収音技術をもっと身近に、そして世界へ…
商品化に向けた今後の展望や夢を聞かせてください。
石黒屋外や雑踏の中で使われる情報案内端末向けのシステムとしては、2022年度上期上市を目標として、活動を続けています。コンシューマー向けのエリア収音マイクについても、2022年度中の商品化を目指しています。
藤枝コンシューマー向け商品の開発は私としても初めての取り組みなので、是非とも成功させたいと思っています。そして、将来的には、PCや情報端末だけではなく、ビジネス、生活シーンはもちろん、医療や災害現場などを含め雑音環境下でのコミュニケーションが求められる全てのシーンでエリア収音技術が活用できる未来を夢見ています。もちろん、そのための努力は惜しまないつもりです。
石黒エリア収音は、世界でも通用する優れた技術です。だからこそ、将来的にはグローバルな市場展開を目指し、これからも営業、SE、研究開発が一体となった全員参加型イノベーションで、市場開拓と研究開発を推進したいと考えています。







