Yume対談
「OKI片桐常務とJapan Innovation Network松本常務理事がイノベーション対談(Yume対談)を行いました」
SUMMARY
ソリューションシステム事業本部(SS事本)は、既存事業の充実化と同時に、お客様やパートナーとDXエコシステムを構築し、新規事業の創出に取り組んでいます。今回は、JIN・松本常務理事と片桐常務執行役員(SS事業本部長)が、実践モードを迎えたOKIの全員参加型イノベーションと今後の事業戦略について語り合います。
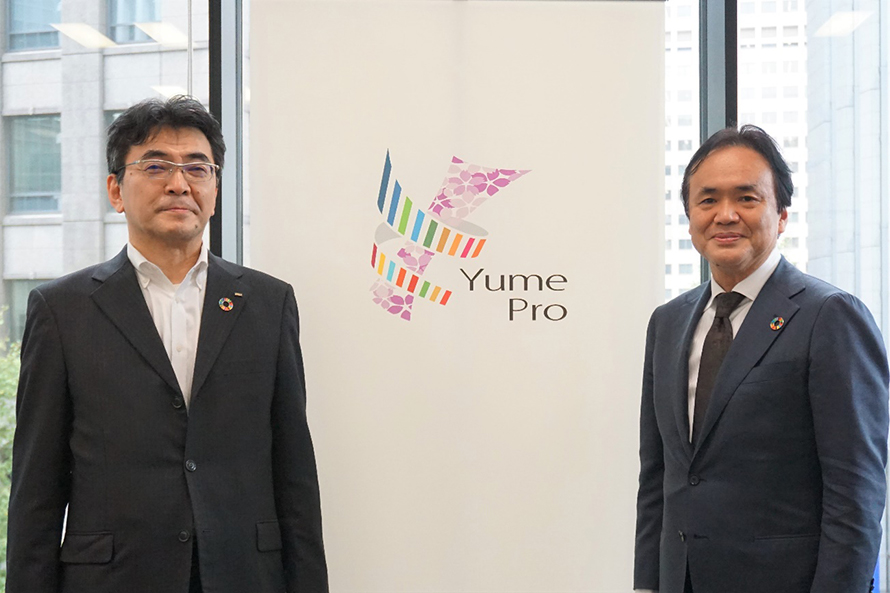
8年ほど前からイノベーションの取り組みは始まっていた
松本一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) 常務理事の松本毅と申します。
片桐さんは、今年度(2022年)4月に常務執行役員 ソリューションシステム事業本部長に就任されたそうですが、今日はビジネスのことを中心に、いろいろとお聞きしたいと思います。まずは片桐さんのOKIでのキャリアからお聞かせください。
片桐私は1984年にOKIに入社し、長く交通、防災など主に社会インフラシステムにSEとして携わってきました。2014年頃から新規事業の創出に関わるようになり、2015年からは執行役員という立場にいます。
松本今も新規事業というキーワードが出ました。OKIのイノベーションマネジメントシステム(IMS)は実践モードということで、新規事業の創出活動を強化されていますが、片桐さんとしては現状をどのように評価されていますか?
片桐OKIは長年、交通、防災、金融・流通、通信、製造業向けのソリューションを提供してきました。そして、2014年には、次世代の成長戦略として社会インフラにフィーチャーした新規事業の創出を目的に、社長直轄の「次世代社会インフラ事業推進室」が設置され、私は初代室長に就任しました。
当時、イノベーションという言葉は、技術・経営革新という意味で使われ、OKIとしても何かを変えないといけないという危機感は持っていたものの、その方法論は手探り状態で、目的も漠然としていました。その後、OKIの保有技術とSDGsが提示した社会課題との擦り合わせなどを行うことで、次第にその方向性が示されてきました。それと、IMSと出会ったことでイノベーションのベースとなる知識やスキルが身についてきたと思います。
この4年余りで、社員研修やYume Proの活動などを通じて全員参加型イノベーションの文化や風土が定着してきており、これからは、その成果を示すフェーズに入ったということで、イノベーションの実践モードとしています。
松本当時の次世代社会インフラ事業推進室では、どのような議論が交わされていたのでしょうか?
片桐当時の川崎社長が「精鋭であるには少数でなければならない」という強引な理屈(笑)で、営業やSE、研究開発部隊出身の7名ほどで発足したチームです。当初はインフラの定義として「次世代社会のインフラ」なのか「次世代の社会インフラ」なのかから始まり、従来の行政機関向けのシステムを主体とするのか、もっと幅を広げ少子高齢化社会などの社会課題全般の解決を目指すのかを議論していました。結果的には「次世代社会のインフラ」とするとテーマが広がり過ぎるので、当面は「次世代の社会インフラ」で社会課題解決を目指すということで落ち着きました。
松本営業、SE、研究開発など部門を超えたチームですね。いわば現在のOKIが進めている全員参加型イノベーションの原型とも言える活動ですね。そして、未来のビッグピクチャーを描き、そこから今やるべきことを進めていくという手法もIMSのプロセスと共通しています。
次世代の社会インフラと言っても、IoTやDX、AIなど次々に新しい概念や技術が生まれる中で、どのようにアプローチしていたのでしょうか?
片桐当初は10年後の社会インフラをデザインするつもりでした。しかし、それでは課題も技術も絞り込めないということで、3年くらいのスパンで考えることとなった結果、やはり、無線・有線の通信技術やセンシング技術といったOKIとして強みがある領域からアプローチしていくことになりました。
IMSのプロセスを新事業創出に実践
松本そのように新しいことにチャレンジする文化や風土が備わってきた現在、たとえば、お客様に提案する機会が増えただとか、ビジネスに変化はありますか?
片桐それはケースバイケースですね。私たちはソリューションシステム事業本部として、数多くのお客様に支えられています。こうしたOKIを信頼してくださるお客様に対して、これまでと同様に、受託開発のビジネスをしっかりと行っています。行政機関のお客様の場合、最近ではデジタル庁が発足するなど変化もありますが、実績や信頼に基づく長い慣例、慣習というものもあり、ビジネスの仕組みはドラスティックには変わりません。
一方で、新規事業を興す場合は、お客様と共創し、パートナーとエコシステムを組むなど、新しいビジネススタイルが必要になってきます。
松本やはり、お客様との信頼に基づくBtoBの受託開発ビジネスは重要であり、それとは異なるやり方を取るのは一朝一夕にはいかないわけですね。その中で、現在、OKIのIPCを中心に新事業の創出に注力されていますが、当時の片桐さんのチームは、その先鞭をつけたわけですね。
片桐次世代社会インフラ事業推進室が発足した2014年は、2011年の震災もあり、世の中的にも防災やBCP、そして社会インフラの重要性が再認識されていた時期でした。この頃から、これまでお付き合いのなかったお客様とコンタクトする機会が増え、異業種の方々と現状のお困りごとなど、ざっくばらんな議論をするようになりました。
松本そうなると、お客様との関係も従来とは違ってきますよね?
片桐そうですね。従来は、どうしてもお客様に買っていただくという立場が多かったのですが、新事業を創出する場合は、お客様とは対等なパートナーという関係性が生れてきます。

松本私は長年オープンイノベーションに取り組んできましたので、今もオープンイノベーションをテーマに講演させていただく機会があります。そこでは"How to do"から"What to do"へ、つまり、提示された明確な課題に対して解決策を導き出すのではなく、どのようにして課題を見つけるのかがポイントで、そのためにはIMSの「機会の探索」から「課題の特定」というプロセスをしっかり実行することが大切だという趣旨の話しをしています。現在、OKIのIPCでは、このIMSのプロセスを実践しているところですが、イノベーションの先駆者として片桐さんは、彼らのやり方をどのように評価されていますか?
片桐やり方に絶対的な正解はないと思います。とにかくトライすることが大事。それでうまくいけば成功体験として残るでしょうし、仮にうまくいかなくても、それを教訓にやり方を見直せばいいだけ。その試行錯誤を続けていくしかないと思います。"How to do"のようにゴールが見えている場合は、それに向かって突き進めばいいだけでしょうが、"What to do"のようにゴールが明確ではないプロジェクトは、どこかで一旦立ち止まり、良し悪しをジャッジすることが必要です。そのためには、KGI(※1)やKPI(※2)といった、しかるべき時期にプロジェクトを評価するプロセスを設けなければなりません。
松本現在、片桐さんが本部長をされているSS事本では、新規事業をどのように扱っているのでしょうか?
片桐まず、既存事業と新規事業をしっかり分けることが必要だと思い、昨年、事業本部内に「DX事業推進センター」を設置しました。これは、以前、私がいた次世代社会インフラ事業推進室をルーツとする60名規模の組織で、IPCと連携し新規事業を担っています。
松本DXというのは、まさにトレンドワードで、とりあえずDXを標榜してみようとする企業も多々見受けられます。その中でOKIは、技術の裏付けがあり、明確な指針も示しているという点でもアドバンテージが高いと思います。
片桐デジタル化のトレンドワードは、ITやICT、そしてIoTからDXというように変遷してきましたが、イノベーションやトランスフォーメーション(変化)は普遍的な概念だと思います。そのDXを推進するためには「何をトランスフォーメーションするのか」と「どうやってトランスフォーメーションするのか」の双方向からのアプローチが必要ではないでしょうか。
松本OKIが市場ニーズ、つまり社会課題を特定し、それに新しい技術で解決策を模索するというIMSのプロセスを実践していることを再認識させていただきました。
失敗は学びの機会。試行錯誤やチャレンジを重ねることが大事
松本さて、SS事本の本部長として、昨今の社会情勢、ビジネス環境、そしてOKIの変化について、どのようにお考えでしょうか?
片桐一番の変化は、コロナ禍によりリモートワークが増えるなど働き方の変化ですね。コロナ禍に関連した事業的な大きなインパクトとして、半導体の供給不足、いわゆるサプライチェーン問題を抱えています。そのような想定外の事態に遭遇しても事業を継続し、収益を上げていくのが私に課せられたミッションです。いかなる変化にも対応できるトランスフォーメーション、イノベーションを進めなければならないと思い、手探りでチャレンジを続けています。そういう試行錯誤は、IMSのプロセスだと松本さんからもお墨付きをいただいたので、その方向性は維持したいと思います。
社内的にはIMSという仕組みを提示することによって、考え方や仕事の進め方などを変えられる社員が増えてくるでしょうし、たとえ失敗しても試行錯誤を重ねることによって個人の経験値も上がり、いずれはいい結果につながると信じています。つまり、失敗は学びの機会として割り切ることも必要です。
松本今後の経営において、これまでのやり方を維持するポイント、そして最も変化が必要なポイントのそれぞれをお聞かせください。
片桐まず、従来からOKIを信頼していただいているお客様に対して安定的にサービスを提供していくことは、絶対に維持していかなければなりません。
変化という点では、OKIが保有しているネットワークやセンシングなどユニークな技術をこれまでのお客様と全く違う業種のお客様に展開していくことだと思います。そのためには、新たな技術を社会が受け入れる社会的受容性を高める必要があり、異業種の方々とのコミュニケーションや共創を深化させなければなりません。
松本その意味でもOKIのYume Proなどの活動は重要だと思います。
私は以前、エネルギー企業にいたのですが、政府のエネルギー政策の転換により新事業への参入など大きな転換期を迎え、大変苦労したことがあります。大きな岐路に立たされ業種や企業は変化を求め、新しい技術やパートナーを求めていると思います。
そこで、OKIが新規市場開拓として注力している領域はありますか?
片桐モビリティや医療・介護、そして道路・橋梁・建物などインフラの維持管理などといった分野に対するサービスは8年前から構想し、現在はIPCとも連携しながら実証実験などを行い、本格的な社会実装を目指しています。
松本先ほど話題にされた社会的受容性について、民間企業のDXは徐々に浸透していますが、従来からOKIのお客様でもある行政機関や自治体などのDX化などについては、どのようにコミットされるお考えでしょうか?
片桐行政機関の方々とは、システム提案等を通じてコミュニケーションは取り続けています。皆さんトランスフォーメーションの必要性は十分認識されていますが、実際に動き出すのは時間を要するものも多いのではないかと感じています。
一方、地域レベルの連携は、すでにいくつかの市町村と包括連携協定を結び、さまざまな実証実験などを実施させていただいています。このような取り組みを通じて、技術の成果を自治体や住民の皆様にお見せすることで、OKIの技術やサービスに対する社会的受容性の向上を期待しています。また、それが次第に広く伝わっていくことも期待しています。
松本グローバルな事業展開については、いかがお考えですか?
片桐現在、SS事本のメインであるソリューションビジネスは、国による政策から文化、習慣にも左右されるので、海外展開し定着させるには時間がかかると思います。したがって、まずは国内でしっかりと実績を残し足場を固めることをまずはやっていきたいと考えています。しかしながら、少子高齢化や労働力不足、自然災害の発生、インフラ構造物の老朽化など、日本と同じ社会課題を抱えている国や地域は多いと思うので、近い将来にはローカライズさせたソリューションを提供していくことも考えていきたい。
松本最後にIMSについてお聞きします。
2024年頃にはIMSの国際標準規格としてISO 56001が制定される予定で、現在、世界各国の企業が認証取得へ向けた活動が続けられています。その中でOKIグループはどのように対応されるご予定ですか?
片桐ISOの認証に関しては品質管理等も含めて、全社的に一括管理している部門があります。IMSに関してはIPCが中心となって取得に向けた活動を続けています。ISO 56001は9001の品質マネジメントや14001の環境マネジメントなどと同様、これからのビジネスには不可欠な規格となるはずです。IMSの仕組みが標準化されると、先ほども申し上げた通り、ゴールを定め、そのゴールまでの達成度合いをモニタリングしながら活動すれば、軌道修正も容易になるので期待しています。
松本失敗しても何度でもチャレンジできる仕組みができるわけですからね。
片桐社会の変化に対応して新事業を創出することは、業種を問わず大きなテーマだと思います。私自身の経験則から考えても、ゼロを1にするのと、1を10にするのでは苦労や努力の面でも全く違うのは明らかです。イノベーションは、まさにゼロから1を生み出す作業でもあり、そういうことを一人でも多く体験してもらうため、教育を含めて力を注ぐつもりです。
※1 KGI(Key Goal Indicator):ビジネスのゴールを定量的に示した指標
※2 KPI(Key Performance Indicator):ゴール達成までのプロセスを定量的に図る指標

<インタビュアープロフィール>
松本 毅
一般社団法人Japan Innovation Network 常務理事
IMSエバンジェリスト
(兼)大阪大学大学院工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 客員教授
1981年に大阪ガス株式会社入社後、さまざまな新規事業創出を手掛け成功に導き、同社の技術戦略部 オープン・イノベーション担当部長、オープン・イノベーション室長などを歴任。
2016年4月から2019年2月まで、株式会社ナインシグマ・ジャパン ヴァイスプレジデント。2019年3月から2020年10月までナインシグマ・アジアパシフィック顧問。
2020年11月から兼務にてリンカーズ(株)顧問 Open Innovation Evangelist
2013年Japan Innovation Network設立メンバー(理事)、2019年3月から常務理事(現職)
(2022年12月27日 イノベーション推進センター)







