Yume対談
「無関心層を動かすために、必要なこととは?
東急不動産×OKIが目指す、行動変容を促す健康増進サービスに迫る」
SUMMARY
健康経営に注目が集まる中、東急不動産とOKIは、ヘルスケアソリューション開発を目指すコンソーシアムにおいて、行動変容を促す健康増進アプリの開発を進めています。そこには、OKIが長年研究を続けている行動変容技術が取り入れられています。今回は、東急不動産の若松氏と鈴木氏をYume STにお迎えし、プロジェクトメンバーである岩井部長と武市、そして藤原執行役員CINO兼CTOが、コンソーシアム立ち上げの背景などを語り合いました。

働き方の変化により多くの企業が抱える従業員の健康管理の課題。その解決に挑む
藤原OKIがイノベーション活動をスタートした頃から、ヘルスケアは注力領域に据えていました。そこから手探りではありますが、キーリソースである行動変容のエンジンを活かしてサービスの開発を続けています。今回の東急不動産様とのコンソーシアムは非常に楽しみであり、新しいヘルスケアソリューションの社会実装を必ず実現させたいという気持ちです。本日は、コンソーシアム組成の背景など、お話しをしていきたいと思います。でははじめに、自己紹介をお願いします。
若松東急不動産の若松です。当社が所有しているオフィスビルの運営・営業・管理を主な業務としています。最大のミッションは、資産価値の維持と向上です。我々のアセットを活用して、最大限のパフォーマンスを発揮することを目指しています。
鈴木東急不動産の鈴木です。私は日比谷パークフロントなど、大型物件の運営が主要なミッションです。また、来年竣工を迎える桜ケ丘の再開発プロジェクトも担当しています。
岩井OKI 第二営業本部 営業第二部の岩井です。第二営業本部は、主に大手金融や通信キャリア、旅客交通といったお客様をご支援しています。私の最大のミッションは新規領域の開拓で、イノベーション推進センターのメンバーと新しいことに取り組んでいます。
武市OKI イノベーション推進センター ビジネス推進部の武市です。OKIで今まで手掛けてこなかった領域で事業開発を担当しています。現在は研究開発部門のメンバーと共に、さまざまな企業と共創を進めているところです。東急不動産様には、私たちだけでは前進できないところを、高い目標を掲げることで引き上げていただいています。
藤原続いて、東急不動産様より、今回活動の背景についてお話しいただきたいと思います。まず、デベロッパーである貴社が、ヘルスケア領域に着目した理由をお聞かせください。

若松皆さんご存知の通り、コロナ禍により働き方はガラリと変わりました。在宅勤務の急速な普及、それからオフィスと在宅勤務とのハイブリッドワークの広がりにより、センターオフィスの在り方も変化しつつあります。これまでは毎日出勤する場でしたが、これからはコミュニケーションを取る場としてのセンターオフィスが求められているのです。
そしてハイブリッドワークが広がる中で、生活リズムの乱れによる身体の不調や、在宅勤務での孤独感などによるメンタルヘルスの不調を訴える方が増えており、多くのお客様が、従業員の健康管理が難しくなってきたとおっしゃっています。働くシーンの中で生まれた課題ならば、働く場であるオフィスを提供する我々が何か手を打たなければ、存在価値がないと考えました。健康経営の一助となるようなソフトサービス、そしてコミュニケーション活性化につながるオフィスというハードサービス、この両軸で新たなサービスを提供することで、選ばれ続けるオフィスビルが供給できるはずです。そこで、「ヘルスケア」をテーマとして据えることになりました。
藤原OKIも2018年からヘルスケア領域に本格的に取り組んでいますが、コロナ禍によりそのニーズが急速に増加しましたね。特に、従業員の健康管理の課題は、特定の企業だけで起こっているのではなく、もはや社会課題です。そこを改善するという意味では、ソフトとハード、両面からサービスを提供することは非常に効果的だと思います。
社会課題は1社だけの力では解決できない。だからこそ、コンソーシアムを組成
藤原コンソーシアムの発足について、2022年5月にプレスリリースを出していらっしゃいましたが、反応はいかがでしたか?
若松非常に反響が大きかったです。大企業から、渋谷という街ならではのスタートアップなど、さまざまな企業から反響をいただきました。発足時のコンソーシアムメンバー11社に加えて新しい技術が肉付けされつつあり、いいサービスができそうだと確信しています。
藤原なるほど、新たな接点が生まれているのですね。ぜひコンソーシアム組成に至った経緯も、お聞かせください。
鈴木社内プロジェクトとしては2021年の年明けにスタートし、最初は社内のメンバーで話をしていました。しかし、我々はヘルスケア領域でのノウハウがほとんどなく、個社だけでは良いサービスを提供できません。そこで、健康にフォーカスしたさまざまなプロフェッショナルにお会いして相談する中で、ビジョンに共感してくださる方が多いことが分かったのです。ならば、オープンイノベーションの精神で、さまざまな企業のリソースやノウハウ、技術を掛け合わせることで、より良いサービスを世の中に提供できるのではないかと感じたのです。それが、コンソーシアムを組成することになった理由です。

藤原コンソーシアムは4つの事業化検討テーマ(1)ウェルネスオフィスの構築、(2)産業保健活動のサポート、(3)行動変容を促す健康増進サービスの開発、(4)エリア健康管理室の実装を掲げており、OKIは(3)の行動変容のテーマに参画しています。
岩井さん、武市さん、今回の共創にどのように想いで取り組んでいますか?
岩井OKIは社会インフラに関わる技術や製品を提供して、これまでお客様のビジネスを支えてきました。しかし社会課題を解決するには、さまざまなプレーヤーと共創し、現場の課題を捉えながら新たなサービスをつくっていかねばなりません。今回の健康増進は、多くの企業にとって共有するテーマであり、それぞれ悩んだり取り組みを進めたりしていらっしゃいます。中でも、私の部門で担当している保険会社様は、まさしく人々の健康についての知見やノウハウを豊富にお持ちです。そういった、さまざまな業界の方々と手を組んでサービスを実現させていきたいという想いで取り組んでいます。
武市東急不動産様とOKIと、コンソーシアムの皆さんで開発するサービスが、本当に世の中や企業にとって必要なものに育てていけるかどうか、まだ現段階では2合目3合目付近だと思っています。今年度行う実証実験などで東急不動産様のテナントである企業様のご反応を見ることで、本当に勝てるサービスになっているのか、そしてOKIが入ることによって競争力に寄与できているのかどうかを確認していきたいですね。
無関心層の行動変容にあえて挑む。それこそがイノベーション
藤原藤原 ヘルスケア領域でのアプリケーションやサービスは、世の中にたくさんあります。しかし、短期間で使われなくなることが多く、これが大きな課題です。本当に価値があり、肌身離さず使いたいと思えるようなサービス・アプリケーションにするために、1つキーワードとなるのが、「行動変容」です。ここになぜ着目したのでしょうか?

若松企業にはさまざまな従業員の方々がいらっしゃるものの、健康のためのサービスは、「皆が使えるもの」でなければ導入ができません。福利厚生は、一部の人だけに偏ってはいけないからです。しかし健康領域では、多くの方がいわゆる「無関心層」です。そこを動かすのは難しく、ヘルスケアのプロに相談しても、誰もが口をそろえて「無関心層に手をだしてはいけないよ」とおっしゃっていました。
鈴木お話しを聞いた企業様も、ほとんどが無関心層を諦めていらっしゃいましたよね。これは大きな問題だと思いました。
若松しかし、新たな領域にチャレンジして、価値を創造してこそのイノベーションじゃないですか。そう考えていた時に、武市さんと話をする機会がありました。「私たちも無関心層を、インセンティブを使わずに動かすことにチャレンジをしたい」と、まさに私たちのビジョンと合致するお話しをしていらっしゃったんです。嬉しかったですね。それから議論を深めていくと、無関心層にアプローチするには、行動変容を促すことが大切だという結論に至りました。そして、多くの無関心層を動かすドライバーとして、OKIさんの行動変容の技術は確実に生きてくるはずです。私も色々調べましたが、行動変容科学分野の研究開発は、OKIさんが第一人者ですから、ぜひご一緒したいと考えました。
鈴木我々もデスクトップリサーチや市場調査などを行い、経営層の健康投資に対する意識は強いことは見えました。しかし、あまり具体的な行動には至っていないように感じていました。ではどうすれば企業が投資をしてくれるのかというと、やはり効果があるサービスが必要です。その意味でも、行動変容というテーマは絶対に切り離すことができませんね。
行動科学に基づくパーソナライズド介入エンジンで行動変容を起こせるか
武市当社の健康保険組合であるOKI健保の担当者も、無関心な人が多く本当に健康サービスを使って欲しい人がなかなか利用してくれないと話していました。行動科学にはさまざまな人にそれぞれ合った効果的な技法があります。一人ひとり、どのようなサービスなら使ってみようと思うのかを探り、戦い方を増やしていかなければいけないですね。
若松そうですね。いつも社内で話しているのは、「無理なく手間なく」という言葉です。生活導線の中で何ができるのか、そっと寄り添うサービスでなければ継続することはできません。だからこそ、無理なく手間なく使っていただき、心身に不調をきたす前に無関心層の関心を引き上げて、健康に対する意識を高めるようにしたいと思います。すると、確実に生産性が上がり、企業の利益につながるでしょう。この好循環を回していきたいです。

岩井行動変容を促すトリガーは、意外と本人が気付かないところにあると思います。そこに寄り添い、背中を押せるサービスができたらいいですよね。さらに、今回はコンソーシアムという形でさまざまな技術やノウハウを持つ企業がありますから、色々なサービスの形を考えることができますし、実現することもできます。それは非常に心強いですし、面白いと思います。多くの企業が健康経営の取り組みをしながらも変わらないのはなぜか、営業としてお客様との対話のなかで掘り下げていきたいと考えています。
藤原今年度に実施するのPoCにOKIも参加させていただくことが決まっており、非常に楽しみにしています。1度目は5月に実施したということですが、そこから見えてきたことについてもお話しいただけますか?
若松PoCの第一弾は、当社オフィスビルの渋谷ソラスタのテナント企業で働く方々を対象に、「食事改善」のサービス実証を行いました。具体的には、コンソーシアム参画企業であるライフログテクノロジー社のアプリ「カロミル」を通して、一人ひとりの健康状態や食事記録をもとに周辺の飲食店の最適なランチメニューのレコメンドを行い、個人の健康意識や行動変容の効果を検証しました。先日、その分析結果が出たのですが、非常に面白い結果となっています。今後のPoCでは、OKIさんの行動科学に基づいたパーソナライズド介入エンジンを活用して、インセンティブに頼らず、さらに運動データも掛け合わせたことも実験をしていきます。
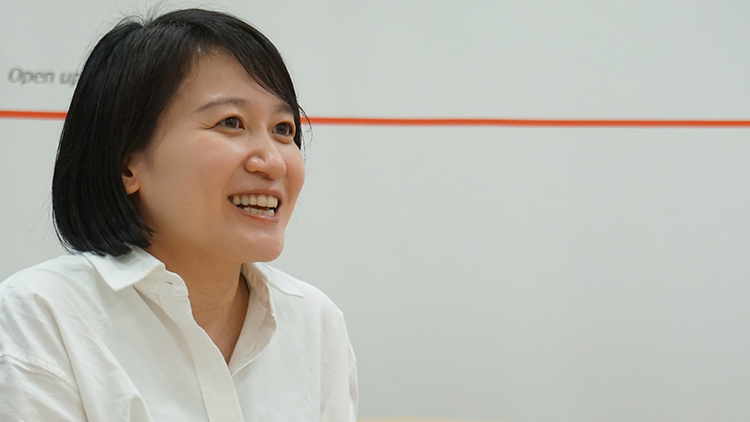
健康無関心層の意識と行動を変え、世の中をより良くしていきたい
藤原それでは最後に、今後の展望についてそれぞれお聞かせください。
若松当社でよく話しているのが、私たちの事業はBtoBtoCだということです。行動も考えも多様化する今、サービスも一人ひとりに合わせて変化できるようにしていかなければなりません。このコンソーシアムを大きく育てる中で、ヘルスケア領域を超越する可能性もあります。その進化も楽しみながら、人やシーンに寄り添ったサービスを提供し、評価されるものにしていきたいですね。当社としても、どんどんリソースを割いて、健康経営に投資もしながら、引き続き力を入れていきます。
鈴木若松がPoC第一弾の話をしましたが、これは最適なランチメニューをレコメンドし人々の健康に寄与するサービスでありながら、街の飲食店を活性化するという効果ももたらすのではないかと思います。そしてこれは、飲食店のみならず、さまざまな業界に広げることができるはずです。あくまで主眼としては健康経営ですが、副次的な効果としてどのようなものがあるのか、常に考えながらサービスを育てていけたらと思います。
岩井これからPoCを経てサービスが実用化されれば、健康無関心層の方々が自らの健康を意識するようになります。そして人が変われば、企業や街にも影響を及ぼし、やがて世の中全体が変わっていくでしょう。そんな夢のような未来に向けて、コンソーシアムの皆さんと一緒にチャレンジしていくことにワクワクしています。
武市健康無関心層の意識を変えていくことは、非常に難しいことです。しかし、誰もが健康でありたいと思っていることは確かです。私たちも難しいことに挑戦しながらここまでやってきて、今では短期間であれば行動変容したという成果が各所で出ています。その期間を少しずつ長くし、1人でも多くの人を対象にしながら、価値を創造していきたいですね。
藤原思わず使ってしまう、肌身離さずチェックしていたくなるようなサービスをつくって、東急不動産様のお膝元である渋谷から日本中に発信していきたいですね。必ず成功させましょう!本日はありがとうございました。
<参加者プロフィール>
東急不動産株式会社
都市事業ユニット 都市事業本部 ビル運営事業部 若松グループリーダー
都市事業ユニット 都市事業本部 ビル運営事業部 鈴木主任
OKI
第二営業本部 営業第二部 部長 岩井
イノベーション推進センター 武市
インタビュアー:OKI執行役員CINO兼CTO 藤原







