Yume対談
「OKI×Jdexの共創が、データドリブン社会に投じた一石。」
SUMMARY
社会全体のDX化をより一層、進めていくために、OKIと株式会社日本データ取引所(Jdex)は、個々の組織でサイロ化している膨大なデータの活用に着目しました。
両社は、データ活用の高度化に向け、データの流通や取引、それに伴う効率的なデータ活用手法である「データ活用ゴールモデリング」で、共創の取り組みを進めています。今回は、Jdex・森田直一社長と、イノベーション推進センター(IPC)の前野蔵人センター長を中心に、共創の経緯や成果、将来のビジョンまで、大いに語り合います。
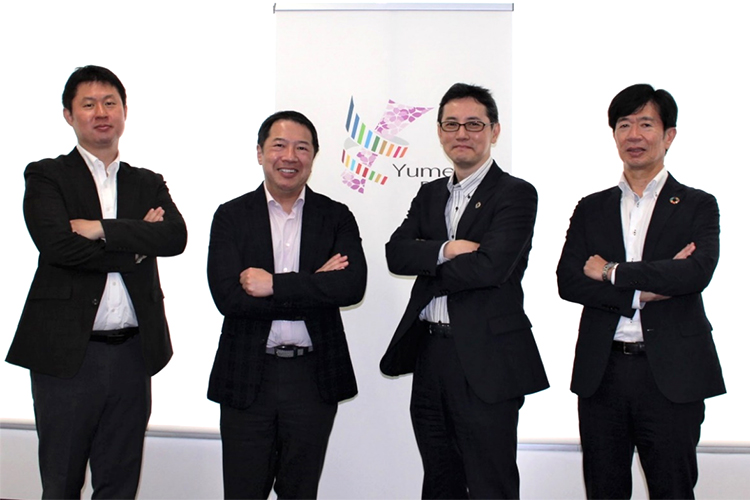
OKI前野IPCセンター長、AI技術研究開発部 須崎部長
将来を見据えた人材交流という共創のかたち
前野本日はご足労いただきありがとうございます。
御社とは2021年度よりデータ活用に関する共創を開始しています。OKIからは研究員の派遣も行い、現場での共創関係も深めている、大変重要なパートナーです。私自身はよく存じ上げているのですが、今回は改めて読者の方に向けて、森田社長の自己紹介とJdexさんのプロフィールからお聞かせいただけますか。
森田私は新卒で大手商社に入社し、商社マンとして20年以上のキャリア重ねる中で、ITやインターネットビジネスに興味を持ち、その後、独立してさまざまな活動をしていました。その過程で多くの方々からのご支援、ご協力を得て、2016年に日本データ取引所(Jdex)を起業しました。2010年代から「ビッグデータ」というキーワードが盛んに語られていますが、企業や組織の枠を超えたデータの流通や活用を促す仕組みや技術は、未だに試行錯誤の状態です。当社は、企業のデータ活用に関するコンサルティング、AIを活用したデータ活用技術の研究開発などを手掛けており、「日本のデータを民主化する」をスローガンに、公正・安全・信頼性を担保したデータエクスチェンジビジネスの事業化を目指しています。
ちなみに、起業の際、ベンチャー企業らしくカタカナやアルファベットの社名をいくつか考えていたのですが、何をやっているかわかりやすい社名の方が社会にアピールできるという判断から、極めてシンプルでストレートな社名としました(笑)。

前野まさに、日本のデータ流通の中心的存在と自負されているということですよね。OKIは、ICTで社会のインフラを担っている企業ですが、このインフラがデータの流通・活用の側面で、大きく変化してきている昨今、御社とのパートナーシップは今後のお互いの成長に、必要不可欠であると感じます。OKIは、2018年度から「Yume Pro」と名付けて進めてきたイノベーション活動を進めていますが、こうした組織的な地固めがあり、御社との連携がスピード感をもってスタートできたと思います。
森田そうですね。私も当初、歴史ある企業のOKIさんが、海の物とも山の物ともつかぬベンチャー企業を本気で相手にしてくれるとは思っていませんでした。でも、話しをしていく中で、「資金提供や業務提携などよりも、OKIさんの優秀な人材をお借りできないか」と、お願いしてみたところ「在籍型出向で検討する」と前向きなお返事をいただきました。そして、2021年度から、奥谷さんというエース級のAI技術者を派遣してもらっています。
前野奥谷には、データ流通と活用を題材に企業経営を実践されている森田社長のそばで、経営者のマインドを学んできてほしいと考えています。これはイントレプレナーシップ(社内起業家精神)の養成としての側面です。またOKIは、これまで自社製品の故障検知など、メンテナンス現場で活用するデータ分析や予測手法などを確立してきましたが、社内業務のDXを進めるものが多く、事業化は進んでいません。Jdexさんが持つデータ取引や流通・活用のノウハウとOKIのテクノロジーを融合することにより、付加価値の高いソリューションの事業化を目指すというのが、今回の共創の目的でもあります。
森田はい。当社としても、そのシナジーが最大化していくことを期待しています。

サイロ化されたデータを組織全体で有効活用する独自のメソッド
須崎OKIはセンシング分野で長年の実績があり、豊富なセンシングデータの蓄積があるものの、それがうまく活用できていなかったため、10年ほど前からAIなどを活用したデータ分析や活用技術の研究開発を組織化しました。奥谷自身、「データ活用ゴールモデリング」というOKI独自のAI・データ分析手法を開発した技術者です。彼には、社会課題の解決に貢献するデータ分析と活用ノウハウを実践の場で学んでもらいたいと思っています。

前野いま話題にあがった「データ活用ゴールモデリング」について、開発者の奥谷さん、簡単に説明してもらえますか?
奥谷現在、多くの企業がDX推進に取り組んでいます。しかし、実際は組織内の各部門が持つデータがバラバラに管理され、やり取りの方法も統一されていない、いわゆるデータのサイロ化により、意思決定に必要なデータの分析・可視化が困難な課題があり、DX推進の妨げとなっています。OKIの事例では、保守や営業、コールセンターなどの部門間で、自社製品のリペア、故障対応といった似通った問い合わせに対し、同じような回答を個別に繰り返している状態で、それぞれの現場から「非効率で、何とかならないか…」という要望がありました。私が考案した「データ活用ゴールモデリング」は、部署ごとに達成したい要求と保有するデータを整理し、適切なAI技術の活用方法をモデル化します。したがって組織全体が情報を共有でき、迅速で効率的なデータ分析と活用を促進します。言い換えれば、“要求工学に基づく最適なデータ活用環境を構築する設計図”のようなものです。
前野なるほど。それで、OKIの奥谷はJdexさんのビジネスに貢献できていますか?
森田もちろんです。すでに、当社の既存のお客様数社と「データ活用ゴールモデリング」を活用したDX推進のPoCが進められています。また、このメソッドは、当社のお客様に対するコンサルティングツールとしても活用させてもらっています。
また、奥谷さんが持たれているデータ分析の知見やノウハウを共有することで、当社としてもサービスの質と幅が広がります。さらに、お客様は奥谷さんがOKIの方だとご存じなので、当社がOKIという技術的なバックボーンを持つ信頼性の高いベンチャー企業であることをアピールできていると思います。
自らの技術がお金に変わる瞬間に立ち会う
奥谷私もこのメソッドを考案した時、机上の空論で終わらないか、実際の現場で使えるのか半信半疑でした。しかし、Jdexのお客様が抱えるデータ活用の課題に対し、「データ活用ゴールモデリング」を適応すれば、アジャイルに解決策を示すことができるなど、汎用性があり現場で使えるツールであることを、実践を通じて確信できたことがとても嬉しく、モチベーションも上がりました。
森田奥谷さんはOKIでは研究開発職で、お客様に接する機会が少なかったと思います。その反面、当社ではお客様の現場に出向き、直接コミュニケートすることが多いので、奥谷さんにとっても大変有意義な経験になっていると思います。
前野OKIでは、職種や部署の枠を超えた取り組みとして、研究開発職もSEや営業ともにお客様のもとに出向き現場の生の声を聴き、お客様に価値提案をする「全員参加型イノベーション」に取り組んでいますが、奥谷さんはさらに一歩先を行っていますね。
人材もデータと同じでサイロ化してしまっては新しい価値は生み出せません。奥谷さんには会社の枠を超えた人材交流のロールモデルとなってくれることを期待しています。
奥谷Jdexに出向したことで、お客様のデータ活用上の課題に直接向き合い、自らの手法に基づいて改革・改善策を提案することで対価を得ることができました。言ってしまえば、自身の技術やスキルが適正に評価され、お金に変わる瞬間に立ち会えました。これはOKIの研究開発では味わえなかった新鮮な喜びです。
前野お金の話題が出たのでお聞きしますが、「データ活用ゴールモデリング」の活用でレバレッジは効いていますか?
森田現状、コンサルで適応している件数は少ないのですが、利益は出ています。これをある程度ターゲットとする業種を絞りつつ横展開することで、その効果は上がってくると期待していますが、課題もあります。それは現在、このメソッドを使いこなせているのが奥谷さんだけということです。今後、誰でも使えるように各スタッフのスキルアップが必要だと感じています。
OKI、Jdex双方の強みを活かせる共創プロジェクトを
前野人材育成が課題ということですが、OKIとしてはコロナ禍でテレワークが増える中、教育面で試行錯誤しているところもあります。Jdexさんはどういったことを意識されていますか?
森田人材育成としては、当社は社員構成の面で課題を抱えています。とくに、30代前半までの若手が中心で中堅社員がいないことです。そういった中で、奥谷さんは若手にとってのいいロールモデルとなっていただいています。
逆に、1年余り当社で実務をされた奥谷さんから、率直な感想を聞いてみたいです。
奥谷OKIは歴史が古く伝統もあり、多くの実績やノウハウを背景にした技術力、組織力があります。また、業務にしても働き方にしても確立したルールがあり、それが社員にとって安心して働ける環境である反面、改革を遅らせる要因になっているような気がします。
一方、Jdexはこれからルールが作られていく段階ですが、少人数なので社員一人ひとりの役割は大きく、逆に言えば会社の成長は社員のスキルに左右されやすいと思います。しかし、意思決定が極めて速く、変化への対応力も強いことを実感しました。私としては両社の特長を活かし、今回の共創を両社の強みを活かしてプロジェクトを進め、共創活動全体を成功に導きたいです。

データ活用で社会課題を解決していく
前野今後、SDGsネイティブと呼ばれる人たちが社会に出てきます。彼らはベンチャー志向が強く、OKIとして、彼らにどのようにアピールしていくかと同時に、これからの激動の時代にどう成長を作っていくのかが大きな課題です。森田さんは、ベンチャー企業の経営者として、どのような認識をお持ちですか?
森田かつてのベンチャー企業は投資家から資金を集め、何としても早期に株式上場を目指し、会社としての資産価値を高めることが求められていました。しかし、2010年代後半あたりから、起業家や投資家のマインドに変化が見え始め、利益を上げることはもちろんですが、OKIが取り組まれているような社会課題への解決姿勢も企業価値として評価されるようになっています。当社としても、データ活用のコンサルティング事業でしっかりと足元を固めて、データの取引・流通などの次のステップへ投資したいと思っています。

前野最後に、今日の総括として、みなさんの今後のビジョンや目標を聞かせてください。では、両社の架け橋となる奥谷さんからお願いします。
奥谷まず、Jdexの一員としては、「データ活用ゴールモデリング」の適応範囲を広げ、コンサルティングビジネス、さらには本格的なデータ取引市場の成功に貢献したい。一方、OKIの社員としてはJdexで得た実践的な経験やノウハウをOKIに持ち帰り、共有すること。そして、これからのデータドリブンな社会の中で、OKIやJdexのプレゼンスを高めたいと思います。
須崎奥谷さんの上長という立場としては、奥谷さんが得意とするロジカルな発想に、Jdexさんのビジネスの最前線で学んだ実践的なデータ活用ノウハウを融合させて、付加価値の高いソリューションの事業化に貢献して欲しいと思います。
森田将来的には、当社が行うデータ取引のプラットフォームに「データ活用ゴールモデリング」を連携させることで、複数企業間の連携DXを支援するプラットフォームの実現を目指しています。そして、私たちは「データの民主化」と称していますが、どんな小さな企業や団体であっても、必要なデータに安全にアクセスし、データドリブンな意思決定ができる環境を提供したいと思っています。それを実現するためには、当社単独では不可能なので、今後もOKIさん、奥谷さんなどお力添えをお願いします。
前野円滑なデータ活用環境は、これからの社会インフラの根幹をなすものです。是非ともこの共創を成功させましょう。
本日はどうもありがとうございました。
(2022年7月11日 イノベーション推進センター)





