『CINO ism Vol.56』
IMSを共通言語に、OKIからイノベーションの輪を広げていく
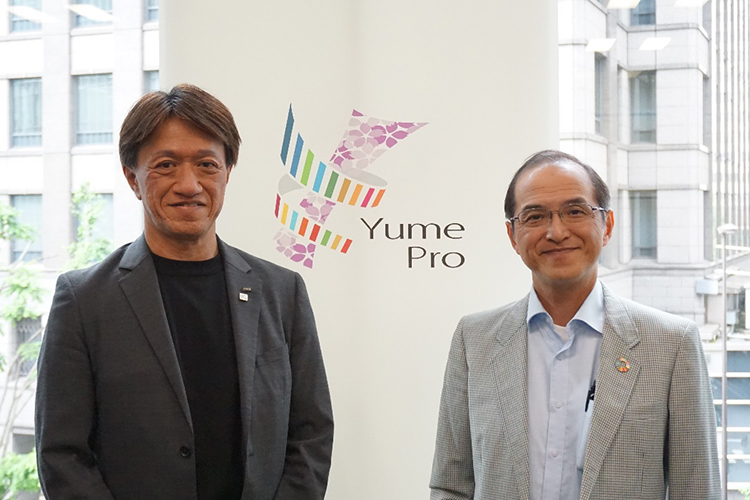
OKIコンサルティングソリューションズ 千村 保文
最新記事
独自のイノベーション・マネジメントシステム「Yume Pro」のもと、実践を続けてきたOKI。IMSを共通言語とするために、社内だけではなく社外の共創パートナーと課題解決に取り組む「共創ワークショップ」を実施しています。
これまでの取り組みや成果、今後のビジョンについて、イノベーション塾長を務めるOKIコンサルティングソリューションズの千村保文さんと対談しました。
イノベーションに課題を抱えるお客様の声から生まれた「共創ワークショップ」
藤原OKIは、イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の国際標準ISO56002をいち早く取り入れ、イノベーション推進活動を推進してきました。新規事業の創出、既存事業の革新、そして業務改善を含めたイノベーションを起こす企業になるという目標のもと、IMSを実装すべく、2018年から活動を始めたのです。OKIのイノベーション活動は世の中からも注目を集め、メディアにも取り上げていただいており、様々な企業様からお問い合わせをいただいています。そして2019年頃からOKIイノベーション塾長である千村さんに、お客様の新規事業アイデアや人材育成に向けたワークショップを「共創ワークショップ」として提供してもらっています。これまで10社を超えるお客様と実施していますが、この共創ワークショップを始めた背景からお願いします。
千村2018年から本格的に、OKIのIMS「Yume Pro」を公表し、社内向けに様々なイノベーション研修を始めました。藤原さんが中心となって、それを積極的に社外にも発信していたことから、お客様から多くのお問い合わせをいただくようになったのです。やはり、製造業をはじめ、日本の企業はイノベーション創出に強い課題感を抱いています。「OKIで実施している教育を、うちでもやってくれないか」という声もいただくようになりました。社内向けの研修プログラムですから、当初はお断りをしていたんです。しかしある時、某製造業から「同じような課題を抱える会社同士、一緒にやりませんか?」とご提案をいただき、それならばOKIの社員の育成になると考え、実施することにしました。それが、「共創ワークショップ」の始まりです。
藤原OKIのIMS「Yume Pro」は、これまでの日本の製造業の業務の進め方や、新規事業プロジェクトなどとは一線を画しています。自社の商品やサービス、技術などを発想の起点にするのではありません。SDGsのゴールなどの社会課題、今まさに世の中で起きていることや、現場の困りごとからアプローチしていく、まさにデザイン思考を突き詰めるプロセスです。実際に、最初の共創ワークショップでの反応はいかがでしたか?
千村新規事業アイデアの発掘を目指して、SDGsをテーマに20名ほどの参加者で3カ月ほど実施しました。社外では初めての取り組みだったこともあり、手探りで進めていったのですが、お互いに新しい発見がたくさんあった共創ワークショップでした。参加した社員の方々が前向きに取り組んでいたことはもちろん、その上司や経営陣の方々からも「従来の“研修”とは全く違い、新たな視点を持つことができた」「自社の社員だけでは絶対に出なかったアイデアが生まれた」と、非常に高い評価をいただきました。この成果を受け、共創ワークショップを続けていくことになったのです。
2020年以降はコロナ禍もありましたが、オンラインで実施したり、対面とオンラインとのハイブリッドにしたりして、10社以上のお客様との取り組みが広がっています。経営陣の方々からの評価が高く、スポットでの実施のみならず継続につながっているお客様もいらっしゃいます。東海エレクトロニクス様とは今年で7回目、セブン銀行様、りそな銀行様も複数回実施しています。

お客様のニーズに合わせた共創WSを10社以上と実施
藤原千村さんがおっしゃっていたように、日本企業はイノベーションに困難を抱えています。世の中には色々なモノやサービスが既にあふれており、新しいことを見つけてビジネスとして発展させていくことはなかなか難しいです。ここが、日本企業の経営者が頭を抱える問題でした。それに対して、OKIのIMSは世の中視点・顧客視点から始めるため、共創ワークショップでも可能性のあるアイデアが出現していくのですね。この取り組みを、1社だけではなく複数の企業と共創して実施していくことは、非常に重要だと思っています。課題感を抱えていてもなかなか踏み切れなかったりする企業も多いはずですよね。初回の共創は成功だと思いますが、その後も共創ワークショップはスムーズに進められたのでしょうか。
千村実は最初から順風満帆、というわけではありませんでした。ファーストカスタマーに近い企業様は、やはり非常に意欲的で協力をしていただいたからこそ、うまくいったのだと思います。しかし共創ワークショップは、私が一方的に講義をするようなものではなく「共創」していくものですから、相手の企業様にも人を出していただいたり、準備をしていただいたりと、負荷がかかるものでもあります。そのため、お客様と話を進めていくと、「総論賛成なのだけど、これだけの負荷をかけて、どんなアウトプットが得られますか?」という声をいただくこともありました。また、OKIの事業部門の中でも「これでOKIの製品が売れるようになるのか」など、すぐに成果が出ることを求めるような声があったことも事実です。実際に参加する人も、「すぐ事業化につながるような素晴らしいアイデアを出さねばならないのではないか」と、必要以上に構えてしまうこともありました。そうして停滞したケースは、共創ワークショップを始めた時もそうですが、今でもあります。
藤原なるほど、実施する側の意識を変えることはもちろん、参加する人の心理的なハードルを下げることも必要ですね。実際には、どのような対応をしているのでしょうか。
千村お客様の課題認識や参加する人の状況によって、臨機応変に対応するようにしています。大きく2つのコースを設けています。1つは、大きなテーマについて3カ月ほどの期間、ある程度の負荷をかけて実施するコースです。これは、お互いの企業の課題や技術などについて理解をし合った上で、ワークショップを複数回実施、最後に発表会を行うという内容になっています。
もう1つは、1日コースです。まずはアイデアだけを出して、いいアイデアが出たら別の機会に行おうということで、まずは1日やってみるのです。「1度アイデアを出してみて、良かったら次に進めよう」となれば、実施する方もそれほど負荷はかかりませんし、参加する方も必要以上に身構えずにいられるようになったと思います。これも3カ月とか1日にとらわれずに3日コースにしたりと、お客様によって柔軟に対応しています。だからこそ、共創ワークショップは2019年の開始から、どんどん発展して続いているのだと思います。
短期間での成果を求めるのではなく、まず課題認識から始める
藤原共創ワークショップは、まさにIMSを共通言語としてイノベーションを創出していく取り組みとして、多くの企業に評価していただいているのですね。今の時代、すぐに商品化や事業化ができるわけではありません。だからこそ、千村さんが実施している共創ワークショップのように、時間がかかっても課題の認識をして解像度を上げて、そこに対するアプローチを何度も実施して試行錯誤をしていかない限り、ビジネスにしていくことはできないでしょう。これをまずは経営陣に理解していただけると、イノベーションは加速するはずだと考えています。
千村そうですね。やはり経営陣との意識や目的がずれてしまうと、共創ワークショップもうまくいきません。実際に3カ月コースで、最後の発表会まで進んだにもかかわらず、「いつ商品ができるのか」、「どれだけ売れるか」という短絡的な質問が出たことがありました。これは、ともすると時間を割いて一生懸命アイデアを磨きこんできた参加者たちの意欲をそぎかねない事態です。だからこそ、共創ワークショップを実施する時には、最初に実施する目的をしっかり伝えると共に、「すぐに商品化や事業化をするものではない」ことを共通認識として形成するようにしています。そして実施していく中で、「世の中の視点でみると、当社はこういう取り組みができていない」「こういう教育が不足している」といったことが見えてくるのです。
藤原イノベーションが必要だということは、経営者もわかっているはずです。過去の成功体験にとらわれずに、現場にある程度の裁量を与えながら、数年スパンで新しいことの芽が出るのを我慢してみていくことも必要です。今、その我慢ができずに短期的な成果だけを求める企業は、今後淘汰されていくという強い危機感があります。だからこそ、イノベーション教育を今後もOKIの社内でやり続けますし、今後はさらにここを発展させて、OKIのひとつの事業として立ち上げようとしています。千村さんはどう考えていますか?
千村共創ワークショップを実施する中で、お客様から様々なご要望をいただきます。IMSをどう取り入れればいいのか、新しいアイデアを出す時のテーマ設定はどうするのか、「Yume Proチャレンジ」のようなアイデアコンテストをやりたいが長続きしない、アセスメントや教育はどうすればいいのかなど、イノベーションに取り組む企業は、多くの悩みを抱えています。それは、OKIがこれまで向き合ってきた悩みと同じです。だからこそ、OKIが伴走してその経験から得たことを提供していくことが、OKIのみならず世の中のためになると考えています。
IMSを共通言語としたプラットフォームの創出へ
藤原今後、OKIとして新たな事業として立ち上げる予定の「IMSサポートビジネス」は、OKIのためという側面も当然ありますが、それだけではなく日本企業の競争力を高めるカルチャー変革の一助になると考えています。私自身もこれまでのように外部講演や記事の発信をしながらアピールしていきますが、OKIが先陣を切ってイノベーションに取り組み、失敗しながら積み上げてきているものを、早く世の中の企業にも伝えて、一緒にいいモノをつくっていけたらいいですね。
将来的な話をすると、この輪を広げて、新しいイノベーションプラットフォームをつくっていきたいと考えています。「国内発のIMSベースのプラットフォーム」として、IMSを共通言語として共に新しい事業を興していこうというものです。そして産官学連携のコンソーシアムをつくり、運営できるようにしていきたいと思っています。千村さんのお考えも聞かせてください。

千村そうですね。OKI単体ではできないことがあるため、こうした産官学の連携で仲間を集めていけば、グローバルで拡大していくことができると思います。これまでOKIがイノベーション活動を進めてきた視点が軸ですが、IMSを共通言語としたプラットフォームをつくっていくという構想は素晴らしいですね。
こうして、自社の中で閉じずにオープンなプラットフォームをつくっていくことに対して「OKIにそんなことができるのか」という懐疑的な声もありますが、実際にOKIがこれまでやってきたことだと思っています。時代が違いますが、私が関わってきたVoIP(Voice over IP)システムの開発、そして標準化は、まさに自社に閉じずに技術をオープンにして、市場を巻き込んで大きくなっていきました。ですから「Yume Pro」も、今はドメスティックな製造業の一部でのIMSかもしれませんが、きっとできると自信を持っています。
藤原これは、日本企業/製造業のカルチャーを変える取り組みです。IMSの仕組みをただ提供するのではなく、デザイン思考のツールとして使うのではなく、伴走しながら産官学を巻き込んで一緒につくっていくものです。OKIが実践の中でたくさんしてきた失敗も踏まえながら、多くの企業と一緒に広げていきたいですね。
千村さん、本日はありがとうございました!
(2024年7月26日、OKI執行役員CINO、CDO兼イノベーション事業開発センター長 藤原 雄彦)







