『CINO ism Vol.51』
Yume Proチャレンジ2022大賞受賞
~OKIの強みを活かした「ブルーカーボン」プロジェクト~
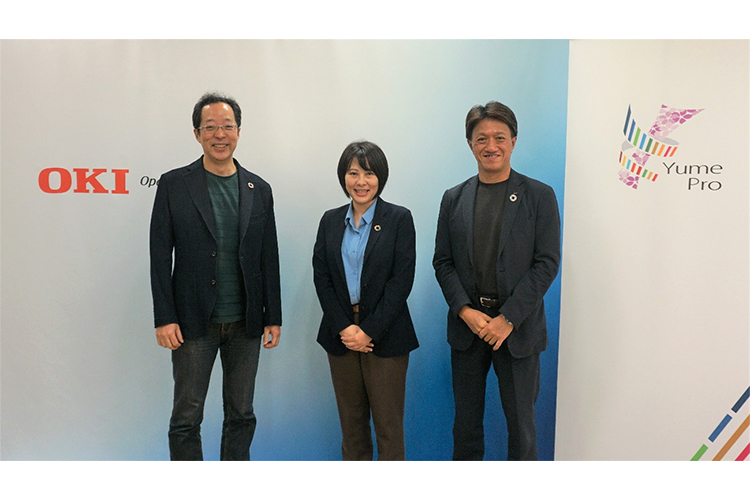
イノベーション事業開発センター 企画室 鈴木(中央)、同 企画室 福永(左)
最新記事
OKIが展開する全員参加型イノベーション「Yume Pro」は現在、具体的な成果を生み出す「実践モード」となっています。
イノベーション実践の場の提供と新規事業の創出のために実施している社内ビジネスコンテストが、「Yume Proチャレンジ」です。開始当初は37件だった応募数は年々右肩上がりで、開始5年で300件を超えました。今回のCINO ismでは、2022年度の大賞を受賞した「ブルーカーボン市場における高精度高品質な藻場計測の実現」の起案者であるイノベーション事業開発センター 鈴木さんと、事務局として支援を行うイノベーション事業開発センター 福永シニアプロフェッショナルを迎え、話を聞きました。
脱炭素社会実現に必要な事業だと考え、Yume Proチャレンジに応募
藤原今日はYume Proチャレンジ2022大賞受賞までの歩みや、事務局の支援体制、そしてこれからの展望について聞いていきます。最初に、大賞を受賞した「ブルーカーボン市場における高精度高品質な藻場計測の実現」について、簡単に説明をお願いします。
鈴木近年、脱炭素社会に向けて様々な取り組みが進んでいます。また、環境への関心の高まりにより、磯焼けも大きな課題となっています。そうした社会課題解決のひとつの手段として注目されているのが「ブルーカーボン」です。これは海洋生物によって吸収・貯留される炭素のことで地球温暖化に貢献するのはもちろん、海の豊かさを守るという観点で注目されています。ブルーカーボンは近年クレジット化されているのですが、藻場の計測をダイバーによる目視確認で行っているため、工数やコストがかさんでしまうという課題がありました。その課題を、OKIの音響技術で解決するというアイデアです。
具体的には、OKIの音響ソーナーにより、藻場をマップ化したり、CO2吸収量を換算したりして、情報を整理していきます。それにより、低コストでの計測が実現できると考えています。まずは藻場計測からスタートしますが、将来は海の見える化を通したエッジプラットフォーム事業をはじめ、環境問題や温暖化対策に事業を展開し、次世代に豊かな海を残すことを目指して活動を続けていきます。
藤原私も審査を行う中で、グリーントランスフォーメーション(GX)に通じる事業アイデアということで、非常に期待できると感じました。鈴木さんは業務で脱炭素事業の創出に携わっていることもあり、ブルーカーボンに興味があったのだろうと思いますが、まずは、Yume Proチャレンジに応募してみようと思ったきっかけを教えてください。
鈴木1年くらい前から記事を読んだりして、何かできるかもしれないとは考えていました。OKIの中で、DX事業についてはイノベーション事業開発センター(以下IBC)の中でも、他の事業部でも積極的に推進されています。しかし、GXという観点では、まだそれほど多くはないと感じていました。だからこそ、そこに一手を打たなければならないという想いが芽生えたのです。その想いを実践する場として、Yume Proチャレンジは最適だと考えて応募しました。
OKIグループ横断で仲間集めて提案が実現
藤原素晴らしいきっかけですね。応募する前に、誰かに相談したのでしょうか。
鈴木当時の上司に相談しました。OKIは組織全体でイノベーションの機運が高まっています。とくにイノベーション事業開発センターでは、ビジネスの種を如何に育てていくのかを常に考えている組織ですから、何かあれば自然と上司や周囲の人に相談する文化があります。
藤原Yume Proチャレンジでは、提案アイデア1件1件に加速支援者が伴走し、一緒にアイデアを磨き上げていきます。鈴木さんのアイデアには、どのような加速支援者が付きましたか?
鈴木事務局に相談したところ、OKIの海洋事業の専門家である特機システム事業部の人を付けてもらえました。私の知らない世界を知っている方からのアドバイスや視点は非常に心強いです。
藤原すごく良い人選ですね。事務局は各アイデアと加速支援者をマッチングする役割も担っています。「この領域ならこの加速支援者が最適だ」と、社内から素早く人選していくのですよね。
福永そうですね。どの加速支援者を付けるのかは、事務局内で議論をして、提案されたテーマの分野に詳しい人や、提案者とは異なる観点を持つ人を選ぶようにしています。
藤原チームを組んでエントリーをしていたと思いますが、その仲間はどのように集めたのですか?
鈴木アイデアを登録する前に、Yume Proチャレンジ登録システムで「ブルーカーボン」と検索してみたところ、他にもブルーカーボンに関連するアイデアを登録していた人が見つかりました。それは海洋領域に特化したOKIコムエコーズ(以下OCE)に所属する2人でした。そこですぐに連絡を取ったのです。OCEの2人も「環境のために何かしなければ」という想いがあったことから、一緒に取り組むことにしました。
藤原IBCから鈴木さんと上司が、特機システム事業部から加速支援者が、OCEから同じ志を持つ2人が集まり、OKIグループ横断型のプロジェクトが組成されたということですね。素晴らしい仲間集めのやり方だと思います。

OKIの強みを活かした提案であることはもちろん、想いの強さが大賞を引き寄せた
藤原次に、応募から最終審査までどのような過程を経たのかを聞いていきます。エントリーをしてから、どんどんアイデアの解像度を上げていったかと思いますが、具体的にどのような活動をしましたか?
鈴木世の中にある資料や書籍などに目を通すことだけではなく、ブルーカーボンの勉強会に出席したりして知見を広げました。そして関連する活動をしている会社や、お客様になりそうな会社にもアポイントを取って、とにかくお話を聞きに行ったのです。その過程で、加速支援者にも関連企業を紹介してもらいました。
藤原加速支援者の支援を得ながら、顧客の生の声を聞きに行ったんですね。まずは一次審査を通過したわけですが、その時はどう感じましたか?
鈴木審査を通過することも当然意識しましたが、それよりも私自身のベストを尽くすこと、自分の提案の質を上げることを強く意識していました。審査結果を聞くまではドキドキしていたのですが通過と聞かされた時はメンバーの方と一緒に喜び、「これで活動を続けることができる」と、ホッとしました。
藤原最終審査に近づくと、アイデアの質はさらに高まります。どのようなことを重視しましたか?
鈴木チーム全員で相談をしながら提案の解像度を上げていきました。そして、わかりやすく相手に伝えることにもこだわりました。最終プレゼンでも、想いを伝えること、自分のベストを尽くすことしか考えていませんでした。
藤原最終プレゼンで、鈴木さんの想いの強さは確かに誰よりも伝わってきました。審査員一同圧倒されましたよ。もちろん、提案の質が高いことは大前提です。しかし、やはり事業としてやっていくには、起案者の想いの強さが本当に大切ですからね。
鈴木「今年を逃したら、来年はないかもしれない」という危機感もありました。こうした活動は、タイミングや縁も大切だと思います。だから想いが先走ってしまったこともありますが、自分でやりたいと言ったことは責任をもって進めなければならないと思っています。
裾野を広げながら、質も高めていく。事務局が果たす重要な役割
藤原続いて、事務局の福永さんにも話を聞いていきます。5年前は40件弱のエントリー数だったYume Proチャレンジも、最近では300件を超えるほどになりました。そこには事務局の努力があったと思いますが、応募促進も含めてどのような支援をしているのでしょうか。
福永イノベーション推進活動を進めているOKIには、アイデアを持っている人がたくさんいます。ただ、なんとなくモヤモヤと考えているけれど、Yume Proチャレンジに応募するほどではないという段階の人が多いことも事実です。そこで、事務局としてはモヤモヤしている段階の人の壁打ち相手となってアイデアを形にしてもらうような活動をしています。さらに、起案してもらったアイデアを「ビジネスモデルキャンバス(BMC)」で整理していくためのサポートも初期段階で行っています。そしてある程度BMCが描けた段階で、伴走者として付けるのが、先ほど鈴木さんの話にも出てきた加速支援者です。その後は、それぞれの加速支援者に各プロジェクトの支援を任せていきます。
藤原応募段階での質を上げていくことはもちろんですが、数百のアイデアから筋のいいものを見つけ出していくことも大切な役割だと思いますが、どのようなことに気を付けていますか?
福永方向感としては2つあります。1つは、「Yume Pro」のプロセスへの理解を全社に広めたいという目的があるため、できるだけ多くの社員にYume Proチャレンジに参加して欲しいという想いです。もう1つは、トップラインを上げるために、その中でも特に事業として可能性の高そうな40~50件のレベルアップをしていくということです。
藤原Yume Proチャレンジが始まって5年、事務局側もスキルが相当上がっているのではないでしょうか。BMCを何件も見ていると、見方が分かってきますよね。そして社外からも、新規事業家の守屋実さんにメンターとして強力なバックアップをいただいたき、さらにスキルアップをしています。応募者だけではなく、事務局や加速支援者といった支援者サイドのレベルも上がっているんです。つまりOKIが全員参加型イノベーションへの道をしっかりと歩んでいるということだと思います。
福永そうですね。私自身、全体的にレベルアップしていると実感しています。

「アイデアを独りにしない」OKIのイノベーション支援体制
藤原他の企業の方とお話をしていると、「社内ビジネスコンテストは、一般的に回数を経るごとに応募数も目減りしていく。OKIのように飛躍的に増えていくケースは珍しい」と言っていただくことがよくあります。福永さんは、その理由をどう考えますか?
福永ひとつは、3年目から設けている加速支援者の存在だと思います。先ほど話したように、OKIにはアイデアを持っている人はたくさんいます。しかし以前は、Yume Proチャレンジの応募要件にまで引き上げられず応募を見送る人、あるいは応募したものの進め方が分からず放置してしまう人、というケースが散見されました。そういった人たちも、少し手助けするだけで走り始めるんです。やはり加速支援者の存在は大きいですね。そうした活動の積み重ねで、社内の意識が変わってきていると感じます。
藤原確かに、最初は「新しいことはイノベーション組織の人たちがやるものだ」という思い込みがありましたね。でも、部門に関係なく新しいアイデアを持っている人って、たくさんいます。そういう人たちを事務局が支援する「アイデアを独りにしない」体制、それをOKIは作っているのです。
福永「アイデアを独りにしない」という観点では、Yume Proチャレンジの応募要件に「必ずVOCを取ってから応募するようにしてください」としていることも大きいと思います。
藤原確かに、この条件を入れたことは大きいですね。応募段階でVOCを取っているという条件は珍しいですし、見方によっては厳しいと思われるかもしれません。だけど、自分のアイデアを使ってくれそうな人の反応を聞くことは、一人で悶々と考えるより遥かにアイデアがブラッシュアップされ、やる気も加速されるはずです。このハードルを課したことによって、みんな苦労しながらもお客様の声を聞くことが習慣になってきましたよね。
鈴木確かに、営業経験のない私にとってはハードルの高い条件であったことは確かです。しかし本当にニーズがあるのかを確かめる機会になりますし、お客様が「いいね」と乗ってくださって次のアポもいただけたら、もう前に進まざるを得ません。それもアイデアを磨いていくための追い風になりました。
福永事業部ごとにイノベーションの取り組みが発生していることも、私たち事務局にとっては嬉しいことです。旧コンポーネント&プラットフォーム事業部の開発本部では、新規技術発掘プロジェクトとして、木曜日の午前中は既存業務に手を付けず、新しいアイデアを生み出すための時間にしていました。そこから生まれたアイデアが、Yume Proチャレンジで上位進出しているケースが多いですね。新しいアイデアはあっても、現業が忙しくてなかなか時間が取れないということも多いですから、「この時間は新規事業を考える」という機会を組織として設けられると、現場としてはやりやすいと思います。
藤原そうした施策を打ったところからは、成果も上がってくるということですね。また、2023年度から、人事施策としても管理職の目標管理シートに「イノベーション」の項目が入りました。イノベーションに時間を割くという意識が、経営層から各事業部、そして人事施策にまで浸透してきています。
海を起点として、様々な価値を創出する事業に育てていきたい
藤原最後に、鈴木さんに今後のビジョンを聞いていきます。これからブルーカーボンのプロジェクトを進めていくにあたり、どのような課題を感じていますか?
鈴木私は研究開発部門出身で、よりよい技術をつくることに注力してきました。しかし営業経験も事業立ち上げ経験もなく、お客様が何を求めているのかも掴みにくいですし、事業を立ち上げるために何が必要なのかも手探りの状態です。わからないことだらけというところが課題ですね。
藤原その状況を、どう突破しますか?
鈴木わからないからこそ、新しいアイデアを出せるという面もあると思います。その強みを活かしつつ、加速支援者や事業について詳しい人に相談をしたり、ブルーカーボンに関係ありそうなところにヒアリングしにいったり、とにかく足を止めないように前進していきます。
藤原全員参加型イノベーションを推進するOKIだからこそ、鈴木さんのように事業立ち上げ経験のない人が大賞をとることもあります。その時に、「何から手を付けていいのかわからない」と動けなくなってしまうと、せっかくのアイデアが減速しかねません。OKIにはイノベーションを支援する仕組みがありますから、周囲の力を借りながら進んでいって欲しいですね。大賞を受賞したことにより、協力者もかなり増えましたよね。
鈴木そうですね。大賞を受賞すれば全社に認知が広がりますから、様々な観点からアドバイスをいただける環境になりました。それ自体は喜ばしいことですが、関係者が増えるとコミュニケーションコストがかかることも事実です。そこはプロジェクトオーナーとして解決していかなければならない課題ですね。
藤原今後のビジネス展開としては、どのようなことを考えていますか?
鈴木数年以内に、「藻場計測」について具体的なソリューションをリリースしたいと考えています。その先に、水産業の支援などさらなる事業の広がりを見据えています。藻場だけではなく藻場に関連する新たな価値の創造や、海の中の見える化など、海を起点として経済活動にまで発展させていきたいですね。
藤原藻場だけではなく海洋生物の保全にも広げていくとなると、それ以外の複数の業務でセンシングを行って、海洋領域のプラットフォームに育てていくことになります。これはまさに、OKIが掲げるエッジプラットフォームです。点から面へ、そしてグローバル展開も目指して欲しいですね。これからも期待しています!

(2023年11月17日、OKI執行役員 CINO兼イノベーション事業開発担当 藤原 雄彦)







