『CINO ism Vol.49』
実践モードを突き進む全員参加型イノベーション
―特機システム事業部―
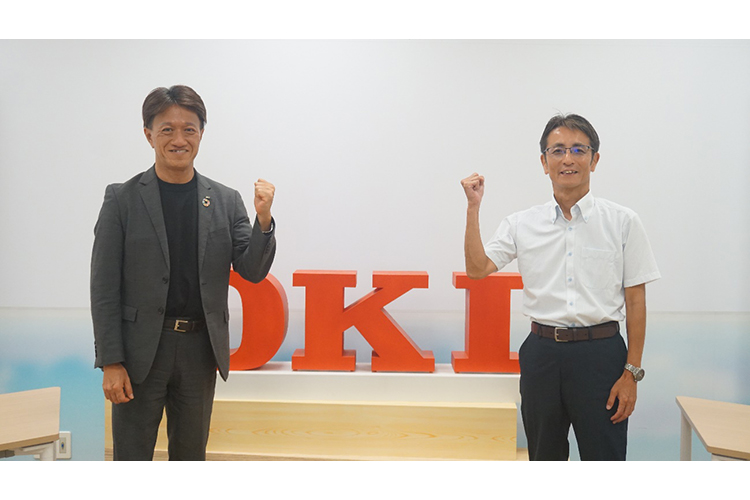
特機システム事業部 事業企画部 田辺部門長(右)
最新記事
OKIが展開する全員参加型イノベーション「Yume Pro」は現在、具体的な成果を生み出す「実践モード」となっています。今回は、長きにわたりOKIが培ってきた海洋分野における水中音響センシング技術を活かした海洋ビジネスに関して、OKIの海洋ビジネスの歴史や技術的な強み、その強みを活かした新規事業の可能性について、藤原CINOと特機システム事業部 田辺 事業企画部長が語りました。
OKIの必然として海洋がある――歴史と強み
藤原OKIは「中期経営計画2025」において、将来事業の注力領域のひとつに「海洋」をあげています。取り組みを加速させる中で、新固定式計測バージ「SEATEC NEO」も10月から稼働開始しましたね。
海洋ビジネスはソーナーなどの既存製品だけでなく、民間適用も含めた新規事業も検討しています。この辺りを今回は田辺さんにお話を聞いていきたいと思います。
まず、簡単に特機システム事業部の事業について紹介をお願いします。
田辺特機システム事業部は、防衛、民航ビジネス、海洋の事業領域で展開しています。まず防衛については、水中音響システムや空中音響装置、防衛情報通信サービスを海上自衛隊様に提供しています。そして航空特機として陸上・海上・航空自衛隊様向けに、コックピットディスプレイなどを納めています。
民航ビジネスでは、タレス・アビオニクス社(フランスの大手航空宇宙電子機器メーカー)と協同開発したフライトデッキ液晶ディスプレイを、エアバス社のA320A350という最新機に搭載しています。
そして海洋は、中期経営計画2025での注力領域として、これまで防衛事業などで培った技術を展開すべく、新規事業の創出に取り組んでいるところです。
藤原「OKIの必然として海洋がある」と言われるほど、海洋はOKIの強みを活かせる事業領域です。事実、OKIは海洋センシングなど、長きにわたり海洋に関する技術を活かした事業を展開してきました。そこで改めて、OKIの海洋の強み、歴史や技術について教えてください。
田辺1936年に海軍技術研究所より水中聴音を依頼されたことから、OKIの海洋ビジネスは始まっています。そこから、潜水艦や水上艦向けのソーナー、そしてソノブイを防衛省に納めるなど、防衛事業を中心に進めてきました。しかし、防衛事業はプレイヤーが限られています。そこで、2021年にディフェンスシステム事業部から特機システム事業部に部署名を変更して、私たちが長年にわたり防衛事業で培ってきた水中音響技術を民間市場へ拡大すべく今年度から本格スタートしたのが、現在の海洋事業です。
技術的な強みは、水中の音の可視化技術です。水中の遠距離に存在する物体が出す微弱な音を検出、分析し、その物体がどのようなものか、どこにいるのか、どういう運動をしているかを把握することができます。今後、このような水中音響技術を活用したビジネスを創出していきたいと考えています。
藤原私も一時期、海洋事業に携わった経験がありますが、まさに今お話ししたように、OKIの強みである海洋IoTを民間に展開していくことに期待を寄せています。ところで、水中音響技術センシング技術は、他社にもある技術なのでしょうか。その中で、OKIの特徴も教えてください。
田辺OKIだけの技術ではなく、他社も取り組んでいます。ただ、それぞれの企業でアプローチが異なります。OKIは遠くに存在する物体が出す音を捉えて分析するパッシブ音響技術で国内トップレベルですが、ある企業では自ら水中で音を出し、物体から反射してきた音を捉えて分析するアクティブ音響技術を用いています。それぞれ良さがありますが、アクティブ音響の場合は自ら出した音が水中生物に影響を与えてしまったり、軍事であれば音を出すことで相手に位置が分かってしまったりするため、将来的にはどちらかというと水中ではパッシブ音響が主流になると考えています。
水中音響センシング技術を発揮できるフィールド
藤原2020年、OKIは水中音響センシング技術を活用して、密漁船や水中の不振なダイバーを監視・検知する「密漁監視ソリューション」を開発しました。もともとは、北海道でナマコの密漁による損害が深刻となったことから相談を受け、取り組んだものです。これはSDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」にもつながるもので、総務省にも興味を持っていただき、矢口港湾建設株式会社、北海道増毛郡増毛町とともに実証実験を行いました。その取り組みの際、OKIは民間に適用可能な海洋IoTをもっと展開できるのではないかと思いましたが、田辺さんはどういう印象を持ちましたか?
田辺民間向けの製品を開発するのは初めての事例で、私たちも新鮮に感じました。そのことが起点となり、私たちの成長戦略を具体化させることになったのです。OKIの得意な水中音響技術を駆使した素晴らしい事例として印象に残っています。
藤原まさに水中音響センシング技術をうまく活用し、社会課題にマッチさせた海洋IoTの好事例です。OKIの強みは、リアルタイム制御と、高品位ネットワーク、そしてハードを作りこめることです。海洋は、この強みを存分に活かせる領域だと思います。
実は中期経営計画2025を考える中で、海洋ビジネスの次のステップとして、水中音響技術の市場をさらに拡大させていけるのではないかと思いました。OKIが手掛ける洋上風力への展開や、漁業など食の安全にかかわる事業など、様々な可能性がありますが、田辺さんはどんなことを考えていますか?
田辺OKIの強みである水中音響センシング技術を活かせるフィールドは、海の中のセンシングだと思います。たとえば、漁業や養殖には、海洋生物の分布を知りたいというセンシングのニーズがあります。海洋生物は鳴き声を出すため、OKIの技術を使ってその音を捉えて調べることが可能です。それは魚を獲るためではなく、海洋生物を守るためでもあります。
洋上風力発電は、その特性上なかなか人が常駐して水上あるいは水中の構造物を点検することができません。そのため、OKIの水中音響センシング技術を活用すれば人が出向かずとも異常を検知できるようになります。
また、たとえば海底ケーブルをセンサーとして活用することで、より広範囲に海洋生物や海洋資源の状況を調べたいというニーズが出てくるのではないかと予測しています。
藤原どのような顧客を想定していますか?
田辺洋上風力発電の場合は、メンテナンスの効率化という観点から、運営する電力会社様になります。
また、漁業や海洋生物の生態調査においては、国をターゲットに想定しています。国として、日本周辺の海洋生物の状態を健全な形で維持する必要があります。これはSDGsの観点でもそうですが、安全保障の観点でも漁業の強化を国策として進めていくためです。また、海洋事業は現状、研究開発が中心なのですが、10年後には国が投資をして技術を社会実装させるビジネスが生まれると考えています。OKIとして、ぜひそこに取り組んでいきたいですね。

海洋プラットフォームの可能性
藤原最近では、OKIの社内ビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」で、ブルーカーボン(※1)のプロジェクトが大賞を受賞しました。これはぜひ、田辺さんの特機システム事業部との連携で将来事業のひとつとして実現させたいです。CO2削減の観点で海洋生物に注目されつつあるため、そういった領域にも水中音響センシングの活用を期待しています。もちろん、技術的な課題もあるかもしれませんが、可能性を探っていきたいですね。
田辺様々な可能性を探っていけると思いますので、特機システム事業部の経験もあわせて貢献できればと思っています。
ブルーエコノミーを含めた海洋市場は、2030年までに500兆円に成長するという算出データもあります。それくらい巨大かつ将来性のある成長市場ですから、私たちも積極的に取り組んでるところです。
藤原様々な形で水中音響センシングなどの技術を活用しながらシーンを見極めて展開していく中で、データが蓄積されていきますよね。それを海洋データプラットフォームとして2031年に向けて整備している最中かと思います。
OKIは中期経営計画2025で、エッジプラットフォームを掲げています。これまで培ったエッジ技術やノウハウを活用してチャレンジする注力領域のひとつが、海洋です。エッジデバイスからの複数のデータや気象情報などをプラットフォーム化していけば、価値を最大化していけると思いますが、田辺さんはどう考えますか?
田辺ポイントは、私たちが持つ技術をどのように活用していくかということです。たとえば洋上風力発電であれば、洋上の建造物やAUV(自律型無人潜水機)といったエッジに私たちの技術が適用されることで、海中の課題を広く解決できると考えています。
データ解析の部分はまさにおっしゃる通りで、海洋の情報だけではなく気象データや漁獲高のデータなどと相関分析などを行うことができれば、新しい価値が見えてくるでしょう。それこそ、OKIにしかできない海洋ビジネスが創出できるはずです。
コア技術で培ったパートナーシップをベースに、海洋ビジネスもグローバル展開を
藤原OKIでは、海外事業リスタートとして、グローバル事業推進本部も新設して取り組んでいます。海洋の領域では、グローバル展開をどう考えているのでしょうか。
田辺防衛においては、海外技術をベンチマークはできないため、これまでグローバル展開は視野に入れていませんでした。しかし民間への展開ということであれば海外進出のチャンスも大きく広がります。また、政府が海洋領域で日本としてのプラットフォームを構築しようという動きがあります。そこでどのような仕様や技術が必要なのかを精査していく段階で、OKIの技術が標準仕様として採用されれば、日本として海外に製品を売ることができると考えます。
また、私たち特機システム事業部は、民航ビジネスで海外メーカーとお付き合いがあります。そういったところにOKIの技術を紹介して、可能性を探りたいですね。他にもディストリビューターなど部品を扱っている会社に対して提案をすることで、グローバルなビジネスを広く開拓するチャンスがあると考えます。
藤原ティーチャーカスタマーなど、良きパートナー企業を見つけて、そこと話をしながらビジネスを進めていけるといいですよね。また、国やリージョンごとにお困りごとは異なるはずです。現場で起こっている課題をいち早くとらえて、そこにOKIの技術でアプローチしていかなければならないと思います。今は、技術の押し売りだけではモノは売れない世に中ですから。
田辺おっしゃる通りだと思います。自分たちだけの観点でモノづくりをしても、結局は売れないものになりますから、グローバルでの課題を見つけていくことは非常に重要なアプローチですね。
事業部の垣根を越えた横串の連携で、ビジネスの可能性がさらに広がる
藤原新規事業創出に向けた可能性は広がりますが、その際にIMS(イノベーション・マネジメントシステム)を意識していますか?
田辺海洋の成長戦略には、ステップ1から3の段階があります。そのステップ2が技術や製品を充実させていく段階なのですが、そこではIMSのアジャイル開発が重要な位置づけになると思います。時間をかけて作ってもニーズに合わないものができてしまうことも多いですし、ニーズに合うものをスピーディーに生み出してきた経験も、私たちにはほとんどありません。だからこそIMS のルールに則ってアジャイルに回し、新しい製品を充実させていきたいです。
藤原何かアイデアが生まれたら、「こういうところでIMSを活用しよう」「これは既存の仕組みでいこう」と、ミドルマネージャーが振り分けていくことが大事ですね。新しいところはYume Proチャレンジに応募を促したり、事業の中で取り組んだりと、アイデアの特性によって色々な手法が、今のOKIにはあります。そういう手法をどんどん取り入れていってもらえると、新しいことを生み出していけると思います。なにしろ、新しいものは、仮説を立ててもなかなかうまくいかないことが多いですから、アジャイルでやっていくことが必要です。ブルーカーボン領域は、それこそ仮説の山ですし、これから市場を開拓していかなければなりません。これまでのOKIが得意としていた「顧客に言われたものを的確につくる」ことではなく、新しい領域でアジャイルに行ったり来たりを惜しまず進んでいくことが、OKIの文化を変えていくことにつながると思います。
田辺ここ数年で、OKIは随分変わったと体感しています。これまでは縦割りの組織で、私たちの事業部の中だけでビジネスを考えていましたが、Yume Proチャレンジなど新しいアイデアを形にする具体的な手法が出てきて、イノベーション活動がどんどん広がるにしたがって、これまでの縦割りの垣根がかなり取り払われていると感じます。海洋というテーマを特機システム事業部の中だけはなく、様々な部門の人たちが一緒になって考えてくれるようになりました。そうすることで、私たちだけでは思いつかなかったアイデアが生まれたり、「これが民間で必要とされているんだ」という新しい気付きを得たり、そういうことがどんどん増えています。確実に横串で連携する動きも見られますし、事業部の垣根を越えて、多様な視点で見る取り組みが、今後も増えていくのではないかと思います。
藤原素晴らしいですね。1つのテーマに対して横串で連携し、みんなが力を合わせて進んでいく。それこそ、OKIが目指す全員参加型イノベーションの姿です。これからも強い意志を持って、「社会の大丈夫をつくっていく。」ために一緒に頑張りましょう。これからもよろしくお願いします!

※1 ブルーカーボン:藻場や干潟などの海洋生態系に蓄積される炭素のこと。そうした蓄積作用を有する生態系を「ブルーカーボン生態系」といい、CO2吸収源の新しい選択肢として注目されている。
(2023年10月3日、OKI執行役員 CINO兼イノベーション事業開発担当 藤原 雄彦)







