『CINO ism Vol.38』
Yume Proの浸透~実践モードに向けて
―統合営業本部 企画管理部の事例―
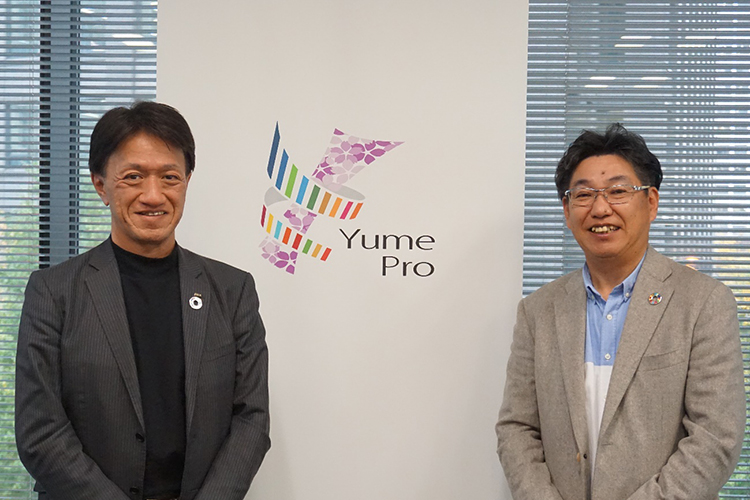
最新記事
今年度の「CINO ism」では、OKIのイノベーション・マネジメントシステム(IMS)「Yume Pro」の浸透~実践モードに向けて、をテーマに、各部門への展開を担う部長/部門長と藤原の対談を続けています。IMSの実践を通じて見えてきた成果や課題について、現場目線のリアルな声を紹介していきます。
今回は、統合営業本部 企画管理部の緑川卓部長との対談です。企画管理部は営業企画や業務管理をはじめ、OKIの営業活動を支える役割を担っています。イノベーション推進センター(IPC)をはじめ、横連携を密にした積極的な活動を行い、近年では、オンラインを活用したプロモーションやイベント開催にも注力し、着実に成果が出始めています。
営業とイノベーション部門の連携は必然だった
藤原私がIPCの前進であるイノベーション推進部の部長に着任した2019年、「営業と一緒に動く」と宣言し、実践してきました。当初は私から強くアプローチしていましたが、営業側も徐々に前向きになり、今では営業から「一緒に提案に行ってほしい」と相談されるようになりました。
緑川さんは現在、企画管理部長として、営業全体の管理部門の責任者ですが、アカウント営業にも長く携わっていました。営業の意識・行動が変わってきた背景・理由をどう見ていますか?
緑川私の感覚では3、4年前から変化が出始め、コロナ禍になり、より顕著になりました。
要因は「世の中の不確実さ」が増したことだと思います。時代の変化に伴い、お客様が「何をやればいいのか」を模索するようになり、我々に対する要求も「これがほしい」といった明確なニーズから、「自分たちはどう変化するのがいいのか、その変化のために有用な提案があるか?」という漠然としたニーズになってきました。それがコロナ禍による環境の激変で、さらに加速しました。
こうしたお客様の変化に直面し、営業の中に「既存の商品だけではマンネリの提案しかできない。新しいことを考えなければ」という危機感が広がったのだと思います。
藤原お客様から「中長期的に何か一緒にやりたい」と言われる機会は確かに増えています。それらに対応するには、潜在的なニーズをお客様と共に掘り起こして価値を創出するIMSの手法、OKIでいえば「Yume Proプロセス」を使わなければなりません。また、中長期の視点でのソリューション検討は、既存事業を抱える部門では対応がきびしいため、営業がIPCと積極的に連携するようになったということですね。
高速回転で仮説を磨くためには営業の力が絶対に必要
藤原今後、OKIとしてイノベーションの実践を加速させるためには「営業のポジションがより重要になってくる」と、私は考えています。
Yume Proプロセスの前段、「コンセプト構築プロセス」では、お客様と議論しながら仮説検証を進めますが、ここでも、お客様と強い繋がりを構築できる営業の力が必須です。また、訪問のタイミングや提案方法など、お客様との接点となる部分は、営業に担ってもらいたいと思っています。
そういった連携によって、仮説を高速回転で磨き上げられるようになります。森社長も、「営業がOKIの技術やソリューションの知識をもっと身に付けて、お客様への初回提案は営業単独で、2回目からIPCと一緒に、というような行動をしてほしい」と話していました。
緑川確かにその通りだと思います。今までは事業ごとの商品やソリューションを勉強しておけばよかったかもしれませんが、これからはグループ会社の技術なども含め、幅広く把握し、お客様から漠然とした問いかけを受けた際にも糸口となりそうな話をパッとできるようになるべきです。決して簡単なことではないのは分かっていますが、少しずつでも前向きな動きが出てくることを期待しています。

プロモーションのデジタル化・オンライン化が一気に加速
藤原プロモーションの活動でも、IPCとの密な連携が進んでいます。社外に向けた積極的な情報発信がOKIとしてのチャンスに繋がりますし、営業にとってもIPCにとっても非常に重要な取り組みです。現在はどういうことに力を入れていますか。
緑川プロモーションにおいては全社連携と合わせて、デジタルコンテンツの拡充や、オンラインの活用が重点施策です。これはコロナ禍によって、デジタルシフトを余儀なくされた背景もあります。
藤原コロナ禍は社会全体にデジタル化、オンライン化の加速をもたらしました。最も印象に残っているのは、リアルから完全オンラインへ切り替えて開催した2020年の「OKIプレミアムフェア」です。営業とIPCが中心となり、本当に苦労して中身を練った結果、市場でも先駆けとなるバーチャルイベントを開催しました。お客様に展示やセミナーを視聴していただけるのか、ネットワークがダウンすることはないか等、初めての試みに課題は山積みでした。結果的には、無事に成功で終えることができましたし、あの経験はOKIとしても大きな財産になりましたね。
緑川私は当時、企画管理部内の営業企画部長として異動してきたタイミングで、イベントの企画・運営に携わりました。何が正しいのか分からずに手探りでしたが、周りとも協力し、努力した甲斐があったなと思います。それは、オンラインを活用したプロモーションを広げていく契機にもなりました。
藤原翌年には、ショールームの活用においても、オンライン化が大きく進みましたね。
緑川はい。まずは東京・虎ノ門の本社オフィス再編に合わせて、従来の「OKIショールーム」を、新たな価値を築く共創のための空間として「OKI Style Square TORANOMON」にリニューアルし、主要拠点である埼玉県蕨市の蕨システムセンター、群馬県高崎市の高崎工場にも同様のコンセプトのスペースを設けました。さらに、各地の支社・支店とのネットワークを整備し、各地域のお客様もStyle Squareや工場のオンライン見学ができるようにしました。
また、今年3月にはWebサイト上にオンラインショールーム「OKI Style Square Virtual」も開設し、さまざまな商品・ソリューションの展示やセミナーをお客様がいつでもご覧いただけるようにしました。これらは随時、コンテンツの拡充やアップデートを行っていきます。
Yume Proを活用した営業部門での成功事例を早く作りたい
藤原緑川さんはIMS構築ワーキンググループ(WG)に営業部門の責任者として参加されています。今年度末にはWGの成果として全社IMS規定および行動手順を記したガイドラインの第1版が発行されますが、どのような期待を持っていますか。
緑川私としては、この規定・手順を使って営業部門での成功事例を早く作りたい、作ってほしいというのが一番の想いです。お客様と手を握って「よかった、うまくいった」と喜び合うような事例が1つでも生まれれば、その経験が周囲へモチベーションとして伝播し、皆が続いていくようになると思います。
藤原IMSを活用した商品はIPCと事業部門の連携で既にいくつかリリースされていますが、新規事業分野での商品創出については、お客様との共創段階であり、商用レベルの成果がまだ出ていません。今年度からの「実践フェーズ」で事業化を加速させる仕組みも構築しているので、営業ともより密に連携して行動する形になっていくでしょう。そうしたところからも成功事例を早く作っていきたいですね。

将来は運用サービスまで含めた商談を獲得できる営業活動を
藤原OKIは今後、全社IMSのもとでイノベーションの実践が加速し、全員参加型イノベーションもより活発になります。そうした中で、営業のあり方、営業活動はどういう形になっていくと思いますか。
緑川既存事業やその延長線の事業も大事にしつつ、将来の柱となる事業として、商品・ソリューションの提供だけにとどまらず、運用サービスも含めて請け負うような案件の獲得が重要だと思っています。いまのOKIの強みはハードウェア、デバイスにあって、これまではモノを作って納めて保守するところまでがビジネスの主軸でした。しかし、制御系のシステムがクラウド上で構築・運用されることが増え、その運用をサポートすることでお客様に「本業に集中できる」という価値を提供できるようになりました。そういったニーズへ柔軟に対応し、新しいビジネスに踏み込んでいくのもイノベーションの1つではないかと思います。
藤原たとえば、注力技術としてIPCで取り組んでいる「高度遠隔運用(REMOWAY)」は、エッジデバイスで集めたデータをクラウドに上げ、遠隔から現場の監視・制御をすることで、労働力不足を解決する仕組みです。OKIとしてはハードやデバイス、SIがビジネスとして真っ先に思い浮かびますが、そのプラットフォーム技術「REMOWAY」により、運用サービスの受託にも繋がる期待と可能性が出てきています。こういった新しいビジネスモデルの展開も営業と強く手を組んで進めていきたいと思います。横展開で市場を広げていくには営業の力が絶対に必要ですからね。
緑川私は、営業は「自転車の前輪」のようなものだと思っています。進むべき道を見定めて舵を取る役目です。そこに後輪となる技術開発や事業が動力、推進力をつけることで、正しい方向へ加速していくことができます。どちらかが主体・主導ということではなく、両輪が揃ってバランスよく機能してこそ、大きな成果を生み出せるのだと思います。
藤原いいですね。それが本当に「一緒に行動する」ということ。他部門からのアウトプットを待っているのではなく、一緒に動いて新しい“価値”をつくっていくことが、社会課題やお客様課題を解決するためには不可欠ですし、それが「社会の大丈夫のつくっていく」ことになります。そのためには、社内における「エコシステム構築」の重要性を正しく認識し、縦割りを崩して横結合を強めていく必要があります。そのことを私は継続して強く推進していきたいと思っています。
(2022年12月23日、OKI執行役員 CINO兼CTO 藤原 雄彦)





