『CINO ism Vol.31』
Yume Proの浸透~実践モードに向けて
―イノベーション推進センター ビジネス推進部の事例―

最新記事
前回までに引き続き、OKIのイノベーション・マネジメントシステム(IMS)「Yume Pro」の浸透~実践モードに向けてをテーマに、各部門への展開を担う部長/部門長と藤原が対談し、IMSの実践を通じて見えてきた成果や課題について現場目線のリアルな声を紹介していきます。
今回は、イノベーション推進センター(IPC)・ビジネス推進部(BID)、青木聡部長との対談です。BIDはオールOKIの技術を活用し、お客様との共創による新規ビジネス開発に取り組んでいる、まさにIMSの実践集団です。当対談ではBIDの現状と課題、これまでの成果や、目指すビジョンについて語り合いました。
[IMSの部内展開]
現場で一番の課題「次にどう動くか」をメンバーと一緒に悩み、考えた
藤原さっそくですが、青木さんは2020年にビジネス推進部(BID)へ異動してきました。それまでの受注開発型ビジネスとはまったく違う仕事の進め方をしている部門に入って、どうでしたか?
青木私は27年間、情報、通信、メカトロと、各事業部門で回路・基板設計を手がけてきました。そこからいきなり新規ビジネス開発に携わることになり、最初はもう手探りで、業務をこなしていくのに一生懸命でした。
2020年度は部内の担当部長として、Yume Proプロセスの入口である「機会の特定」のため、メンバーと一緒に多くのお客様を訪問し、仮説を立ててはお客様をまた訪ねるという活動に明け暮れていました。
藤原すでにIMSを実践している現場に入ってリーダーシップを取るのは大変だったと思いますが、私は当時の青木さんを、「周りと一緒になって進めるという強い意志を持っている」と感じていました。
青木私はとにかく、お客様の話を聞き、メンバーとよく議論し、お客様の課題をどう解決するかを具体化していくことを強く意識していました。
あの頃はメンバーも経験豊富とまでは言えず、現場では「(お客様から話を聞いた)次にどう動くか」で悩んでいたので、私もアイデアを出しながら一緒に試行錯誤していました。当時、メンバーと行動を共にできたことはとてもいい経験でした。振り返ってみれば、私に期待されていた役目は、現場の課題解決のために皆と一緒に考え、前に進めていくことだったのかなとも思います。
藤原仮説に対して明確な回答や意見が得られればよいのですが、抽象的な返事のほうがむしろ多く、だからこそ次の行動をどうするかという悩みも出てきます。そうしたときに、チームリーダーやマネージャーが一緒に考え、加速支援するのは非常に重要です。青木さんのそういう仕事のやり方はメンバーからの信頼も育んでいきましたね。
[IMSの活用状況]
成果の具現化に向けた「ターゲットの絞り込み」へ
藤原2年間のYume Proプロセスの実践を経て、2021年度には「BIDで機会の特定ができてきた」と、私の目には映りました。物流とヘルスケアの2分野で着実な前進が見られましたし、高度遠隔運用もかなり試行錯誤したものの、いい状況になってきていますね。
青木さんは、どのような意識でマネジメントに臨んできましたか?
青木2021年度にIPCの基本方針として「Realize(リアライズ)」=成果の具現化が掲げられました。そこで私は、お客様の課題や価値観をもっと具体化しなければ成果まで辿り着けないと考え、「これまで培ったお客様との関係を大事にしつつ、ターゲットを絞り込む。そのうえで水平展開を考えていく」という方針に切り替えました。
藤原試行錯誤の段階であれば、できるだけ多くのお客様に仮説を持っていき、手応えを探るやり方もよいですが、あるフェーズからは、OKIのビジョンに共感いただけるお客様に絞って話を進めていかないと、なかなか具現化には結びつきません。活動方針の変更は大きなプラスとなりましたね。
聞き手に物語を伝える事業シナリオをつくる
藤原お客様と共創の合意まで進んだ物流、ヘルスケア、高度遠隔運用の3分野に関して、私は青木さんに「事業シナリオを作ってほしい」とお願いしました。新規事業を興す際には、事業規模やビジネススキーム、投資とリターン等々をきちっと数字で示す必要があります。そうしないと経営者にも事業部門にも納得してもらえず、先に進むことができません。
青木さんが試行錯誤して作り上げた事業シナリオは、当時の経営陣にもきちんと説明し、ゴーサインをいただくことができました。あれはとても大きな成果だったと思います。
青木はい。経営陣から「ここまでできているなら、やってみれば」と言っていただけたのは本当に嬉しかったです。
最初に指示を受けたときは、正直なところ「どう作ればいいんだ」と戸惑いました。ですが、藤原さんらがあらかじめ作られていた“事業シナリオを作る際に必要な情報や資料のリスト”があったので、まずはそれらを揃え、さらに「シナリオというのは人に物語を伝えることだ」と考え、集めた情報に自分たちの想いを込めて、分野ごとに20ページほどの資料を物語的にまとめました。皆で力を合わせて事業シナリオを作り上げ、それが評価されたことは、BIDとして非常に大きな手応えを掴んだ気がしました。
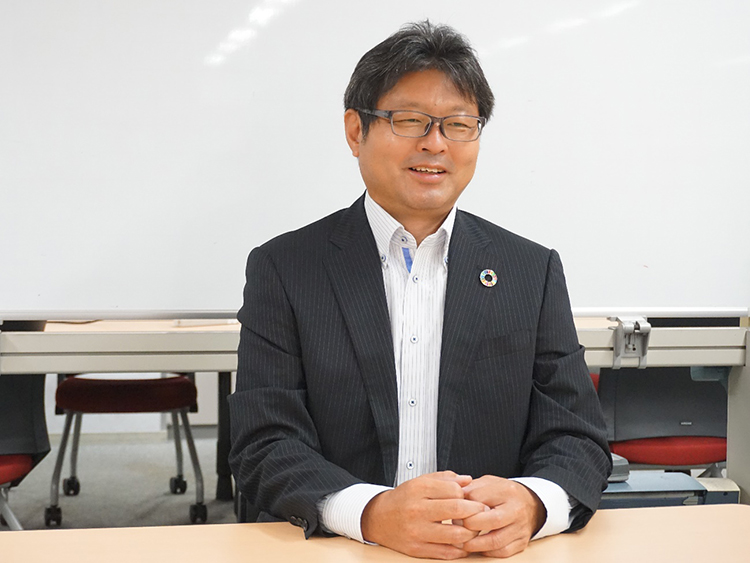
ビジネス開発と研究開発はワンチームが必然
藤原青木さんが異動してきたのはイノベーション推進部と研究開発センターを統合したタイミングでしたが、ヘルスケア分野などはそれ以前から部門の垣根を越えてビジネス開発に取り組んでいました。
ビジネス開発と研究開発が同じ組織になり連携を深めていることについて、青木さんはどのように捉えていますか?
青木お客様の困り事や価値はお客様と話をして明確にしていくものですが、そのソリューションを具現化できるかどうかは研究開発部門にかかっています。我々の仮説も、開発が「この課題は解決できる」と思わなければ、絵に描いた餅です。具現化できないものをお客様に提案するわけにはいきませんから、お互いが一緒になって活動するのは必然だと思います。
お互いの連携はどんどん強くなり、お客様先に一緒に行って話を聞く機会も増え、研究開発の視点でお客様課題を捉えることもできています。BIDと研究開発部門がワンチームでプロジェクトを進めていく形は、もはや絶対的なベースラインだと思っています。
藤原研究開発者も、お客様と話をすることで切迫感やスケジュール感といったものが直に分かります。ビジネス開発担当と一緒に考え、お客様に寄り添って研究開発していくことは必要不可欠です。そういったチームで動くと、「できる・できない」をその場で判断できるので、スピーディに進められるようになります。このスピードを上げることはイノベーションにおいて非常に重要なのです。
営業部門、事業部門も巻き込み連携していく
藤原私は、常々営業部門との連携も重視しています。2019年度にイノベーション推進部長を務めた時から「営業と一緒に動く」と宣言し、実践してきました。新規ビジネスというのは、事業性が見通せないうちは事業部門もなかなか前向きに取り組めないので、「まずは営業と共に行動する」と考えました。今では、営業から「一緒に提案に行こう」と声をかけてもらえるようになりましたね。
青木私も営業部門との連携は大事だと考えています。
物流向けソリューションでは、営業部門が先々の横展開を睨んで、「OKI Innovation World」や「OKIプレミアムフェア」といったイベントに物流関係のお客様を招待する活動を実行してくださり、とても心強く感じています。また、事業部門にも共感をいただき、商品化に向けた活動にも着手しました。さらに、ヘルスケア分野では、営業部長がお客様先に同行訪問してくれるなど、現場での連携が少しづつですが着実に進んでいる実感を持っています。
藤原IPCが見つけたテーマ・案件を営業部門が認識して一緒に行動し、仮説がブラッシュアップされて事業部門も加わったときに、完全なチーム、全員参加型イノベーションができ上がります。そういう仕組みを確立して、大きく広げていきたいですね。
[今後の目標・ビジョン]
「OKIならではの技術をビジネスにどう使うか」を常に考えてほしい
藤原BIDに一番期待していることは、イノベーション実践の牽引役、良いお手本であってほしいということです。
今年度は社長の方針で「実践モード」を掲げ、IMSというプールを「泳ぎ切れるスイマー」を増やしていくことを目指しています。BIDには、願わくはメンバー全員が「泳ぎ切れるスイマー」になってほしいし、青木さんにはそれを見据えたマネジメントをしてほしいと思います。
青木決して簡単なことではないですが、頑張ります。部内では、課題や障壁に直面した時に「ちょっとでもいいから、何か一歩を踏み出そう」と、私を含め皆がよく口にしています。何事も諦めずに、少しずつでも前に進もうというモチベーションで取り組むことが大事だと考えています。
藤原私はIPCの研究開発メンバーに対して、OKIにとっての技術の重要なキーワードは“リアルタイム性”であると言っています。現在注力するAIエッジ、リアルタイムAIがOKIの研究開発の強みです。BIDのメンバーには、世の中の動向にアンテナを張りつつ、「OKIならではの優れた技術をビジネスにどう使うか」を常に意識してほしいと思っています。
青木物流分野でいま取り組んでいるのは、まさにAIを活用したリアルタイムインテリジェンスな物流DXです。ヘルスケア分野でも今後AIをうまく組み込んで、ウェルビーイングに貢献するリアルタイムな仕組みを作っていきたいと考えています。リアルタイムなAIがOKIの強みであることを念頭に置いて、さらに次の新規ビジネス、お客様への新しい提供価値を、研究開発と一緒に見つけていきます。
藤原成果が増えていけば、社内でもイノベーションへの気運がより高まっていきますし、社外に対しては「イノベーション先進企業としてのOKI」をさらに示していくことができます。OKIは必ずそこまで到達できると思っていますので、一歩ずつ前進していきましょう。
(2022年8月29日、OKI執行役員 CINO兼CTO 藤原 雄彦)





