『CINO ism Vol.30』
Yume Proの浸透~実践モードに向けて
―イノベーション推進センター UX技術研究開発部の事例―
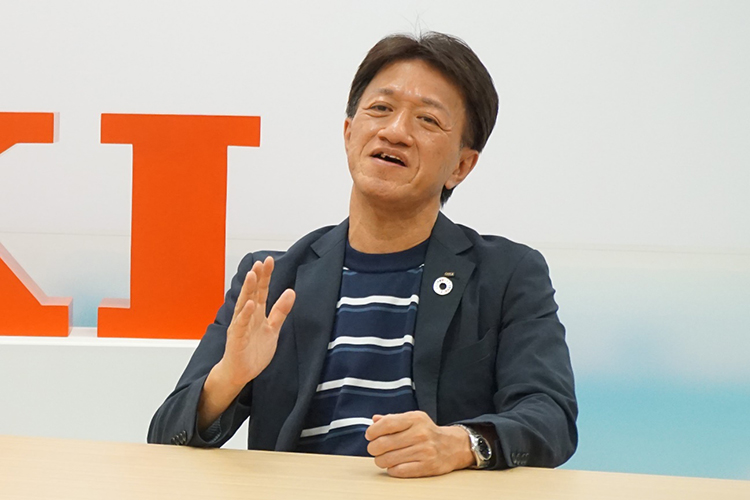
最新記事
前回までに引き続き、OKIのイノベーション・マネジメントシステム(IMS)「Yume Pro」の浸透~実践モードに向けてをテーマに、各部門への展開を担う部長/部門長と藤原が対談し、IMSの実践を通じて見えてきた成果や課題について現場目線のリアルな声を紹介していきます。
今回は、イノベーション推進センター(IPC)・UX技術研究開発部(UXD)の塚本明利部長との対談です。UXDはAIエッジを強化する「ユーザー・エクスペリエンス(UX)領域」を手がけ、OKIと社会をつなぐソリューションの開発に取り組んでいます。IMSの実践における現状と課題、今後の目標について語り合いました。
[IMSの部内展開]
デザイン思考でYume Proの実践を加速
藤原UXDの研究開発は、エンドユーザーへのきめ細かなアプローチが必要不可欠な領域です。提供先が企業であっても、その先のエンドユーザーを常に意識し、現場の困り事やニーズを捉え、BtoBでの提供価値を作り出さなければなりません。
このようなやり方は、まさにIMSのコアである“デザイン思考”です。UXDはYume Proへの親和性も高かったと言えますね。
塚本UXDは従来から、人とシステムとの接点に関わる技術を開発してきたので、エンドユーザーの状況を正しく把握すること大事だという認識が部内に根付いていました。また、デザイン思考に関する知見、実践手法を身に付けているメンバーもおり、その手法を使って具体的な研究開発やOKI製品への応用展開を行っていました。もともと「現場の課題を明確にして進めていこう」という考え方がベースにあったので、Yume Proもスムーズに展開できました。
長年の事業部経験を研究開発のマネジメントに活かす
塚本私は2019年度までソリューションシステム事業本部に所属しており、2020年4月にIPCが発足したタイミングでUXDの部長となりました。
先に話した通りYume Proの展開はスムーズだったのですが、メンバーが新規事業創出を目指す上で技術開発にどの程度の品質や性能が求められるのか、その要求にどう応えるのかといった経験をあまりしていなかったことは不安のひとつでした。
藤原Yume Proプロセスに則って、「機会の特定」「コンセプトの検証」を進め、さらに事業部門と連携していく工程では、品質や性能のレベルはこれまでよりもぐっと上げる必要があります。そうしなければお客様に納得いただける提案ができないし、事業部門も受け入れられない。研究開発者にしてみると以前よりも工数が増えることになり、「そこまでやらないといけないのか」といった不満が生まれる可能性も現実的にはあります。そうしたことも考慮して「UXDをうまくマネジメントできるのは誰か」と検討した結果、塚本さんを抜擢しました。お客様とのコミュニケーションなど対外的な面と、商品開発における品質確保や部門間連携など社内的な面の、両方をマネジメントできる適任者が塚本さんだったわけです。
塚本部長としてメンバーに最初にしたことは、事業部門での経験を、良いことも苦労したことも含めて伝えることです。それから「今後はお客様のニーズに応える品質のものを商品化し、世に出していくことにきちんと関わらなければならない」ということの意識付けと、「そのためにどのようなプロセスが必要か」の説明をしました。UXDにはデザイン思考の下地がありましたし、幸い事業部門を経験したメンバーもいたので、新しいやり方への理解は比較的早く浸透したと思います。
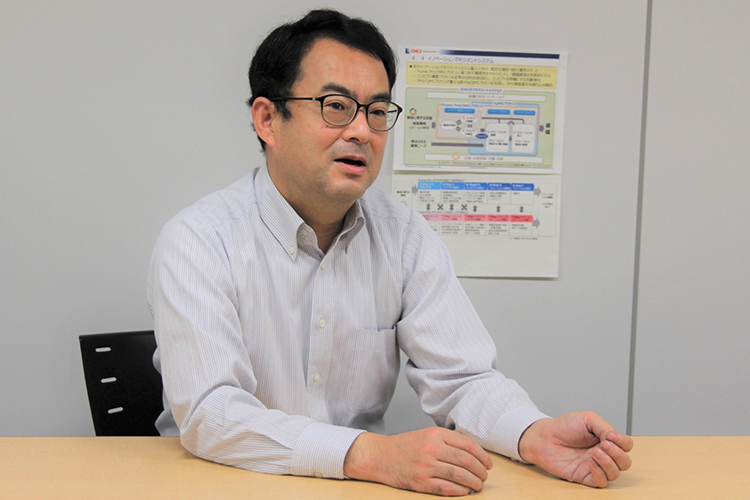
[IMSの活用状況]
社会の変化に合わせたソリューションの創出
塚本UXDでは、「イノベーション戦略」の中でUX領域の注力技術として3つのテーマを掲げています。それは、①デジタルツイン・コンソール、②「個」別化するインタラクション、③ウェルビーイングの把握と支援です。
①ではOKIグループ内の製造や保守現場に向けたXR技術による遠隔作業支援システム、②では表情からの感情推定や視線検出技術を活かした店舗向けのスマートレコメンド(提案型注文)システム、③では行動変容技術でウェルネスオフィスを実現するヘルスケア分野向けソリューションなどの開発を進めています。
藤原これらは “コロナ感染拡大”で起こったニーズとなっていますよね。対面での業務が制限されたことによる課題をグループ内で発見し、解決に向けた価値提供の機会を得ることができました。また、企業におけるウェルビーイングや健康経営が注目されるようになったのも、感染対策や、リモートワークに伴う従業員の健康管理への意識の高まりによるものと思います。
塚本遠隔作業支援システムについては、事業部と深く連携し、工場に入り込んで課題抽出から一緒に進めました。今年度は、視線検出技術を応用し製造現場の作業品質を向上させることにも取り組んでいます。
ヘルスケア分野のソリューションは、IPCのビジネス推進部(BID)と組んでさまざまなプロジェクトを推進しており、鹿島建設株式会社様やコクヨ株式会社様との共創事例をはじめとして確かな成果も生まれています。こうした実績を足がかりに事業部門との連携をどう取っていくかが今後の大きなテーマです。
藤原ウェルビーイングや脱炭素を促進するには人々の行動変容が1つの鍵を握っています。それをDXで実現できるかにチャレンジしているのが、まさにUXDとBIDです。その提案でお客様に「自社のソリューションに組み込みたい」と言っていただけたのは、嬉しいですね。
ただ、ここから商用化に向けた活動を進める中でやるべきことはたくさんあります。それをしっかりやり切っていくことを期待しています。
研究開発から不特定多数の“N”を意識
藤原行動変容のソリューションは、商用化も決して遠くないと思いますが、スピード感を持って進めないと他社に追従される可能性が高い分野です。また、「エンドユーザーが楽しく使ってくれるか」「本当に行動変容が起きているか」を検証していく必要もあります。
実証実験を行う際には、相当な数の利用者にアプローチして検証する必要があるので、きちっと作り込んでいないと「これではすぐに使えない」となってしまう。研究開発部門、特にUXDは、大規模な実証実験に臨むために不特定多数の利用者=Nをしっかり考慮した品質を確保することが必須になります。
塚本Tプロセスでコンセプトの創造・検証を始めた当初、「コンセプト」の意味合いを一般的な「概念」だと捉えていたのですが、実際に進めていくと品質や規模が問われます。とくに検証の段階では、お客様に「買う価値があるか」を見極めていただく必要があるので、単にコア技術だけでなく、たとえばインターフェースや必要な機能、その使いやすさなども含めて、トータルで評価いただける形に仕上げなければいけません。こうしたことも今はメンバーに浸透し、実践にも表れてきています。
[今後の目標・ビジョン]
実践を伴うデザイン思考の浸透
塚本UXDは、デザイン思考の普及にも携わっています。2021年度に実施した「デザイン思考研修」では、当部門のメンバーがカリキュラムを作り、講師も務めました。今年度は「イノベーション実践研修」に組み込み、これまで座学的だったカリキュラムをがらりと変え、リアルな現場課題に、デザイン思考の手法・技法を用いる方法を学べる実践的な内容にしていきます。
藤原デザイン思考で実践に取り組む現場で課題となっているのは、仮説を立ててお客様に提案したものが「ニーズはない」と言われた時に、どうすればいいか分からない、次に打つ手が出てこないという壁に突き当たることです。本来はここで、課題の発見を繰り返さなければいけないのですが、知識やスキルがなければなかなかうまくいきません。
こうした社員の困り事を解決するために、お客様への質問の仕方やコミュニケーションの取り方など、課題発見のアプローチ手法を学べる場はとても大切です。今年度からの「実践モード」を加速させるという意味でも、UXDの教育支援がさらに重要な役目を果たすことになるのは間違いありません。
塚本UXDにおいても、以前からデザイン思考に関する理論や手法は知っていたものの、それらを実践する機会は限られたものでした。しかし、IPCになって、その技法・手法を自ら実践しなければならなくなり、さらに人に教える立場として「模範を示さないといけない」という危機感も芽生えました。今後も引き続き自分たちの実践力を強化し、さらにはそれを多くの社員に浸透させるための行動を活性化させてゆきます。
藤原「模範になろう」という前向きな姿勢は非常にいいですね。ぜひオールOKIとしても、「IMS-Ready」や「全員参加型イノベーション」に積極的に取り組む姿をお客様やパートナーに見ていただけるようにしたいですね。
「お客様があってこそ」を忘れずに、お客様と一緒にいいものを作っていく
塚本UXDが今後目指すところは、繰り返しになりますが「実践力のある組織」です。UX技術の多様な引き出しを用意し、お客様の困り事を正しく把握して的確なソリューションを提案できる。そして技術を開発し商品としてアウトプットしていくことを日常の業務とする組織にしていきたいです。それが、新規事業創出という形で社内貢献につながっていくと信じています。
そして、そうした取り組みはお客様があってこそできるということも忘れずにいたいと思います。「お客様の課題解決のために、お客様と一緒にいいものを作っていく」ということを実践していきます。
藤原私はよく「研究開発者自らがエンドユーザーの視点になって考えなければいけない」と言っています。是非、「お客様と共にエンドユーザーを見て、一緒に提供価値を考えていく」ことは非常に大事です。これに関しても率先垂範でOKIを引っ張っていってほしいと思います。
(2022年8月15日、OKI執行役員 CINO兼CTO 藤原 雄彦)





