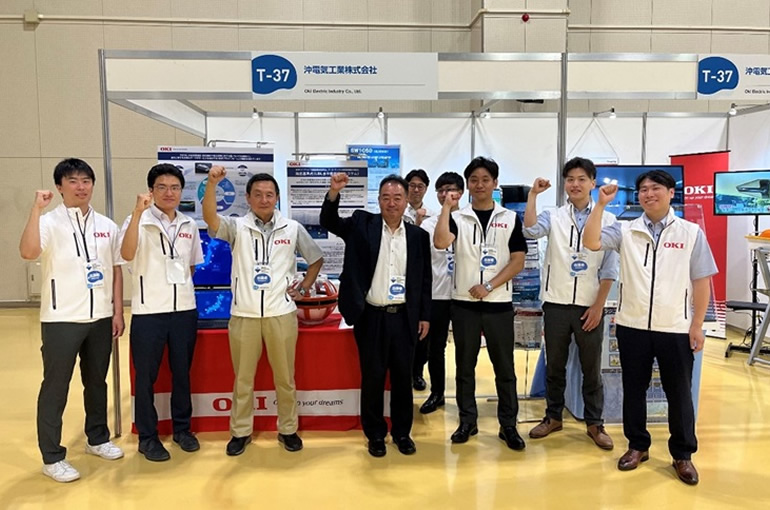- HOME
- デジタルトランスフォーメーション(DX)
- DX最新情報
- 無線が医療機器に悪影響?医療現場の負担を減らす無線事例3選

DX最新情報
無線が医療機器に悪影響?医療現場の負担を減らす無線事例3選
医療現場では、電子カルテに代表されるようなICTの活用が急速に進んでいます。2014年に病院内の携帯電話の利用が緩和され、無線の利用も広がっています。ここでは、医療現場での課題を踏まえた無線の適用例をご紹介します。

医療機関のICT化で、無線の利用が拡大する理由とは
医療機関のICT化がイノベーションを引き起こす

現在、総合病院や診療所などの医療機関では、急速にICTの活用が進められています。
たとえば電子カルテを導入することで、従来は医師が紙に記入していたカルテをパソコンやタブレットに置き換えることができます。カルテを電子情報としてデータベースで管理するため、診療の際に患者の情報を素早く引き出したり、病院内で患者の情報を共有することにより受付や会計の業務を効率化できます。これにより、看護師、薬剤師、受付スタッフの業務負担を軽減できるだけでなく、患者の待ち時間を削減できるメリットもあります。
既に国内の病院では、2016年で42.5%、400床以上の大規模な病院では79.8%の病院が電子カルテを導入しています。電子カルテは、急速に普及が進む一方で、システム毎にデータ仕様が異なり、他の病院とは医療情報をやり取りできない課題も顕在化しています。厚生労働省が主導して医療情報の標準化を進めており、病院と診療所間といった地域医療連携にも役立てることが期待されています。
電子カルテ以外のICT活用としては、医用テレメーター(医療機器のデータ送信)、無線LANや携帯電話、タブレットなどの電波を利用する機器の活用が進んでいます。また、入院患者や面会者向けのインターネットアクセスを提供する病院も増えてきています。
また、医療の質の向上や地域格差の是正が期待される遠隔医療は、ICTを最大限に活用した医療といえるでしょう。
スマートフォンやタブレット活用には無線の利用が欠かせない

一昔前までは、病院の中では携帯電話の電源を切ることが常識でしたが、現在では待合室や病室、診療室でも電源を切る必要は無くなっています。
これはかつて、"病院や診療所での携帯電話の使用は原則禁止する"という指針が、総務省が参加している「不要電波問題対策協議会(現在の電波環境協議会)」から1997年に示され、病院内での携帯電話の利用には制約があったからです。
一方、病院内における無線LANやPHSの利用ニーズの高まりを受け、総務省の地域振興のための電波利用に関する調査研究会では「病院内における電波利用に関する調査研究報告書」を公表するなど、電波が医療機器に与える影響などが研究されてきました。
その後、2G携帯サービスの廃止により携帯電話の電波の出力が小さくなっていることや、医療機器の性能が向上して電波による影響が大幅に減ったことなどから指針が見直され、2014年に「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」として新しい指針が発表され、病院における携帯電話の利用が大幅に緩和されました。この指針では、病院内の待合室や病室、診療室のエリア毎に携帯電話の使用ルールを設定することや、携帯電話の離隔距離の設定が示されています。
携帯電話からの電波は、端末からの距離が遠くなるにつれて減衰します。そのため一定の離隔距離を確保すれば、医用電気機器への影響を防ぐことができると考えられており、医用電気機器から1m程度を離すことを目安とされています。一方、医用電気機器に密着して使用した場合は大きな影響が発生するおそれがあるため、医用電気機器の上に携帯電話端末を置くことは禁止されています。
また、携帯電話以外の無線通信機器の使用については、患者や面会者などのスマートフォンやタブレットの使用が生活に不可欠なものとなってきていることや、医療用システムとしての無線通信機器の使用が急速に普及していることから、PHS、無線LAN、フェムトセル基地局(低出力で狭いエリアをカバーする小型基地局)の利用が想定されています。
医療機器の所在管理などの用途でRFIDタグやBluetoothなどの普及も進んでいます。これらの導入に当たっては、それぞれの医療機関において独自に試験を行った場合は、その試験結果や医用電気機器の取扱説明書からの情報などを元に、医用電気機器への影響について確認を行うことが規定されています。特にRFIDは、読み取り機(リーダー)などから強い電磁波が発出される場合があるため、導入に当たっては慎重に影響の確認を行うことが必要とされています。この指針はあくまでも"指針"であるため、最終的な判断は各医療機関に委ねられることになります。
医療機関でのICT導入に立ちはだかる、さまざまな課題とは?
◇ セキュリティの問題
特に電子カルテのような重要な個人情報が含まれる診療情報は、過失による情報漏えいや目的外利用も大きな問題になる危険性があります。ウィルス対策や情報漏えい対策といったシステム的な対策だけでなく、医療機関で雇用している職員へセキュリティに関する教育を実施したり、注意を促すといった人的な対策も必要になります。
◇ 医師、看護師、病院職員のITリテラシーの問題
PCに慣れていない医師や看護師などの医療従事者の場合は、文字のタイピングに時間がかかり、必要な情報を呼び出すのに時間がかかることが考えられます。また、ICTシステムを導入し適切に運用するためには、機器や工事などの多額の導入費用とITの知識を持った担当者による適切なシステム運用が必要になります。こういったシステムの初期導入費用や運用の負担を軽減するため、クラウドサービスを利用することも選択肢の一つとなります。
◇ 機器の導入時の問題

病院内に機器やセンサーを設置する場合には、病院内の工事が課題となります。24時間365日稼働している病院では、入院患者へ精神的なストレスを与えないため、騒音や振動が発生する大規模な工事は避けなければなりません。
無線を利用した病院内の管理・監視の3つの適用例
ここで、ICTを活用した、病院での無線利用について適用例を3つ紹介します。
1)病室の室内空気環境の監視の例
病室では適切に換気を行い、空気環境を快適に保つ必要があります。厚生労働省の建築物環境衛生管理基準では、病院では二酸化炭素(CO2)濃度の基準は1,000ppm以下と定められています。空気環境が管理基準を満たしているかどうかを管理するためには、病院内の各病室に環境センサーを設置し、リアルタイムで監視をする必要があります。
ここで、電波到達性が高く免許不要で利用できる920MHz帯無線を使用して、各センサーを接続することで遠隔から全ての病室の環境監視ができます。さらに各病室への配線工事が不要となり、入院患者に不便をかけることなくシステムを導入することが可能になります。
2)薬品保管庫の温度管理の例
病院内で使用される薬品は、病院内に点在して存在する薬品保管庫で保管されています。この薬品が適切な温度範囲で保管されているかどうかを管理し、履歴を管理する必要があります。
そこで、常温の薬品保管棚の温度管理には電池で駆動する無線内蔵の温湿度センサーを設置し、低温の温度測定が必要となる冷凍保管庫には、測温抵抗体を使用した温度センサーを設置するなど最適な温度センサーを選び、これらのセンサーを無線で接続することで、配線工事無しでシステム導入が可能になります。さらに、遠隔からリアルタイムで監視ができるため、病院職員や看護師の手作業での管理作業の負担を軽減することができます。
3)手術器具や医療機器の所在管理の例

院内で使用される医療機器は、患者の治療などに合わせて移動して使用されることが多く、いざ機器が必要となった際に機器が見つからないことが病院での課題となっています。
そこで、所在管理が必要な医療機器にRFIDタグを取り付け、病院内の各所に設置されたRFIDリーダーを介して、RFIDタグの情報を読み取ることで所在を把握することができます。これにより機器を探す手間や時間の削減や、器具の紛失を防止することができます。病院内の各所に設置するRFIDリーダーを920MHz帯無線を使って結ぶことで、工事コストを削減することも可能です。
医療現場では、「人」も「システム」も世代交代が進んでいる
医療現場では、ICT化に保守的であったベテラン医師から、ICTに違和感のない若手医師への世代交代が進んでいることを背景に、大規模な病院だけでなく中小規模の病院にもICT化の波が押し寄せています。また、医療現場側のニーズが「機器」から「サービス」へシフトし、クラウドサービスを活用する例が増えているなか、現場の設置工事コストを最小化できる無線の利用が注目されています。
病院内の利用においても実績のある920MHz帯無線機は、たとえば以下の商品があります。病院内のICT導入を検討する際には、無線の利用を検討してみてはいかがでしょうか?
- OKIのDXの活用・導入に関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。
- Webからのお問い合わせ: お問い合わせはこちら(別ウィンドウで開きます)
- ※本記事は2016年9月に掲載しました。記事中に記載する数値、固有名詞、市場動向等は掲載日現在のものです。