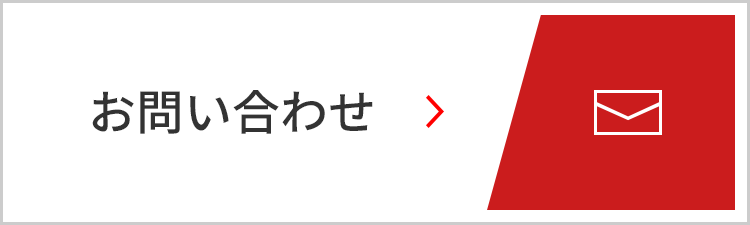- Home
- 商品・サービス
- 海洋の取り組み(海洋プラットフォームなど)
- 水中音響通信
海洋
水中音響通信

省人化、省力化の需要に伴い、海洋分野でも水中IoT機(水中ドローン、水中ロボット、AUVなど)の利活用が重要になってきます。水中音響通信は水中無人機運用の可能性を広げることができる技術になります。OKIは水中IoT機で活用できる水中音響通信の開発に取り組んでいます。
水中音響通信の活用イメージ

- 沖合養殖の設備管理
- 遠隔地にいるオペレーターが、水中音響通信を介して水中ロボットを制御して設備の状況を人に代わって行います。

- 海洋資源調査
- 一人のオペレーターが複数の水中ドローンを制御して、短期間で効率よく海底の資源調査を行います。
水中音響通信とは?
水中における通信方法として、おおまかに有線通信、音波を使った無線通信(水中音響通信)、光を使った無線通信(水中光通信)の3つがあります。
| 長所 | 短所 | |
|---|---|---|
| 有線通信 |
|
|
| 水中音響通信 |
|
|
| 水中光通信 |
|
|
水中音響通信は、水中での無線通信が行うことができ、一般的な長所としては長距離通信が可能です。ただし、通信容量が少なく、画像や動画などの大容量データには適していません。
通信容量が少なる理由としては、マルチパス(※1)や水中IoT機(水中ドローン、水中ロボット、AUVなど)の移動により発生するドップラー効果(※2)が通信の安定性に大きな影響を与えます。
OKIは今後、海洋資源探索において水中IoT機器が広範囲で自由に活動できる仕組みが必要と考えています。そのためには長年、取り組んできた長距離通信が可能な水中音響通信の技術を活かし、更なる高度化を目指して日々、研究開発を取り組んでいます。

マルチパス
ドップラー効果
- ※1 マルチパス
経路の異なる複数の波のこと(水中では海面反射波、海底反射波など)。送出した音波が海面の波や複雑な海底地形面により、干渉や遅延ノイズなどが発生して、受信する側に正常なデータが届かなくなり、通信が成立しないことがある。 - ※2 ドップラー効果
音波など波の発生源と観測者との相対的な速度によって、発生波の周波数とは異なる周波数が観測される現象。
OKIが独自開発する水中音響通信
水温、塩分濃度、溶存酸素など、水中IoT機(水中ドローン、水中ロボット、AUVなど)にセンサーを取り付けることで海中の情報を安全に収集することができます。とくに複数の無人機を同時に使用することで広大な海洋で効率的な情報収集が可能になります。
OKIは水中音響通信によって、水中IoT機に設置したセンサーで収集した情報をリアルタイム・ニアリアルタイムで、有人船(母船)・陸上設備に集約を可能にすることを目指しています。通常、陸上の無線で使われる電波が減衰する水中では、音響通信のネットワークを構築し、水中以外では高速な有線・通常の無線通信を行います。
この運用により、海洋のオペレーションをより効率的かつ安全に行うことができると考えています。

目標性能
| 通信速度 | 32kbps |
|---|---|
| 通信距離 | 2km |
| 耐ドップラー性 | 相対10kt(5m/秒) |
| 周波数帯域 | 14kHz-30kHz |
| 変調方式 | OFDM-16QAM |
| 送波器数 | 1 |
| 受波器数 | 4以下 |
| 1対N通信 | 開発中 |
水中IoT機の利用効率性を考えて通信距離を2kmと設定し、その中で通信速度を32kbpsと設定しました(従来の性能指標よりも1.6倍の高速化)。32kbpsでは粗い画質の映像通信ができる限界値程度になります(テレビ電話で音声を認識できる)。実際には水中IoT機器内でセンサーデータを処理して集約した情報を送付するユースケースを想定しています。
一般的に水中音響通信では、マルチパスや無人機の移動により発生するドップラー効果が通信の安定性に大きな影響を与えますが、OKIの水中音響通信は、マルチパスへの耐性を確保しつつ、ドップラー効果については無人機の移動に対して相対10ktまでの移動に対応することができます(例:水中IoT機同士が逆向きに5ktで移動する場合)。
OKIが目指す実用化に向けたシナリオ
水中音響通信技術によって水中の無線通信ネットワークの構築が可能になれば、沖合養殖の設備管理や海洋資源調査など、海洋産業の効率化や新たなビジネスの創出が可能になります。
今後OKIは、水中における1対Nでの複数通信や、IoT機を中継ノードとしてさらなる遠距離通信を可能にする水中でのマルチホップ通信などの開発を進め、1つのシステムで複数の水中IoT機が広範囲で利用可能となるシステムの実用化を目指します。
- STEP1:2020年11月発表
- 鉛直方向の伝送通信:洋上母船とIoT機器間
- STEP2:2023年6月発表
- 水平方向の伝送通信:長距離の海中間
- STEP3:今後
- 中継機能: IoT機器を経由した通信機能
- 複数通信機能:複数のIoT機器を同時に制御する機能