COLUMN
【2025年最新】設計図書の電子化とは?法的要件から現場での活用法、オススメのクラウドサービスを徹底解説

「設計図書の電子化に興味があるが、法律がクリアできるか不安・・・」「データはどう活用すればよいのだろう・・・」そうした疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、最新のガイドラインを踏まえ、設計図書の電子化に必要な法的要件を徹底解説します。さらに、電子化した図面を現場で最大限に活かすクラウド活用術と選び方、オススメのクラウドサービスもご紹介。
設計図書管理の電子化に興味がある、検討中のご担当者は必見です。
目次
設計図書とは?
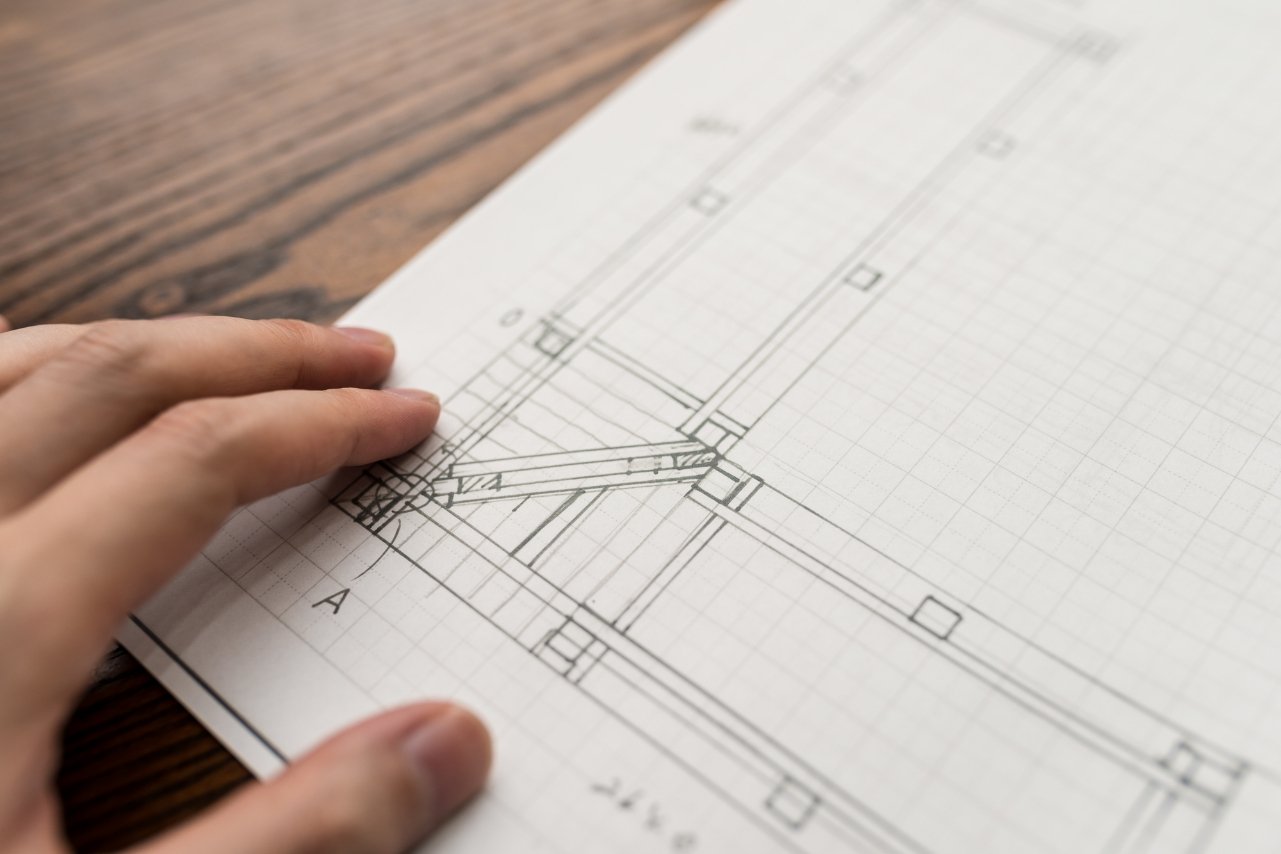
設計図書とは、建築プロジェクトにおける設計者の意図を、施工者へ正確に伝達するための重要な書類です。建築図面、仕様書など多岐にわたる書類が含まれますが、特に重要なのは以下の2つです。
- 建築図面: 建築物の構造、配置、機能などを詳細に図示したもので、建物の全体像や各部の寸法、形状などが記載されている
- 仕様書: 使用する材料の材質、品質、施工方法などを具体的に記述したもので、図面だけでは伝わらない詳細な情報が記載されている
これらの設計図書には、建築の工程、使用材料、具体的な作業内容など、建築プロジェクトに関するあらゆる情報が網羅されています。そのため、工事費用の見積を算出する積算業務においても、重要な役割を果たします。
また、設計図書は、建築基準法に基づき、施工後一定期間(一般的には15年間)の保存が義務付けられています。この保存義務を怠り設計図書を廃棄、紛失した場合、建築士法により罰則(30万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。
従来、設計図書は紙媒体での作成・保存が一般的であり、その管理には多大なコストと手間がかかっていました。しかし、2005年に施行された「e-文書法」(電子帳簿保存法)によって、設計図書の電子データによる保存が法的に認められ、設計図書の電子化が急速に進展しました。
設計図書の電子化、法的にどうすれば?最新要件と現場活用法
設計図書の電子化は、効率化やコスト削減など多くのメリットをもたらしますが、「法的要件が複雑で難しい」と感じる方は少なくないでしょう。
ここからは、設計図書の電子化における最新の法的要件と、電子化した図面を現場で最大限に活用する方法を詳しく解説します。
2023年JIIMAガイドラインによる最新要件
2023年にJIIMA公益社団法人「日本文書情報マネジメント協会 ガイドライン検討会」が発表した「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」は、設計図書の電子化における作成、保存に関する要件が細かく規定されています。
主な要件は以下の通りです。
作成時の要件:
・電磁的記録で作成された各設計図書に建築士の記名を行う
15年間の保存方法:
・電子ファイルの原本を、ドキュメント管理システムなどで適切に保存・管理する
・バックアップを作成し、その証明を可能にする
・電子ファイルにタイムスタンプを付与し、10年経過前に追加のタイムスタンプを付与して保存期間を延長する
保存要件:
・保存期間を通じて、作成時と同じ状態であることを確認できるように、真正性を確保する
これらの要件を満たすことで、設計図書の電子データは法的にも有効なものとして扱われます。
電子化した設計図書を現場で最大限に活用する方法
設計図書を電子化する最大のメリットは、現場での活用です。以下に、業務効率を大幅に向上させる現場での活用法を解説します。
クラウドサービスの活用:
・タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末から、いつでもどこでも設計図書にアクセスできるようにする
・リアルタイムでの情報共有を可能にし、コミュニケーションの円滑化を図る
図面管理システムの導入:
・設計図書のバージョン管理や検索機能を活用し、必要な情報を素早く見つけられるようにする
・図面への書き込みや注釈機能を使用し、現場での情報共有や指示の伝達を効率化する
クラウドサービスの選び方:設計図書電子化を成功させるために
設計図書の電子化を成功させ、現場での業務効率を最大化するためには、適切なクラウドサービスを選ぶことが重要です。クラウドサービスを選ぶ際には、以下のポイントを参考に検討しましょう。
- 法的要件への対応: JIIMAガイドラインなどの法的要件を満たしているかを確認しましょう。データの真正性や保存期間、セキュリティ対策などが重要です。
- 現場での使いやすさ: タブレットやスマートフォンなど、現場で使用するデバイスに対応しているか、操作性が高く、スムーズに図面を閲覧・共有できるかを確認しましょう。
- 必要な機能の搭載: 図面のバージョン管理、書き込み・注釈機能、CADデータ連携など、現場で必要な機能が搭載されているかを確認しましょう。
- セキュリティ対策: 設計図書は機密情報を含むため、セキュリティ対策が万全であるかを確認しましょう。アクセス権限の設定やデータ暗号化などが重要です。
- サポート体制: トラブル発生時のサポート体制が整っているかを確認しましょう。導入時のサポートや操作説明なども確認しておくと安心です。
これらのポイントを総合的に判断し、自社のニーズに最適なクラウドサービスを選びましょう。
オススメ:OKIの図面活用クラウドサービス 「TerioCloud」とは
OKIのTerioCloudは、設計図書の電子化と活用を強力にサポートするクラウドサービスです。建設、製造、メンテナンスなど、さまざまな現場で図面を扱う業務において、情報共有の効率化と生産性向上を実現します。

TerioCloudは、これまでの紙図面で悩ましかった「現場での持ち運びや閲覧に手間がかかる」「情報伝達の遅延」「図面の劣化・紛失」といった課題を解決するために開発されました。
TerioCloudを利用することで、タブレットなどのモバイル端末から、いつでもどこでも必要な図面にアクセスできます。図面の共有や閲覧がスムーズに行えるため、現場でのタイムリーな情報共有、コミュニケーションの円滑化や意思決定の迅速化に貢献します。
また、図面への書き込みや注釈機能、バージョン管理機能なども搭載されており、現場での作業効率を大幅に向上。TerioCloudは、設計図書の電子化を単なるデータの置き換えに留まらず、業務全体の効率化と生産性向上に貢献します。
まとめ
設計図書の電子化は、2005年の「e-文書法」や2023年のJIIMAガイドラインによって着実に進んでいます。設計図書の電子化を検討する際には、この記事で解説した法的要件をしっかりと理解しておくことが重要です。また、電子化した図面を現場で有効活用するためには、クラウドサービスなどのツール導入がおすすめです。
設計図書の電子化を検討されている方は、ぜひTerioCloudの導入をご検討ください。TerioCloudを活用することで、設計図書の電子化を成功させ、業務効率と生産性を向上させることができます。
TerioCloudの詳細については、お気軽にこちらからお問い合わせください。
<参考情報>
・OKIの図面活用クラウドサービス 「TerioCloud」
参照:JIIMA公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 ガイドライン検討会 「建築設計業務における設計図書の電磁的記録による作成と保存のガイドライン」
PICK UP
その他の記事
TAG
キーワードから探す
RELATED ARTICLES
関連記事
CONTACT
OKI Style Squareに関するご相談・
お問い合わせはこちら







