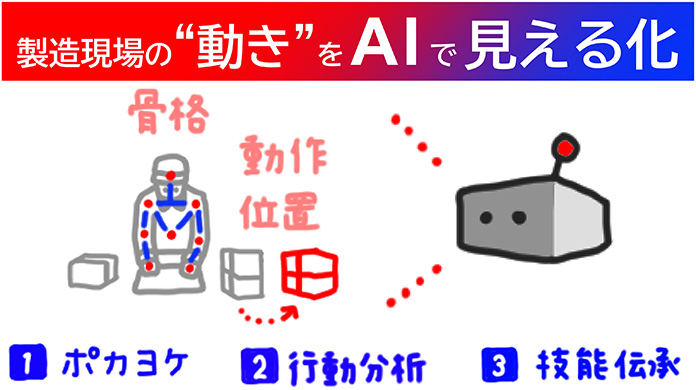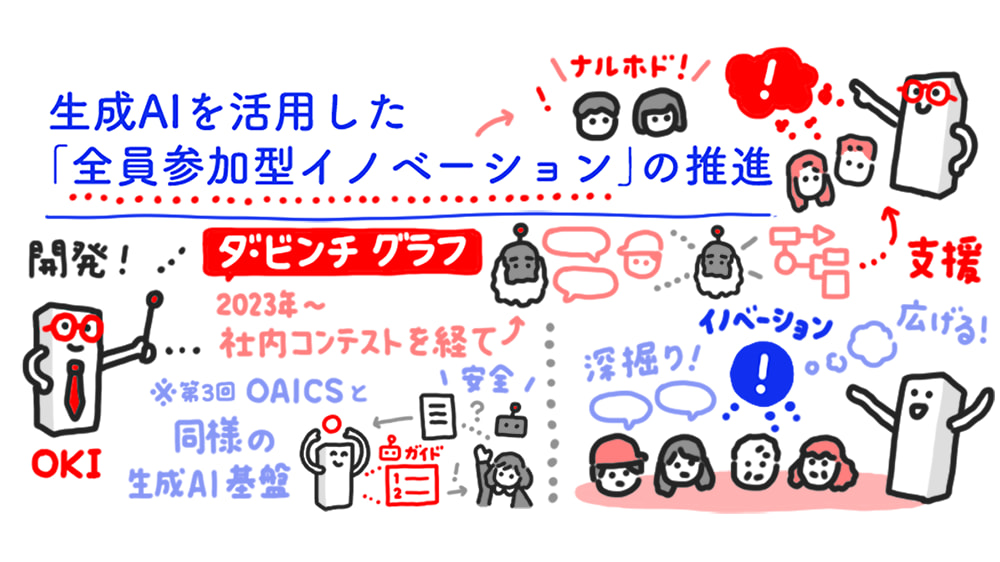COLUMN
「海洋の見える化」を実現!OKIが提供する「海洋プラットフォーム」とは?

「海洋の見える化」とは、OKIが保有する「水中センサー」「水中音響」「情報処理」の技術を活用して、陸上と同じように海中の状況を把握することを指しています。今回は、「海洋の見える化」の目的や効果のほか、それを実現する「海洋プラットフォーム」についてご紹介します。
目次
「海洋の見える化」は何のため?海洋事業が抱える課題とは?

「海洋の見える化」は、海洋事業が抱える以下のような課題解決に役立てることができます。
海中の侵入者・不審な自律型無人潜水機(AUV)の侵入
海洋構造物の破壊や海洋資源の略奪を目的に、海中に侵入者(ダイバー)や不審な自律型無人潜水機(AUV)が忍び込むケースが想定されます。このような侵入者・AUVから構造物や資源を守るための、防犯・監視を目的としたソリューションが求められています。
また、海洋安全保障の観点から、他国の潜水艦による日本の領海への侵入監視も非常に重要です。
水中での作業の安全確保
海洋構造物の工事や点検、メンテナンスでは、ダイバーによる海中作業が必要になります。不慮の事故を未然に防ぐために、ダイバーの安全確保のさらなる改善が求められています。
海洋建造物の老朽化・破損
自然災害や経年劣化により、海外では大規模な海洋構造物の老朽化・破損が進んでおり、点検・メンテナンスのコストが膨らんでいます。また、老朽化の進行にメンテナンスが追い付いておらず、作業を効率化させるテクノロジーが求められています。
地球温暖化等による海洋資源・水産資源への影響
地球温暖化による海洋資源や水産資源への影響も深刻な問題となっています。温暖化が進行すると、海水温度が上昇し、それに伴い海洋環境や生態系にも変化が起こります。この変化は、魚種の分布、繁殖パターン、食物連鎖等に影響を及ぼし、最終的には水産業にも大きな影響を与えることが懸念されています。
OKIの「測る・伝える」技術で実現!海洋プラットフォームの概要とその効果

OKIは、海洋プラットフォームをの構築にとってすることで、上述した海洋事業が抱える課題解決にチャレンジしています。では、「海洋プラットフォーム」とは何なのか?また、導入することでどのような効果が得られるのかについて解説します。
海洋のあらゆるデータをモニタリングする「海洋プラットフォーム」とは?
「海洋プラットフォーム」とは、海洋のあらゆるデータをモニタリングすることで、上述した海洋事業が抱える課題を解消することを目的にしたシステムのことです。「海洋プラットフォーム」の開発は、以下のSTEPで進行しています。
STEP1:技術開発・活用する技術(~2025年)
すでにOKIが保有している「水中音響技術」を活用し、海洋のデータをモニタリングする技術の研究・開発をするフェーズです。国の研究開発プロジェクトなどを通じて、海洋プラットフォームの実現に欠かせない技術を開発しています。現在、海中の微弱な音を検出する「光ファイバーハイドロホン」、検出した音源の「方位・位置推定」技術、検出した音源の「類識別技術」技術の開発や実証実験に取り組んでいます。
STEP2:海洋モニタリング技術の研鑽と実績作り(2026~2028年)
海洋モニタリング技術を実際に導入して実績を増やしていくフェーズです。また、導入後のフィードバックを通して改良を施し、技術の精度を高めていきます。
STEP3:海洋モニタリングの社会実装(2029~2031年)
海洋モニタリング技術を完成させ「海洋プラットフォーム」として社会実装するフェーズです。OKIが保有する「水中センサー」「水中音響」「情報処理」の技術を活用して、海のあらゆるデータをモニタリングする「海洋プラットフォーム」を実現し、上述の海洋事業が抱える課題解決に貢献します。
海洋プラットフォームの効果
「海洋プラットフォーム」がどのような問題を解決するのか、またその効果はどのようなものなのかについて解説します。
海中の侵入者・自律型無人潜水機(AUV)の検出
海洋プラットフォームのモニタリングシステムによって、海洋構造物などの重要施設に侵入した不審な人(ダイバー)・モノ(AUV等)を早期に検出し、犯罪を未然に防止することで、海の安全を守ることに役立てることができます。
海洋構造物のメンテナンス・資源探査・海洋開発の安全性向上
海洋プラットフォームのモニタリングシステムによって、水中で作業しているダイバーや水中ロボットが「どこでどのような作業をしているか」リアルタイムで確認でき、作業者・ロボットの安全確認・作業状況確認・位置把握に役立てることができます。また、水中音響通信技術を使って水中ロボットが撮影した映像を遠隔からリアルタイムで確認できるのもポイントです。
海洋環境・漁業資源の保全(藻場の見える化など)
養殖業や漁業などの水産業に海洋プラットフォームのモニタリングシステムを導入することで、「どこにどれぐらいの量の魚がいるのかを見える化」でき、水産資源管理などに役立てることができます。また藻場の育ち具合を確認することもでき、海洋環境や資源を守り、脱炭素社会の実現に貢献することもできます。
まとめ:OKIの目指す海洋の見える化とは?
海洋開発の効率化・安全性の向上は、海洋事業が抱える課題解決だけではなく、海洋安全保障、経済安全保障や脱炭素社会の実現に欠かせない要素となっています。OKIは、今回ご紹介した「海洋プラットフォーム」によって「海の見える化」を実現し、海洋事業が抱えるさまざまな課題の解決と海洋環境の適切な管理に貢献していきます。
PICK UP
その他の記事
TAG
キーワードから探す
RELATED ARTICLES
関連記事
CONTACT
OKI Style Squareに関するご相談・
お問い合わせはこちら