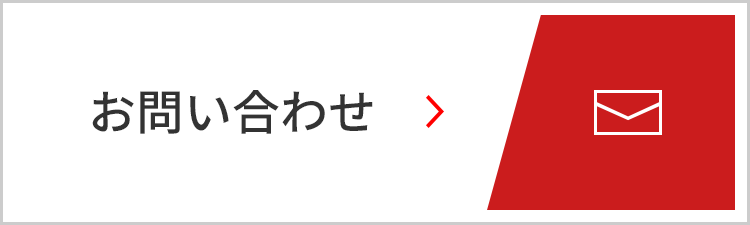導入事例
OKIグループの商品・サービスにより課題を解決された
お客さまの声や、共創への取り組みをご紹介します。
スマートフォンナースコールで業務効率を大きく向上
情報連携の充実により、さらなる医療サービス向上を目指す

茨城県厚生農業協同組合連合会
総合病院 土浦協同病院
総合病院 土浦協同病院は、プライマリケアから三次救急医療、緩和ケアから高度先端医療、予防医療からリハビリテーションなどの総合的な医療を展開。高度先進医療を含めた質の高い医療を提供する地域中核病院として、茨城県全体の医療を担っています。2016年3月、旧病院から7kmほどの高台にすべての疾患に対応する800床の急性期総合病院として移転新築オープン。救命救急センターは大型ヘリポートも設置、広域災害救急にも対応するほか、2021年には手術支援ロボット「ダビンチサージカルシステム」を導入、500症例を超えるなど、先進医療にも注力しています。同院では2016年よりOKIのPBXと「Com@WILLソフトフォンスマート」アプリケーションをケアコム社のナースコールシステムと連携させ、iPhoneによるスマートフォンナースコールを活用。情報連携機能を充実させ、さらなる医療サービスの向上を目指しています。なお本システムは、OKI商品取扱店の水戸通信工業株式会社が受注・構築しました。
- 本事例のリーフレット
概要
- 課題
-
- 新病院への移転を機に、安全で強固な情報共有システムを構築
- 旧病院のナースコール用PHSでは、電子カルテを閲覧できず、不便さを感じていた
- PDAなど複数の端末が必要、手書きメモのPCへの再入力が必要など非効率
- 成果
-
- iPhoneによるスマートフォンナースコールを実現、駆け付け前に状態が分かり安心
- メモや撮影画像のiPhoneから電子カルテへの反映など必要な機能を実現
- ナースコール応対および医療情報閲覧も、スマートフォン1台で実現
導入ソリューション
Com@WILLソフトフォンスマート
スマートフォン(iOS/Android™)にナースコール連携用アプリケーションをインストールすることにより、ハンディナース端末として利用することができます。
※Com@WILLソフトフォンスマートのご利用にはOKI製のPBXまたはビジネスホンの導入が必要です。

詳細
課題・背景
2016年の新病院移転を機に
スマートフォンナースコール導入を決断
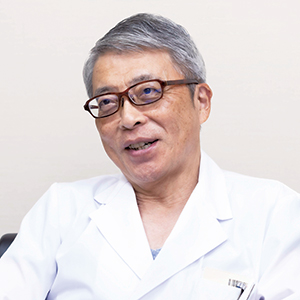
総合病院 土浦協同病院
統轄病院長補佐
滝口 典聡氏

総合病院 土浦協同病院
副院長兼看護部長
宮本 佳代子氏
2016年の新病院移転について、統轄病院長補佐の滝口典聡氏は、次のように話します。「当院は2016年3月、あらゆる疾患に対応する800床の急性期総合病院として移転新築オープンしました。それを機に、世界の大手企業に匹敵する安全で強固な情報共有システムを構築。電子カルテはもちろん、患者の最新の状態や手術の進捗状況、そしてナースコールに至るまですべての情報を集約し、各スタッフがタブレットや院内の大型モニターなどでいつでも確認できるような環境を整えました」。
そして、そのタイミングで他院に先駆けてナースコール応対用にスマートフォンを導入した経緯を、副院長兼看護部長の宮本佳代子氏は、こう話します。「 移転の2年ほど前から、新病院のナースコールシステムについての要件を固めていきました。私は県の指定で1995年にオープンした院内併設の地域がんセンターで勤務した際、ナースコール応対専用のコードレス電話機を利用した経験があります。かなり大型の端末でしたが、着信の際に何号室のどのベッドからの呼び出しかがわかり、とても便利だった記憶がありました。一方、旧病院ではPHSとナースコールシステムが連動しておらず、不便さを感じていました。そのギャップを埋められるのでは?との期待があって、2016年当時ではまだあまり普及していなかったナースコール応対のスマートフォン化を選択しました」。
端末にiPhoneを選定したポイントについて、情報システム管理室の青野世那氏は、こう述べます。「看護部からの要件としては通話を効率的にしたい、複数の端末を持ち歩きたくない、電子カルテや看護支援システムと連携したい、バイブレーション機能が欲しいといったものがあり、それをすべて満たせる機種としてiPhoneが浮上しました。当時、Androidに比べiPhoneは高価でしたが看護支援システムとしての機能性および、将来性などを総合的に勘案してiPhoneを選定しました」。
導入のポイント
ケアコム社ナースコールシステムとの連携性および
iPhoneでの開発に前向きなOKIを選定

総合病院 土浦協同病院
情報システム管理室
青野 世那氏
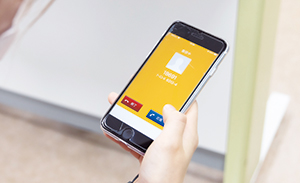

OKIのスマートフォンナースコールは、PBX(DISCOVERY neo/neo2、CrosCore3)、アイホン社/ケアコム社のナースコールシステムと連携し、従来のPHS に加えて、「Com@WILLソフトフォンスマート」アプリケーションでスマートフォンをハンディナース子機として利用できます。ナースコール応対も医療情報閲覧も、スマートフォン1台で実現します。
スマートフォンナースコールのパートナーにOKIを選定した理由を、青野氏はこう明かします。「当院が利用しているケアコム社のナースコールシステムと連携できることが、決め手でした。併せて、当時iPhone によるナースコールシステム連携は対応が難しいとするベンダーが多い中で、OKI だけが積極的に手を挙げていただいたことも大きな要因でした」。
OKI は同院からの要望に応え、「Com@WILL ソフトフォンスマート」アプリケーションでiPhone によるナースコール連携を実現。青野氏は当初の苦労を、こう語ります。「たとえば初期は、圏外から戻ったときにアプリを立ち上げ直さないとならない不便さがありました。これはiPhone の当時のOS 仕様によるものだったのですが、その後、OKI にプッシュ通知対応いただいたことで改善されました。また、一部通信が不安定な場所が見つかりましたが、こちらも無線LAN のアクセスポイントを増強することで解消されました」。
ちまたでよくささやかれるスマートフォンは操作が難しい、通話品質が不安といった声について、同院の現場における導入時の反応を、宮本氏は次のように話します。「当時、同時に刷新される電子カルテの操作説明会は開催しましたが、iPhoneの操作について分からないであるとか、戸惑うといった声は、現場からはほとんど挙がりませんでした。音声品質についても、まったく気になりませんでした」。
成果・今後
スマートフォンナースコールの機能性で業務効率を向上
さらなる高品質な医療サービス提供を推進
同院では、ナースコールとしてのiPhoneが約300台、内線通話と院内ホームページ閲覧のみのiPhoneが約600台。さらに、化学療法室など通話機能が不要な箇所ではiPod Touchも利用されています。
iPhone によるスマートフォンナースコールの導入効果は、多岐に及びます。宮本氏に、ポイントを挙げていただきました。
「呼び出しの際、何号室のどのベッドからか、浴室やトイレなのかなどの場所も、ディスプレイ画面から一目で分かります。緊急度合いも、画面の色や音で識別できます。さらに、電子カルテや生体情報モニターのアラートも連動しており、駆け付ける前に手元で患者さまの状態が把握できます」。
「患者さまのリストバンドと投与する点滴のバーコードをチェックして、患者誤認、薬剤の取り違いや用量違いなどを防ぐことにも役立っています。かつては、重い専用のPDAを首から下げて、夜間は懐中電灯も必要でした。iPhoneナースコールなら1台で済み、バックライトもあるので夜間も非常に便利です」。
「体温などのバイタル情報も、従来は手書きメモを取りナースセンターで入力していましたが、いまはベッドサイドでiPhoneから入力すれば、そのまま電子カルテへ連携します」。
「術後創傷の経過確認などは患者様のリストバンドでバーコードを読み込み、iPhone のカメラで撮影して必要な画像を選択、そのまま電子カルテに連携できます。これまでのようにデジカメで誤認を防ぐため患者さまのリストバンドも一緒に撮影して、ナースセンターのPCにSDカードを使って取り込む、といった手間がなくなりました」。
「褥瘡(じょくそう)を防止する耐圧分散マットレスの貸し出し状況も手元で確認できるようになり、これまでのようにホワイトボードとマグネットで一覧化して管理するといった手間がなくなりました」。
「手術室の監視カメラ映像を、スマートフォンナースコールから常に見られるよう連携しています。連絡が取りづらい室内の様子が分かることで、終了時間の把握や連絡するタイミングがつかみやすいなど、さまざまなメリットがあります」。
このように、大きな効果を上げているスマートフォンナースコール。同院では今後さらに機能を充実させ、医師や看護師の業務効率と働きやすさの向上、そしてさらに質の高い医療サービスの提供につなげたい意向です。
「欲しい機能としてはチャットです。互いの状況を問わず気軽に連絡が取りあえて、履歴が残る。医師側でも病棟のスタッフグループに指示が出しやすく、看護師からも医師に問い合わせしやすいことで、多くの打ち合わせが不要になるでしょう。また、たとえば急患の手術の担当医を調整するといった際なども、タイムラグが解消できる期待もあります」。(滝口氏)
「音声入力の自動文字起こしツールも利用できれば、ちょっとした記録や申し送りなども、さらに効率化できると思います」。(宮本氏)
「そのほか、一斉通知機能もあると便利です。お知らせはグループウェアや院内のサイネージに掲示していますが、手元に届くことでより確実に伝達できるでしょう。このように、ナースコールにスマートフォンを活用したことで、さまざまな活用アイデアが生まれています。ただし当院はイントラネット環境のため、クラウドサービスを活用する際は、セキュリティ面での配慮が必要となります。この辺りは厚生労働省のガイドライン(※1)でもややグレーな書き方をされているので、安全性と利便性の兼ね合いで検討したいと考えています」。(青野氏)
最後に滝口氏は、OKI への期待を次のように結びました。「当院では今後も、スマホナースコールをはじめとしたテクノロジーの活用で、医師や看護師、職員の働き方と業務効率の改善を通じて、よりよい医療サービスの提供に努めてまいります。OKI には引き続き、医療の現場に最適なソリューションの提供に期待しています」。
- ※1 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
お問い合わせ先
- ご質問・ご意見等がございましたら、以下のフォームよりお問い合わせください。
- 導入事例お問い合わせフォーム
- ※記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。
- ※Com@WILL、Com@WILLのロゴは、沖電気工業株式会社の登録商標です。
- ※Androidは、Google LLCの商標です。
- ※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ※各導入事例の記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2025年2月掲載