「日本の森林の地面は砂漠化している。」・・・今年も総指揮官として参加いただいた地元の山田さんの言葉が印象的でした。

滑車を通したロープを引っ張り、木を倒します |

こんな大木も不要な木でした |
日本の森林の地面は、間伐されていないところが多く、地面に太陽光が差し込まない。
このため、木がしっかりと地面に根を生やさない。また、栄養分となる下草が生えないためです。
2002年10月19日(土)〜20日(日)、「OKI山と緑の協力隊」29名は、今年で2回目となる「中伊豆町プログラム」に参加しました。このプログラムは、(特活)地球緑化センターの協力を得て企画された、OKIグループ単独の森林ボランティア活動で、同センターより、総指揮官の山田さんを含む4名の方にご参加・ご指導いただき、中伊豆町・町有林で間伐を行いました。
初日は、13時30分に作業を開始しました。開始に際し駐車場で全員集合! 山田さんより、作業内容・手順・安全についての説明を受け、全員が4班に分かれました。各班は、7〜8名で構成され、地球緑化センターからの3名とOKIの経験者(社員)1名に指導者になってもらいました。各自は、頭にヘルメット、腰にのこぎり、手に手袋をつけ、作業現場へ向かいました。
いよいよ間伐作業の開始です。空を木の葉で覆っている木々の中で、二股になった木や真っ直ぐに育っていない木を優先して切り倒し、太陽光が差し込むようにします。木を切る前の準備として、倒す木の出来るだけ上部にロープをかけ、倒す側の適当な別の木に滑車をつけロープを通しておきます。準備完了後は、倒す木の根元より少し上を、倒す側から中心近くまで水平にのこぎりで切り込みを入れます。次に、切り込んだ上部から斜めに切り込みをいれ三角形の切り身を作り摘出します。次に、三角形の切り込みの中心より数センチ上を目標に、裏側から平行に木が倒れない程度まで切り込みを入れます。そして、予め準備しておいたロープを引っ張り、木を倒します。倒した木は、2m間隔に切り、間伐材として活用されます。

間伐前は、木の葉が空を覆っていました |

間伐後は、太陽の光が差し込みます |
昨年は、上記の作業を繰り返しましたが、今年は、作業終了(16時)の約1時間前から新たな作業が追加されました。2m間隔に切った木で、直径10cm程度のものを探し、皮むきを行いました。山田さんとその仲間の皆さんが、天城山の遊歩道作りのボランティアをされており、皮むきした木は、そのために使われるそうです。我々が持っている道具は、のこぎりだけです。これでどうやって木の皮を剥くのか・・・叩いたり、傷をつけたり・・・試行錯誤でしたが、要領の良い人のやり方を見たり、山田さんに教えてもらったりして、"コツ"を発見した後は、みんな子どもの頃に戻ったように夢中になってしまい、作業終了時間も忘れてしまうほどでした。皮むきは、のこぎりの背を使って行いますが、皮を剥ぐと水分があるのを発見!「木は、水を栄養分として吸収している」と小さい頃学んだことを今になって実感しました。皮を剥いだ木は、各自、肩に担いで駐車場にある保管場所まで運びました。

こんな風に、木の皮を剥ぎます |

皮を剥いだ木は、1日でこんなに集まりました |
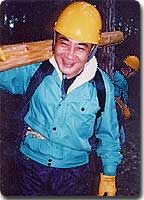
皮を剥いだ木を運ぶ
沖電気伊野専務 |
作業終了後は、車に分乗して宿舎へ。温泉につかり疲れを取った後は、食事。19時、沖電気地球環境部の高橋部長より、弊社の環境への取り組みについて簡単な説明を受けました。そして部屋を変え、森林教室が始まりました。山田さんより、森林についてのお話があり、その後、指導者も含め、参加者全員が、「今日の感想と自分にとってのボランティアとは」を話ました。森林教室では、沼津地区で用意してもらったお酒とつまみもあり、大変盛り上がりました。
2日目は、8時30分から11時30分まで作業を行いました。「中伊豆町プログラム」も今年で2回目、参加者も増えてきました。これからも、毎年行って行こうと思いますが20〜30代の社員にも大勢参加してもらいたいものです。

参加者全員で!旗も作りました。 |
|