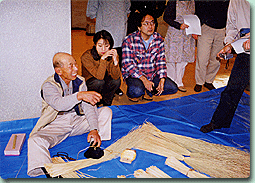
ほどけない紐の縛り方を伝授! |
2000年12月2日(土)、沖電気小金井研修センターで、昔からの日本の伝統民芸である「わら細工」を21世紀に伝えて行こうと、"みんなで「わら細工」体験!"を行い、沖電気グループの社員・家族23名が参加しました。
群馬県安中市にお住まいの農家の高橋さん(現在は庭職人)は、今年で70歳を迎えられました。小さいころより、わら細工をされており、農協などに米俵を納めたり、市で「わら細工教室」の講師をされています。安中市でも、「わら細工」のできる人は数少なくなってきたそうです。
今年の3月にご自宅を訪ね、沖電気グループ社員向けに「わら細工」の講師をお願いしたところ快く引き受けていただきました。「わら細工」に使う「わら」は、実をつける前に刈り取ったものを使います。刈り取りは8月で、「わら細工体験」は、9月以降に可能ですが、お正月の飾り物を作るので、12月にお願いしました。

2品目の完成です |
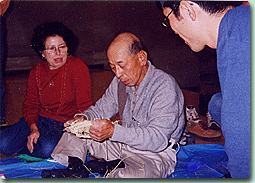
外国人奥さんも参加しました |
午後1時、参加者全員の簡単な自己紹介の後、高橋さんにご挨拶をいただき、早速作業開始です。「わら」は、1時間ほど前に、熱湯をかけてぬめし、柔らかくしておきます。最初の飾り物は、「わら」を直径10cmほどの大きさに束ねビニル紐で下部を縛ります。普通の縛り方では、二重に縛るまでは、手を離すとほどけてしまいますが、一回縛るだけで、手を離してもほどけない縛り方を教わりました。縛った上部を3等分し、左右の部分をよじり、編んで行きます。最後に真中の部分をよじり、先に編んだ2つの間に編みこんでいきます。こうして、相撲取りの化粧回しのようなものを作り、短冊に切った白い紙を編目に食い込ませ1品完成です。1時間半が過ぎました。右へよじった場合は左向きに編み、左へよじった場合は右向きに編むことがなかなか覚えられず、うまく行きませんでした。次は、ひとまわり小さい束を縛ります。縛った上部を半分に分け、さらに両方を3当分し、1品目と同様に編んでいきます。編み終わったら片方毎に輪をつくり目がねのようします。紅白の飾りつけをすれば完成です。
笑顔、会話、笑いの中で参加者それぞれの作品が完成しました。わら細工を通じてお年よりとのふれあいを楽しみ、昔の人々の知恵を知ることができました。また、この体験の3時間で見知らぬもの同士が知人のように親しくなれたような気がしました。これをきっかけに、このような活動に今後も参加して行こうと言ってくれた人が大勢いました。体験終了後の懇親会では、高橋さんより「わらぞうり」または「わらじ」が全員にプレゼンとされました。
尚、安中市の高橋さん宅より小金井研修センターまでの、「わら」の輸送は、(株)沖電気物流センターのご協力をいただきました。

全員で作品と一緒にパチ! |
|